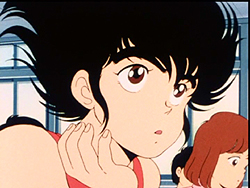 大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
ダンゴってパンツ一丁で寝ているのかなぁ。
登場人物
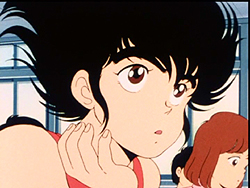 大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
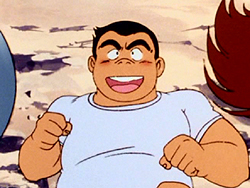 団五郎。愛称ダンゴでケンの親友。
団五郎。愛称ダンゴでケンの親友。
ケンはダンゴに、思いっきり顔を近づけて、話しかけた。
「なぁ、ダンゴ?」
「な、なんだよ?」
「すごいドキドキしてるんだな」
「えっ・・?」
「ダンゴの心臓さ」
いつのまにか、ケンがダンゴのシャツの中に手を入れて、ぶ厚い胸板に手を当てていた。
「ケ、ケン・・」
「俺、神の城でお前と生活を始めてから、ずっと一緒だっただろ? 飯を食うときも、風呂に入るときだって。
だから、俺は団五郎のことを、何でも知っているつもりになっていた。
でも、まだ知らないことがあったんだな」
「どういう意味だよ?」
「こうして、お前の体に直接触ると、感じるんだ」
「感じる・・?」
「ダンゴがいま、とても怖い思いをしていることをさ」
「分かるのか?」
「あぁ。ごめんな。夢の話を笑ったりしてさ」
ケンが意外と素直に謝ってきたので、ダンゴは目をパチクリとさせた。
「・・ケン、ありがとうな」
それは自然にダンゴの口から出た感謝の言葉だった。
ケンは柔らかい表情を浮かべながら、ダンゴに話しかける。
「実はさ、俺も夢の中でドラゴ帝国に襲われて、うなされていたことがあるんだ」
「ケンが?」
「あぁ。小さいときの話さ。そのときは相手がドラゴ帝国なのかも分らなかったよ」
「そんなことが・・」
「それでさ。ワンワンと泣く俺のことを、死んだ
爺ちゃんのふとんの中はとても暖かくてさ。俺、爺ちゃんの暖かさを感じて、怖いことも忘れたよ」
普段のケンからは想像できないような、意外な事実。
ケンにもそんな幼少の頃があったのかと考えると、ダンゴの体の緊張も徐々に解けはじめた。
ケンは、ダンゴの耳元でささやく。
「今度は俺が五郎のことを暖めてやる」
「あたため・・?」
「あぁ。五郎を暖める」
「な、なにするんだ・・?」
ダンゴは困ったような声で、返事をした。
ケンは片手をダンゴの胸にあて、もう片方の手をダンゴのお腹に伸ばした。
ケンの指がダンゴのヘソの部分に触れた瞬間、ダンゴの体がビクリッ!と反応する。
「ケン、くすぐったいよ・・」
「いいから、黙って目を瞑っていろよ」
「でも・・」
ダンゴのお腹はまん丸と太っており、とても弾力がある。
ツンと指を立てると、トランポリンのように反動でお腹が揺れるほどだ。
ケンは、ダンゴのお腹を、ゆっくりと優しく撫ではじめた。
「ダンゴのお腹って、触るとピチピチなのな」
「な、なに言ってるんだよ・・」
ダンゴは、照れくさそうに顔を赤らめる。
ケンは5本の指で、ダンゴのお腹をゆっくりと撫でまわし始めた。
指の暖かい感触が、体の中にジンジンと染み渡る。
しかし同時に、言葉にできない恥ずかしさが、洪水のように襲ってくるのも事実だった。
ダンゴの息遣いが、わずかに荒くなる。
ケンはしばらくダンゴのお腹を撫で廻した後、
人差し指をダンゴのお腹に立てて、そのままヘソからゆっくりと下に降ろした。
「はうっ」
人差し指は、お腹という山頂をゆっくりと下へなぞりながら、下半身へと移動する。
その方向にあるものを考えたとき、ダンゴは思わず声をあげた。
「ケン、それ以上は・・ダメだっ」
「ダンゴ、ジッとしてろよ」
「でもさ、でも・・」
「怖いことなんか、これですぐに忘れるさ」
「でも・・そこは・・!」
スーと降りた指が、ダンゴのブリーフのゴムに到達していたのだ。
ケンはダンゴのブリーフを、ゆっくりと撫で回した。
ダンゴのブリーフは、ケンのブリーフに比べると倍以上は大きい。
体格の差もあるのだろうが、ダンゴの飛び出たお腹や、
大根のような太ももは、子供用のブリーフでは小さすぎるようだ。
中のモノが、相当に窮屈に収められているのが分かる。
「ダンゴのパンツって、でっけーな」
「あ、あまり触るなよ・・」
「ゴムがちぎれそうなほど、パンパンに張ってるぜ」
「バカヤロ・・」
ケンの指はブリーフのゴムを通過して、さらに下へと進む。
そして、ブリーフの先端にある膨らみで、その指は止まった。
「ふあっ・・」
「ここが五郎の大切なところ・・。緊張して縮こまってるじゃないか」
「だって・・」
「いま、ほぐしてやるからな。怖いことなんかすぐに吹っ飛ぶさ」
「ほぐすって・・ひっ!」
ダンゴはケンの行動を見守ろうと考えたが、それどころではなくなった。
ケンが親指と人差し指で、ダンゴのおちんちんを摘んでいたからだ。
「ひぃ!」
「パンツに比べて、ダンゴのチンチンは小っちゃいんだな」
「お前のだって、大きさは変わらないだろ・・」
「俺のはもっと大きいぜ」
「ウソつけ」
ケンの指はまるでピアノを弾くように、ダンゴのおちんちんと思われる部分をブリーフの上から揉み漁る。
さらに、太ももの付け根を探り、股ぐらから、おちんちんをグッと掴んだ。
「ケン、そんなっ、ひぃ!」
5本の指で、しっかりとダンゴのおちんちんをいじりまわす。
ケンは親指に力をいれて、おちんちんの竿と思われる部分をグイッと持ち上げた。
(ひぃぃ、ふぁああ!)
ダンゴの体が、自然と大きく仰け反った。
(ひぃああ!)
ダンゴの未成熟な性器は、ケンの手のひらで好きなようにいじられる。
(ケン、うぅっ!)
まさか、ケンが自分のチンチンを触ってくるなんて・・!
他人に、自分のチンチンを触られる、いや揉まれるなんて初めての経験だ。
一瞬、ダンゴはケンを怒鳴りつけて抵抗しようかと考えた。
しかし、ケンの言葉が脳裏によぎる。
<俺が五郎のことを暖めてやる>
その言葉がダンゴの頭から離れず、どうしたらよいのか激しい葛藤を生み出していた。
チンチンを触られるのは、顔から火が出そうなほど恥ずかしい。
でも、ケンの優しい言葉を信じたい。
だから、ダンゴは目を瞑り、真っ赤な顔で歯を食い縛って耐えた。
ケンはダンゴのおちんちんを揉みながら、感じていた。
(ダンゴのヤツ、すげー興奮してる!)
なぜなら、ダンゴのブリーフの中のモノが、どんどんと硬さと大きさを増していたからだ。
さらに胸に当てている手から、ドクンドクンという心臓の鼓動が、手に取るように伝わってくる。
自分も
恥ずかしさと同時に、気持ちよさを感じていたなと、ケンは小さい頃の気持ちを思い出していた。
ケンは、さらにブリーフの上から、ダンゴの玉袋と思われるところを優しく握る。
「これがダンゴの・・」
「ひっ、ふあっ、そこはぁ!」
ケンの言葉に、思わず悶えるような声をあげるダンゴ。
気持ちよいやら、くすぐったいやら、複雑な感覚。
ブリーフの上からとはいえ、ケンの指が玉袋の撫でるたびに、ダンゴは大きな体を揺らし始めた。
「おいダンゴ、あまり暴れるなよ」
「ふへぁ、んぐぐ・・無茶いうな」
ケンは、しばらくおちんちんを揉み続けた。
すると、ダンゴのブリーフは異様な形で盛り上がっていた。
もちろん、その形状はふとんの中なので見えなかったが、
手の感触から、ダンゴのおちんちんが、勃起してパンパンになっていることは明らかだった。
ケンは耳元で囁く。
「ヘヘッ、気持ちいいだろ?」
「べ、別に気持ちよくないよ・・」
「素直じゃねぇな」
なかなか素直な気持ちを出さないダンゴに、ケンはだんだんイラついてきた。
テントを張るようにそそり勃った、ダンゴの竿と思われる部分。
そこをマイクのように握り締めて、ギュッと思いっきり締め上げた。
「ぎゃあああ!」
「勃起すると、でけーじゃんか」
ダンゴは全身に電気が走ったかのような衝撃を感じて、絶叫を漏らす。
ケンはダンゴの竿をブリーフの上から掴み、そのまま亀頭と思われる部分をなぞった。
ダンゴの亀頭はカチンカチンに膨れ上がる。
さらに、ダンゴは全身の痙攣が止まらない。
ケンは亀頭をグイグイと押し込み、なぞり続ける。
「んあっ、ケン!」
「ダンゴって、けっこう敏感だな。チンチンがドクンドクンっていってるぜ」
「ふあっ、はう!」
「どうした、ダンゴ?」
「・・・頭が真っ白になって、なにがなんだか分からないよ・・」
「えへへ。俺もそうだったぜ」
「えっ?」
ケンの意外な言葉に、ダンゴはギュッと瞑っていた目を開ける。
そして、ケンの顔を見ると、それは不思議と柔らかい表情に見えた。
「昔、
「ケンが?」
「ああ」
「そういえば俺、いまは気持ちよくて・・怖いことなんかすっかり・・」
「やっぱり気持ちよかったんだな、ダンゴ!」
その言葉に、ダンゴは真っ赤になってコクリとうなづいた。
「もう怖い夢を見ても、悲鳴あげるんじゃないぞ」
「あぁ・・。ケンありがとうな」
「俺とお前の仲だろ」
「うん・・。今度はケンのも触らせてくれよな」
「え、俺の・・? ハハハ、機会があったらな」
そういうと、ケンはダンゴの股間から手を放し、ニコッと微笑む。
ダンゴの顔にも、照れくさそうな笑顔が戻っていた。
次回へ続きます。