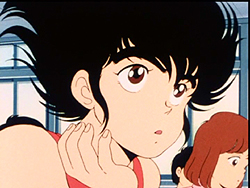 大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
エロなのかサスペンスなのか、はっきりしろって感じですよねw
登場人物
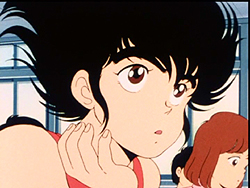 大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
 団五郎。愛称ダンゴでケンの親友。
団五郎。愛称ダンゴでケンの親友。
(はむ・・もぐ・・)
ケンは舌で、ダンゴの唇を丁寧にねぶっていった。
生暖かい舌と、かすれた唇の感触に、ダンゴの目はトロンと溶けそうになる。
柔らかくて、気持ちよくて・・。
ダンゴはそのまま快感に身を任せようとしたが、
ケンと男同士でキスをしていると考えると、相当に恥ずかしいことに気がついた。
ダンゴは顔を真っ赤にして、ケンの舌を拒もうとした。
(はむ・・それ以上はダメだ・・)
しかし、ケンはダンゴの唇を、
おいしいフルーツでも食べるかのように、舐め尽して愛撫していた。
ケンの舌が、執拗にダンゴの舌を追い回す。
そのうち、ケンの舌が、ダンゴの舌にからみつき、唾液が流れ落ちた。
(ああっ、なんだこの感触・・)
(はぐ・・もぐ・・)
いつのまにか、ダンゴは瞼を閉じて、ケンの舌を追い求めていた。
舌と舌が絡み合うたびに、嫌なことを1つずつ忘れていく。
いままで感じたことがない、打ち震えるような快感。
そして、自分がケンに守られているような安心感が、ダンゴの心を覆っていった。
同時にしょっぱい涙が、ダンゴの頬から零れる。
(ケン・・もっと・・!)
(ダンゴ・・)
ペチャッ、ペチャッとした音が、部屋に響き渡る。
ダンゴは、自分の体に乗っかるケンの背中に手を回して、ギュッと抱きしめた。
抱き合ったまま、しばらく熱い接吻をし続けるケンとダンゴ。
ダンゴは大きく広げた鼻から、熱い息をただ吐き続ける。
(ふぅふぅ・・)
(ダンゴ・・)
一体、何度唇を合わせたことだろう?
ケンの唇が、フッとダンゴの唇から離れたとき、
2人の唇のあいだに、細い唾液の糸が引かれていた。
ケンとダンゴは、数センチの距離でしばらく見つめあう。
先に口を開いたのはケンだった。
「へへっ。俺のファーストキスを、ダンゴにあげちまった」
「ケン・・・」
「本当は好きになった女の子にあげようと思っていたのによ。でもダンゴのためだから、しかたねーな」
「ごめん・・俺のために・・」
「気にするなよ。本当のこというと、俺のファーストキスは、
「それって、もしかして・・?」
「あぁ。俺がドラゴ帝国に襲われる怖い夢を見たときに、爺ちゃんが同じことをしてくれた」
「そっか・・。ケン、ありがとう」
いつのまにか、ダンゴの顔つきは不思議と柔らかくなっていた。
ケンはダンゴを下に見つめながら、話しかけた。
「ダンゴ?」
「なに・・?」
「落ち着いたか?」
「あぁ。ケンのおかげだ」
「もう、夢なんかでビビるんじゃねぇぞ。いつまでもガキじゃないんだからさ」
「もう大丈夫だ」
「明日からきちんと1人で起きろよ」
「わかった」
ケンはダンゴの返事に満足な顔をする。
そして、お腹に乗ったまま、ダンゴに笑いかけた。
ケンは腹の上に乗ったまま、麓を見下ろすようにダンゴの体を見つめる。
「ん・・?」
ダンゴのシャツは汗で濡れているのか、はち切れんばかりにピッタリと肌に張り付いていた。
逞しい胸の盛り上がりが浮き彫りになっている。
「ケン、どうしたんだ?」
「ダンゴの体って、よく見るとすごいな・・」
「なにがだよ・・」
いつもは気にしないが、いざこうしてマジマジと見つめると、ダンゴの肉付きはすごい。
筋肉と脂肪のつき方が、ケンとはまるで違うのだ。
首から腹にかけて、ずっしりとした重量感。
二の腕も、はち切れんばかりに、袖からむき出しになっている。
暗がりの中でも、乳首が透けて見えるくらいに、胸は豊満で盛り上がっていた。
「あのさ・・」
「ケン?」
「ダンゴの体、もっと触りたくなっちまった」
「ええっ?」
「これからやることは、爺ちゃんに教えてもらったことじゃない。
お前の体をジッと見ていたら、もっとダンゴを気持ちよくさせたくなっちまってさ」
「気持ち良く・・?」
「ファーストキスのついでだ。俺の好きにさせてくれよ。な、いいだろ?」
その言葉を聴いて、ダンゴはゴクリと唾を飲み込む。
一体、"好きにさせる"とは、どういう意味なのか?
どうしようかと迷ったが、いまのダンゴにとって、ケンの行為を拒絶する理由は何もなかった。
ダンゴは顔を赤くしながら、ケンに返事をした。
「いいよ、ケンの好きにして」
「ダンゴ・・」
「ケンに俺のすべてを知ってもらいたいんだ。いまだって、俺のことを支えてくれたのはケンなんだから」
そういうと、ダンゴは自分の言ったことが恥ずかしかったのか、視線をそらした。
「ああ。任せとけ、ダンゴ!」
ケンは得意気な笑顔をみせると、ゆっくりと右手をダンゴの胸に伸ばす。
そして、シャツの上からダンゴの盛り上がった乳首を、人差し指と親指でギュッと摘んだ。
「ああっ!」
ビリッと電気が走るような刺激に、無意識に声を出してしまうダンゴ。
ケンはそのままダンゴの胸肉を鷲づかみにし、ガシッと揉みはじめた。
「ダンゴの胸ってすげぇ!」
「んあっ、ケン、そこは・・!」
「プリンみたい」
「あうっ」
「いつも風呂でお前の体を見ていたけどさ。実際に触ると、とっても柔らかいのな」
筋肉でガッチリしていると思っていたダンゴの胸板。
しかし、予想外の揉みやすさに、ケンは夢中でダンゴの胸を触りまくった。
もう片方の手を、ダンゴの左の乳房に伸ばす。
両手で、ダンゴの乳房をグイグイと揉みほぐしていく。
ダンゴの胸は弾けばブルンと揺れるような、弾力があった。
それにしてもダンゴは肉付きがいい。
こりゃまるで肉まんだなと、ケンは感嘆の声をあげながら、
ダンゴの乳房を円を描くように揉んでいった。
「あああっ・・そこは・・」
果たして、男が胸を揉まれて気持ちいいのかと、ケンは一瞬考えたが、
ダンゴが言葉にならないかすれた声で反応するのを見て、快感にはまっていることを確信した。
「ダンゴの胸って、まいやゆいよりも、大きいよな」
「は、あっ! そ、そんなこと・・」
「まいの胸はペチャンコだからよ。ダンゴのほうがよっぽど女の子みたいだぜ」
「バカなこというな・・」
「それに、このぷるんぷるんのダンゴの体さ・・なんていうか・・」
「・・?」
ケンは、ダンゴの胸を揉むのをやめると、顔をダンゴの胸の谷間に埋めた。
「ケン?」
「・・・」
「ケンってば?」
「こうやって胸の中に顔をうずめていると・・俺もなんだか気持ちよくなってきた」
「どういう意味?」
「分からねぇけど、懐かしい感じがするんだ」
「懐かしいって?」
「シャツに染み込んだダンゴの汗の匂いがさ・・。心が落ち着くんだ。ごめん、言葉でうまく言えないや」
「ケン・・」
ケンは顔を起こして、もう一度ガシッとダンゴの乳房を鷲づかみにする。
そのまま乳房の真ん中を盛り上げるように、ギュッと掴んだ。
「はあっ!」
「じゃ、今度は吸うからな」
「吸うって・・おい・・」
ダンゴの素っ頓狂な声を無視して、
ケンはシャツの上から、ダンゴの乳首に喰らいついた。
シャツに染み付いたダンゴのしょっぱい味。
その味を噛みしめながら、ケンは舌で乳輪の先端をチロチロと突く。
「ふやああっ、ケンっ!」
「気持ちいいか?」
「なんか変な気分に・・」
ケンはさらに、唇と歯を使って、ダンゴの乳首の先端を軽く噛んで見る。
「ぎゃ!」
ジンジンとした甘い刺激が、ダンゴの体中に染み渡っていく。
乳首の快感に耐え切れなくなり、ついに全身を痙攣させはじめた。
まだ、軽く噛んだだけだというのに、ダンゴは随分と敏感に反応するなとケンは思った。
(ダンゴのヤツ、乳首がモロに感じるみたいだな)
ケンがしばらく乳首を愛撫したあと、唇を離すと、
ダンゴのシャツは唾液ですっかり濡れており、乳首はシャツの生地を突き上げるほどに勃ち上がっていた。
乳輪が、透けて見えそうだ。
(よし、今度は右の乳房を吸っちゃえ)
ケンはダンゴの左胸をゆっくりと揉みながら、今度は唇を右の乳房の上に移動する。
唇と舌で、ダンゴの汗で透けている乳首をコロコロと転がしてみる。
「はあっ、ぐぐっ、ふは!」
「ダンゴって、めちゃくちゃ感じやすいんだな」
「そんなことあるか・・ああっ」
熱い息を吐き、悶えるダンゴ。
ケンはまるで、お母さんのおっぱいからミルクを吸いだすかのように、ダンゴの乳首をしゃぶりついた。
チュウチュウと音がする。
ときに甘噛みし、愛撫していく。
「あっ、ダメだ、ケンー・・」
ザラついた生地の上から、ジンジンと染み渡る感触に、ダンゴは打ち震える。
シャツの上からしゃぶっただけで全身を悶えさせるダンゴを見て、
もし直接刺激したら、ダンゴが悶え狂ってしまうんだろうなと、ケンは妙なことを考えたりもした。
ケンはしばらく胸を揉み続ける。
ダンゴはその間、ハァハァと息を荒げていたが、
ふと気がつくと、ケンの手の動きが止まっていた。
「あれ・・ケン?」
「ごめん・・俺のほうが気持ちよくなって・・・・」
「ケン、そのまま寝てもいいよ」
きっとケンも気持ちよくなったんだろうなと、ダンゴが一瞬気を許した瞬間・・。
「ひゃあ!」
下半身にビリッと電気が流れるような感覚が走った。
「ダンゴのチンチン・・」
いつのまにか、ケンの顔がダンゴの下半身に移動し、
ブリーフの上からダンゴのおちんちんを、パックリと食べていたのだ。
ダンゴのブリーフは、三角形にテントを張っていた。
先ほどから胸をたっぷり揉まれて、おちんちんにも影響が出てしまったらしい。
ケンは、ダンゴの大切なところを、はむはむと唇で軽く包み込んでいた。
「ションベン臭いけど、ダンゴの匂いがする・・・」
「うあっ、あやや!」
ケンの唇が、ダンゴの亀頭を甘噛みするたびに、ダンゴはガクガクと体を震わせた。
「これがダンゴのチンチン・・俺の大切な・・」
「はんああっ!」
「・・・スー・・ハー・」
「ケン?」
いつのまにか、ケンから透き通るような寝息が聞こえていた。
(なんだよ、ケンのヤツ、寝ちまったのかよ・・)
一瞬、ケンを起そうかと考えたダンゴだが、まだ起きるまでには時間がある。
(俺のチンチン咥えたままなんだけど・・。とりあえずこのままにしておくか)
ダンゴは窓から陽が昇るまで、自分の股間に顔を埋めるケンの背中を、ずっと撫でていた。
もしこのまま時が止まってくれたら、ずっと幸せでいられるのにとダンゴは思いながら、
安堵の笑みを浮かべていた。
──その日の朝の食卓。
学校に遅刻しそうになったケンとダンゴは、急いで朝のご飯と味噌汁を食べていた。
「おい、ダンゴ! なんで、起こしてくれなかっんだよ」
「ごめん・・。なんかホッとしちまって」
しかし、ダンゴの様子がいつもより暗い感じがする。
「目玉焼き、いただきっ!」
ダンゴの目の前の皿にある目玉焼きを、ヒョイっと箸で奪い取る。
「ケン、なにすんだよ! 俺の目玉焼きだぞ!」
「へへーんだ! あまり暗い顔するなよ!」
いつも通りのダンゴの反応に、ケンは少しだけ安心した。
そのとき、つけっぱなしにしていたテレビから、緊急報道が流された。
<本日、釧路市の街中で死体が発見されました。
郵便局に勤める50歳の男性で、鉄棒で心臓を刺されて死亡した模様です。
現在、詳しい捜査を進めていますが、目撃者は現在のところ・・・>
ケンはテレビに流れる報道を見て、おもむろに口を開いた。
「残酷な殺され方だな・・って、おいダンゴ!!」
「えっ?」
「醤油!」
「しょうゆ・・?」
「なにボケッとしてんだ。目玉焼きに、醤油をそんなにかけてどうするんだよ!」
「ああっ! ごめん・・」
ダンゴは、醤油で真っ赤に染まる目玉焼きを見て、心のなかがざわざわとした。
(この郵便局のおじさん・・・夢の中で俺のことを襲った人じゃないか!
殺されたってどういうことなんだ・・まさか俺が・・)
次回をお楽しみに(←ォィ)