 大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
エロそうでエロくない?
登場人物
 大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。
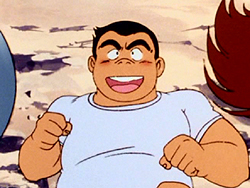 団五郎。愛称ダンゴでケンの親友。
団五郎。愛称ダンゴでケンの親友。
──次の日。
「おでんの具がないなら、もっと早く言えよな・・」
ダンゴは1人でブツブツと文句を言いながら、陽が沈む街道を歩いていた。
この時間は、普通ならばダンゴが夕食を作っている時間だ。
しかし、今日はたまたまダンゴの母親が、おでんを作るという。
ところが、肝心の材料が足りないから、ダンゴが買ってくることになってしまった。
(早く買い物を済ませて、かあちゃんのおでん食べなくっちゃ!)
すでに、お腹の虫が「ぎゅ〜」と音を立てていたのだ。
(空が急に暗くなってきたな・・急がないと・・)
近道をするために、裏路地に入ろうとしたとき。
後ろから声をかけられた。
「おい君、ちょっと道を聞きたいんだが」
「え、俺?」
「ああ。この辺りは慣れないもので、道に迷ってしまってね」
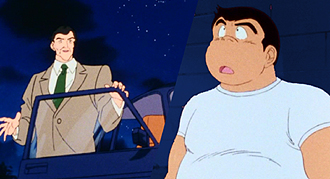
ダンゴが自分の顔を指差しながら振りむくと、そこには高級車に乗った1人の男性。
年は30歳か40歳くらいだろうか?
背広を着て、きちんとした身なりをしていることから、会社の偉い人なのかなとダンゴは思った。
「おじさん、どこから来たの?」
「札幌からきたんだ。ここに住所を書いた紙がある。すまないがこちらに来てくれないか」
「はい!」
元気よく答えたダンゴは、車のある場所へと歩を進める。
ダンゴが車の中を覗こうとしたとき。
突然、男がダンゴの太い二の腕を掴んだ。
「な、なにするんです!?」
「フフフッ」
ダンゴが振り向くと、男は白目を剥き出しにして、酸のような液体を垂らしていた。
まるで、ゾンビのようだ。
「うわぁ!!」
そのおぞましい姿に驚いたダンゴは、男の腕をはずそうと必死にもがいく。
「おじさん、なにすんだよ!」
「ほう、子供にしては、なかなか腕力があるな」
「放して!」
「団五郎・・。大牙剣の友達、いや両親のいない大牙剣が、心を許す唯一の人間だ・・」
「どういう意味!?」
「フフフッ。いい肉付きをしているではないか」
「な、なに言ってるの!?」
「ドラゴ帝国によって、これからお前の体はもてあそばれるのだ。大牙剣の一番大切なものをめちゃくちゃにしてやる」
「ド、ドラゴ帝国だって!?」
ダンゴは背筋を凍らせながら、腕を払いのけようと必死にもがく。
そのとき、ダンゴの視界に巡回している警察官が入った。
条件反射のように、ダンゴは大声で怒鳴った。
「おまわりさん、助けて!!」
「どうした、何事だ?」
ダンゴの叫び声に気がついた警察官は、小走りにこちらに向かってくる。
偶然とはいえ、これを天の助けと言わずに、なんと言おうか。
ダンゴは「うわぁ」と叫びながら男の腕をはずし、一目散に警察官に駆け込む。
先ほどの倍の大きさで、必死にわめいた。
「おまわりさん! この人、ドラゴ帝国の生き残りだ!」
「ドラゴ帝国だと?」
「本当だって! 早く、なんとかして!」
「あぁ。分かった。安心したまえ」
警察官は足音もなく、ダンゴに近づいた。
そのまま薄気味悪い笑みを浮かべて、ダンゴの豊満な腹に、強烈なパンチをぶち込んだ。
「ほげっ!」
お腹を抱えてもがきながら、その場にうずくまるダンゴ。
「がっ、はっ・・どうして・・」
ダンゴは激痛の走る腹部を押さえながら、視線を上に向ける。
そこにはあざけり笑う、警察官の姿があった。
「ググッ、もう逃げ場はないぞ、団五郎」
「がはっ、げほっ」
「なぜなら、私もドラゴナイトなのだから」
「そ、そんなバカな・・」
「これから俺たち2人で、お前の体をもてあそんでやるぜぇぇ」
警察官の服がビリビリッと乾いた音を立てて、破けていく。
服の下から、青いイタチの化け物のようなドラゴナイトが現れた。

ダンゴの目の前に、不気味な青いドラゴナイト。
口からヨダレを垂らす姿は、野獣が飢えているように見える。
さらに後ろには、酸をポタポタと垂らした、ゾンビのような男。
「ひぃえええ!」
ダンゴは2匹の化け物に挟み撃ちにされ、腰を抜かしてヘナヘナと座り込む。
恐怖で、顔が凍りついた。
「俺をどうしようっていうの!?」
ダンゴは左右の隙を伺うが、とても逃げられそうにない。
そうしているうちに、ゾンビのような男は、ダンゴの背後にゆっくりと近づた。
ダンゴの後襟を掴んで持ち上げる。
そのまま首根っこに腕を回して、首締めをした。
「あがっ!」
「ハーハハッ」
「2人がかりなんて卑怯だぞ・・」
「卑怯? 最高の褒め言葉よ」

ゾンビのような男が、後ろから話しかける。
「このまま、お前を殺すのは簡単だ。しかし、それでは我々の欲求が満たされないのでな」
「うぐぐ・・!」
「実は我々の一番の好物は、人間の精液なのだ」
「なんて・・?」
「人間の精液だ。特に若い人間のものほど美味だ。
これからお前の体を、じっくりといたぶらせてもらう。
壮絶な快感に打ち震えながら、たっぷりと美味いものを出してくれよ」
「な、なにする気だ・・」
「その青いドラゴナイトは、特にお前のような太った少年が大好物でな」
「ええっ!?」
「お前は想像以上に良い体をしているようだ。
これからたっぷりと愛撫してやる。実は私もお前のようなデブはけっこう好きでな」
ゾンビのような男は、再びダンゴを羽交い絞めにする。
そして、ダンゴの豊満な胸とお腹を、青いドラゴナイトに突き出した。
まるで、ダンゴの体を好きにもてあそべと言わんばかりに。
「フフフッ、人間は服を着て、性器を隠しているらしいな。
まずは我々の目の前にモノをさらけだし、たっぷりと屈辱を味わうがいい」
「わわっ、やめろ!」
ゾンビのような男の背中から、突然白い触手のようなものがフワッと空に伸びる。
触手は、にゅるにゅると移動しながら、ダンゴのシャツを下から掴んだ。
そして、まるで医者に胸を診察されるかのように、シャツが襟元までめくりあげられる。
「あわわわっ」
ダンゴのピチピチな胸とお腹。
青いドラゴナイトは、ダンゴの豊満な体を見て、思わず舌なめずりをする。
「グィッ、めちゃくちゃうまそうな体じゃないか」
「ひぃえ!」
青いドラゴナイトは、ニヤッと笑いながらダンゴの体に近づく。
ダンゴのズボンに手をかけ、カチャカチャとベルトをはずし始めた。
その光景を見て、ダンゴは不安のどん底に陥った。
精液だの、好物だの、先ほどから話していることは・・?
さらに、ベルトをはずすということは、間違いなくパンツまで脱がすのだろう。
ドラゴナイトがしようとしていることを理解した瞬間、
ダンゴは声を「やめろぉぉ!」と大きな声で怒鳴りあげていた。
ダンゴは目の前の現実から逃げ出そうと、目をギュッと瞑って震えだす。
そして、足をバタバタと動かした。
「ええい、おとなしくしていろ!」
背後の男は、さらに別の触手を伸ばし、ダンゴの左右の足首をそれぞれ巻きつかせた。
そのまま大の字になるように、両足を完全に固定する。
「ひゃああ!」
必死に手足に力を入れてみるが、微動だにしない。
まるで触手という十字架に、手足を拘束されたかのような状態だ。
そのうち、「ガチャ」だの「ジィィ」だの、チェックを下ろすような音がして、
ズリッとズボンが膝下まで落ちてしまったのだ。
「ほほう、いい肉付きだ」
背後の男の言葉に、ダンゴは恐る恐る視線を下に持っていく。
案の定、ズボンは使い物にならないくらい破れた状態で、膝まで落ちていた。
シャツは触手にめくりあげられ、ただ白いブリーフが最後の砦として残っているだけだった。
ダンコの体は、白いブリーフを除くすべての部分が、あらわになってしまったのだ。
ダンゴの顔は温度計が振り切るように真っ赤になっていく。
「ほう、ズボンの下にまだ服を着ているのか」
「パンツはやめて!」
「グヘヘッ、まだガキのくせにでかいお腹だぜ。
それに太ももがパンパンに張ってはみ出してるわ。真ん中の膨らみも美味そうだぜぇぇ」
ダンゴの太ももは、すべすべで傷ひとつなく、小麦色に焼けていた。
ブリーフの中心に、ポツンとした膨らみ。
ダンゴはその膨らみを隠そうと、必死に足を交差させてモジモジとさせる。
「コイツ、生意気にチンチン隠そうとしてやがるぜ」
「見るなぁぁ」
「グェェ、中のモノを想像しただけで興奮してきたぜぇ」
ダンゴのムチムチした肉付きの良さに、青いドラゴナイトは舌から唾液をポタポタと垂らせる。
ダンゴは目を瞑り、真っ赤な顔でこの状況を逃避しようとしていた。
「よし、次はパンツを下ろすとしよう」
その言葉を聞いて、ダンゴは体をビクンッ!と反応させる。
「おい、まだ脱がせてないぞ。可愛いヤツめ」
「やめろ」
後ろの男は、目で青いドラゴナイトに合図をする。
青いドラゴナイトは、ダンゴのブリーフのゴムにゆっくりと手をかける。
その様子を見て、ダンゴは穴があったら入りたくなるほどの羞恥心に襲われた。
「お願いだから、やめて!」
「この膨らみからして、中のモノは相当に小さいぜぇ」
「俺を裸にしてどうするつもりなんだ」
「決まってるだろ。美味いモノが食べたいんだぜ」
「訳わかんないこというな!」
ダンゴは必死に言葉で抵抗を試みるが、それをドラゴナイトが理解できるとは到底思えなかった。
青いドラゴナイトは、指をブリーフのゴムに手をかける。
そのまま勢いよく、ズリッとブリーフを膝下まで降ろした。
その瞬間、ダンゴのピーナッツのようなおちんちんが、ポロンと小さな音を立てて上下に揺れた。
「あああっ・・・」
下半身に感じる冷たい風。
ダンゴは声にならないかすれ声をあげると同時に、ギュッと目を閉じて震えだした。
そんな穢れないダンゴの姿を見て、2匹のドラゴナイトはニタッと笑みを浮かべる。
「グェー! ピンク色で綺麗なチンチンだぜぇ。全然使ってないな」
「皮がかぶったままだ」
「ちっちぇな」
「まだ精通してないんじゃねぇかぁぁ?」
次々に浴びせられるドラゴナイトの言葉責めに、ダンゴはただ歯を食いしばって俯いていた。
青いドラゴナイトは、ダンゴのおちんちんをゆっくりと覗き込んだ。
わずかに震えるダンゴのおちんちんは、少々陥没気味で、皮がかぶっていた。
「このままじゃ、じっくり見られないぜ」
青いドラゴナイトは、股ぐらの中に縮こまっているダンゴのおちんちんを、親指と人指し指で器用に摘む。
そのまま強引に、前に引っ張り出した。
「ひぃあ!」
「ほほう、可愛いおちんちんだぜ」
「ううう・・」
「どうした? そんなに恥ずかしいのか、団五郎?」
「くぅぅぅ・・」
「グェェ、舌でたっぷりと舐めつくしてやる」
おちんちんを間近で見られるという屈辱に、ダンゴは歯を食いしばって耐えようとした。
そんないたいけなダンゴの姿に、2匹のドラゴナイトは悪魔の笑みを浮かべていた。
やっていることは相変わらずですが(^^;