 花園ユーミ。花の国に選ばれた女の子だが、男の子にも負けないアクティブな性格。
花園ユーミ。花の国に選ばれた女の子だが、男の子にも負けないアクティブな性格。
話がなかなか進みませんが・・・。
登場人物
 花園ユーミ。花の国に選ばれた女の子だが、男の子にも負けないアクティブな性格。
花園ユーミ。花の国に選ばれた女の子だが、男の子にも負けないアクティブな性格。
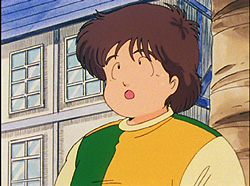 三沢健太。幼少の頃からのユーミの友達で、ユーミのことを愛おしく思っている。
三沢健太。幼少の頃からのユーミの友達で、ユーミのことを愛おしく思っている。

「ユーミさん、健太くん、いらっしゃい」
ユーミと健太は、ケシ丸とかき丸とそっくりな妖精たちに歓迎されていた。
(随分と妖精さんがいるんだな・・・)
大地を覆いつくすほどの、たくさんの妖精。
ケシ丸やかき丸とは微妙に色が違ったり、形が違ったりしているようだ。
健太は、目の前の不思議な光景に戸惑いながら、「ヘヘッ」と照れながら頭の後ろを掻く。
周りの景色に目をやると、枯れた花や荒廃した大地が続いている。
(ここが本当に花の国なのかな・・?)
花の国というわりには、随分と寂れた世界だ。
イメージとは、だいぶかけ離れている。
しはらくすると、杖を突いたヨボヨボの妖精が前に進んできた。
「よく来てくださったな。ユーミさん」
「あなたは?」
「私は花の国の長老ですじゃ。わざわざお呼びして申し訳なかったのぉ」
「花の国はいまどうなっているの?」
さっそくユーミは花の国の現状について、長老に尋ねた。
「・・・と、そういわけなんじゃ」
長老は、花の国で起こっている事件について、ユーミと健太に語った。
健太は「ウーン」と目を細めながら、長老に質問する。
「ねぇ、長老?要するに氷の王って悪いヤツを、花の国から追い出せばいいんでしょ?」
「そうじゃ」
「どうすれば追い出せるんですか?」
「まずは、花の女王を取り戻して欲しいんじゃ」
「花の女王?」
「花の女王は氷に閉じ込められておる。もし女王を眠りから覚ますことができれば、
この世界は元に戻り、ユーミさんも魔法が使えるようになるはずじゃ」
「そっか、女王が目覚めれば・・・」
健太は長老の言葉の意味を知り、改めて周りの景色を見渡す。
(この世界が枯れた花ばかりなのは、氷の王のせいなんだ。女王が目覚めればすべて元に戻るのか・・)
ウンウンと頷きながら、納得した。
ユーミは1人納得する健太を横目に、長老に話しかける。
「長老さん、氷の王からどうやって花の女王を取り戻せばいいんですか?」
「それが、分からんのじゃ・・・」
「えーっ?なによそれ?」
「そのために、ユーミさんと健太くんに来てもらったんじゃ」
「うーん、どうしよう・・・」
首を傾けて悩むユーミに、健太はやんわりと話しかける。
「ユーミちゃん、僕達で考えればいいじゃないか」
「うん、そうね!」
「本当にすまんな・・ユーミさん、健太くん」
長老は申し訳なさそうに、話を続けていく。
「ただ、氷の王は美しいものを常に求めているんじゃ。
そこになにか状況を打破できるヒントがあるといいんじゃが・・」
「美しいもの・・?」
ユーミは顎に指を当てて、荒廃した大地に視線を向けた。
健太は、クイクイッとユーミの袖を引っ張りながら話す。
「ねぇユーミちゃん、どうしようか?」
「うーん・・・まずは氷の王に会ってみましょうよ」
「えーっ。だって、会った途端に殺されちゃうかもしれないよ」
「もう。健太くんはいつも弱虫なんだから」
「そんな。慎重に考えないと危ないじゃないか」
「大丈夫よ」
一体何の根拠をもって、ユーミは大丈夫と言っているのだろうか?
(どうせ、ユーミちゃんのことだから、行き当たりばったりなんだろうなぁ・・)
いつものユーミの調子に、健太は「ふぅ」と肩を落とした。
そんな健太をみて、ユーミはちょっと怒ったような口ぶりで反論する。
「じゃあ、健太くんには何か考えがあるっていうの?」
「・・・」
そんな都合の良いアイデアなど、咄嗟に浮かぶわけがない。
(しょうがない、行くしかないか・・・)
ユーミが一度言い出したら聞かないことは、当の昔に分かっていることだ。
もはや提案を飲んで氷の王に会いに行くしかなかった。

・
・
・
「わぁ、飛行機って楽しい!」
ユーミは、気持ちよさそうに叫んでいる。
ユーミと健太は、妖精たちが発射してくれたグライダーを使って、氷の王がいるという洞窟に向かっていた。
空を駆け抜けるグライダーは、とても心地よい風を感じる。
グライダーは、おんぼろで原始的な作りではあったが、操縦どおりに飛んでいるようだ。
「フンフン」と鼻歌まじりに操縦するユーミ。
一方の健太は、なぜか真っ青な顔をしている。
「あれ、健太くん? どうかしたの?」
「あのさ・・・僕、黙っていたけど高所恐怖症なんだよね・・」
「えーっ! 健太くんって、ほんっとうに弱虫なのね!」
「大きな声出さないでよ・・グライダーが揺れるじゃないか」
グライダーの操縦席を必死にしがみつく健太。
目を閉じて、下を見ないように必死だ。
「もう、健太くんなんか連れて来たって、何の役にも立たないじゃないの!」
「ひ、ひどいよ、ユーミちゃん・・・」
ユーミの言葉に、いまにも泣きそうになる。

健太は薄目を開けて、横にいるユーミにぼやいた。
「ねぇ、ちょっと疑問に思ってたんだけどさ・・・」
健太はブルブルと震えながら話しかける。
なにか話していないと、失神してしまいそうなのだ。
「え、健太くん、なに?」
「ユーミちゃんが、どうして花の妖精さんに選ばれたの?」
「どういう意味よ!?」
「いやその・・だって、他にも花が似合う、おしとやかな女の子はたくさんいるじゃないか」
「なによそれ! 私が選ばれちゃいけないっていうの?」
「そんなことはないけど・・・」
「頭がいいから選ばれたのよ」
「えーっ! ユーミちゃんは算数のテスト、この間25点だったじゃないか」
「そんなの関係ないでしょ!」
「国語だって、理科だって・・・」
「もう、そんなこと今はどうでもいいでしょ!」
ユーミはムッとした表情で、操縦桿を強く握り締める。
そして、大きくグライダーを蛇行させる。
「うわっ!ユーミちゃん、やめてよ!」
「健太くんは、おちんちんついてる男の子なんでしょ!本当に頼りにならないわね」
「そんなエッチな言葉使わないでよっ」
「分かったぁ。健太くん、本当はおちんちんついてないんでしょ?」
「小さい頃に、ユーミちゃんはお風呂で僕の裸みてるじゃないかっ」
「あら、そうだったかしら?」
ジェットコースターのように、グライダーを自由に操るユーミ。
「ぎゃあああ!」
健太は目を回して、失神寸前だ。
しばらくすると、グライダーは氷の王がいる洞窟の近くに着陸した。
「ふぅ・・・死ぬかと思った・・」
健太はぐったりとした様子で、グライダーからゆっくりと降りた。
「もうっ、健太くんは男の子なのに全然役に立たないんだから。そのまま気絶してればよかったのに」
「そ、そんな・・ひどいよ・・」
ユーミの容赦ない言葉が、健太の胸にグサグサと突き刺さる。
たしかに、自分が頼りないことは分かっている。
しかし、それを現実として突きつけられると、さすがに落ち込んでしまうのも事実だった。
「健太くん、何をもたもたしてるの?」
先ほどの言葉はすでに忘れたのか、ユーミは洞窟のある丘に向かって歩き出している。
(もう、ユーミちゃんは本当に勝手なんだから・・)
健太は内心ムッとするが、これがいつものユーミのペースなのだ。
「ユーミちゃん、待ってよ!」
仕方ないなと思いながら、先を歩いているユーミのあとを追う。
(僕、こんなんでユーミちゃんの恋人になれるのかな・・)
落ち込んで、ため息交じりの健太。
ユーミと健太は、氷の王がいるという洞窟の入り口に到着した。
洞窟の中を覗いてみると、岩肌がすべて氷で覆われており、寒々した感じがする。
健太は、その薄気味悪い洞窟を見て、ゾクッと体が震えた。
「なんか不気味な洞窟だなぁ・・」
「さぁ、健太くん、行きましょ」
あっけらかんとした声。
ユーミには、怖いとか恐ろしいという感情がないのだろうか?
健太は困ったように頬をかきながら、ユーミに話しかける。
「でも、危ないんじゃないのかな・・?」
「なによ、健太くん。ずっと怖がってばかりじゃない!」
「でも、いきなり襲われたりしたら・・」
「そのときは、健太くんが守ってくれるんでしょ?」
突然自分を頼りにしてくるユーミに対し、脊髄反射のように胸の前で軽く拳を握る。
「そ、そりゃ、もちろんさっ!」
「わぁ、健太くん、逞しい」
「えへへ」
「じゃあ、先に入って」
「えーっ!?」
一体ユーミはどこまでが天然で、どこまでが計画的なのか・・・。
結局、健太が先頭を歩くことになってしまった。
(怖いなぁ・・・大丈夫かなぁ・・)
健太は首筋に嫌な汗をかきながら、先頭を進む。
氷で覆われた岩肌は、なんとも不気味な感じがする。
洞窟には、多少光が差し込んでいるのか、思ったより明るかった。
先ほどから、自分の肩をちゃっかりと掴んでいるユーミに、健太はクスッと笑う。
(やっぱり、ユーミちゃんだって怖いんじゃないか・・)
ユーミは普段は強がっているが、やはり怖いものは怖いらしい。
こういうユーミの女の子らしい可愛い仕草が、健太の胸をキュンとさせるのだ。
ユーミが自分を頼ってくれると思うだけで、健太はとても幸せな気分になる。
(ユーミちゃんの手は暖かいなぁ・・・)
肩の部分だけは、ユーミの温もりを感じる。
健太は、こんな状況の中で、少し頬を赤らめていた。
「ユーミちゃん、僕から離れないようにね」
「う、うん・・」
少しだけ、健太が男らしく見えた瞬間。
──『ようこそ、いらっしゃいました』
洞窟に響く、陰湿な男の声。
道化師のような格好をした男が、ユーミと健太の前に現れた。
中途半端なところで終わってるなぁ<俺