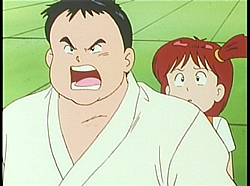 金太君です。
金太君です。
今回のテーマの1つが「陵辱」の在り方なんですが・・。
登場人物
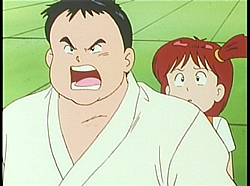 金太君です。
金太君です。
 権藤大三郎です。
権藤大三郎です。
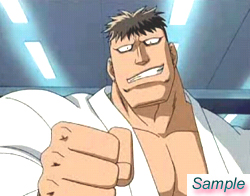
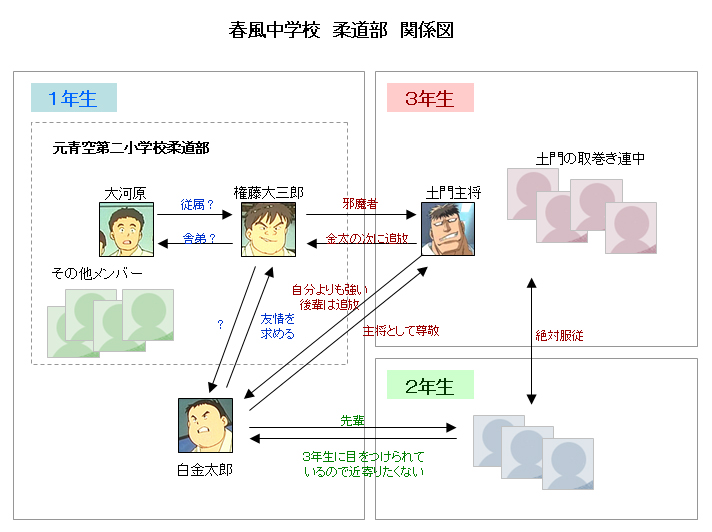 分かりやすいように、春風中学柔道部の設定をまとめてみました。
分かりやすいように、春風中学柔道部の設定をまとめてみました。
──金太が土門を吹っ飛ばした翌日。
なにやら道場の雰囲気が、騒然としている。
「うぐっ!」
3年生が、金太を壁際に取り囲んでいた。
土門は、金太の柔道着の襟を掴んで締め上げる。
鬼のような形相だ。
「おい白金! 昨日はこの俺様に、人生最大の赤っ恥かかせてくれたじゃねーか!」
「ち、違い・・ます・・」
「違うもヘチマもねぇんだよっ!」
「だって、本気でやれって・・」
「貴様、先輩に口ごたえする気か!?」
そのまま金太の襟を掴み、さらに持ち上げる土門。
金太は、柔道着を持ち上げられ、つま先でやっと立っている状態だ。
「く、苦しいっ!」
ゲホッと喉をつまらせる。
道場の異様な雰囲気に、2年生たちは土門と金太のやりとりを、見てみぬフリをしていた。
まるで昨日は何事もなかったように。
<土門主将の威厳を損わせやがって!>
<どう責任とるつもりなんだよ!>
3年生の雑言罵倒が、火の粉のように、金太に降り注ぐ。
「てめぇは、生意気なんだよ!」
土門はどさくさに紛れて、金太のみぞおちに強烈な拳をぶち込んだ。
「がはっ!」
「おい、白金。小学校で準優勝したか知らねーが、てめーはウチの柔道部の伝統をわかってねーぜ」
「げほっ、ぐぐっ・・」
「なに苦しがってんだ、この1年坊主が!」
「ううっ」
金太が3年生に絡まれている様子を見ていた大河原は、血相を変えながら権藤に話しかける。
「権藤さん! このままじゃ白金は土門主将たちに・・。なんとかしないと!」
「ヘッ。いま俺たちが動いても、話がややこしくなるたけだ」
「でも、白金は権藤さんにとって大切な・・」
「お前は黙ってろ!」
権藤は拳をギュッと握り締めながら、金太と土門のやり取りを見つめていた。
「おい、白金!」
「うぐっ・・」
「名前呼んでるんだぜ。返事くらいしたらどうだ!」
「ハ、ハイ・・」
土門は、金太の襟からゆっくりと手を放す。
金太はようやく解放され、ゲホッと咳込みながら両膝をついた。
そして、喉を押さえながら、ゆっくりと顔をあげる。
「白金、お前に春風中の柔道部の伝統を教えてやる」
「伝統・・?」
「そうだ。1年生が先輩に手を出すことは許さん。技は払いのけるか、受身をとれ。お前からは仕掛けるな」
「そんな・・それじゃ柔道にならないじゃないですか」
「伝統を守れないっていうのならば、柔道部をやめてもいいんだぜ」
「ス、スミマセン・・」
ションボリとうつむいてしまう金太。
そんな金太の従順な性格に、土門は小さく頬を上げて笑う。
「今日から、お前だけは3年生がみっちりと稽古つけてやる」
「えっ・・?」
「特別稽古ってヤツだ。今日から、お前には先輩後輩の礼儀を教えてやる。分かったか!」
「はい・・」
「俺たち5人を相手に、実践的な稽古をしてもらうぜ。これもお前を強くするための練習だからな」
「わ、分かりました・・・」
(ヘヘッ。白金は実直で真面目すぎるぜ。こういうヤツが一番扱いやすい。
しかし、白金の実力は本物だ。昇段試験を受ければ、確実に黒帯を取得できる実力がある。
こうなったら毎日、白金の体力を少しずつ奪い取って、抵抗できなくしてやる。
そして、体力の限界に達しとき、白金の体をじっくりと愛撫してやる。そのときがお前の最後さ。
こういう強くて硬派なヤツほど、愛撫されたときの反応が強烈だからな。ヘヘッ)
そういうと、土門は金太の柔道着を引っ張り、ムリヤリその場に立たせた。
土門は、フラフラと足元がおぼつかない金太の体を、背後に抱え上げる。
そのまま腰を低く落として、肩越しに畳に投げつけた。
強烈な背負い投げに、金太は円を描くように空中に飛ばされる。
「うぐっ!」
金太は左腕で畳を叩き付け、かろうじて受身をとる。
ちょっとでもタイミングが遅れれば、全身を強打して怪我をしてしまうだろう。
「い、痛ぇ・・」
「おい、何してる! 次は俺の番だぜ!」
「ちょ、ちょっと待って・・」
「ボヤボヤすんな!」
取巻き連中は、畳の上でグッタリと倒れた金太を、強引に立たせる。
「白金、てめーは先輩の好意を無駄にすんのか!」
土門は声を荒げながら、取巻きから竹刀を受け取る。
そして、ぐずぐずと起き上がる金太の肩を、竹刀で叩きつける。
「ぎゃああっ!」
肩が竹刀で軋む鈍い音。
さらに、取巻きたちは、金太に休む暇を与えずに、それぞれが得意の投げ技をしかけていく。
金太は何も抵抗できずに、投げ技をひたすら喰らい続けた。
──真っ赤な夕陽が街中に沈もうとする頃。
土門の大きな声が、道場に響き渡る。
「よーし、今日の練習は終了する。解散!」
「「「ありがとうございました!」」」
1年生と2年生は横一列に整列して、深く礼をする。
しかし、その中に金太の姿はなかった。
土門は含み笑いをしながら、ゆっくりと道場の隅に歩いていく。
そこには、投げられて傷だらけになった金太の惨めな姿。
「ハァハァ」と荒い呼吸をしながら、畳の上に倒れている。
(ヘヘッ。初日からだいぶ疲れているみたいだな。投げばかり喰らえば、体も悲鳴をあげるはずだ)
土門は上からニンマリと笑いながら、金太を覗き込む。
「おい、白金! お前は最後の整列にも並べなかったな!」
「ハァハァ・・・」
「罰として、この道場を綺麗にぞうきんがけして帰れ。分かったか」
「ハ・・ハイ・・・」
土門は、手元にある雑巾を、金太の顔にポイッと投げ捨てる。
「ハハハッ、このボロ雑巾は、いまのお前の姿そっくりだな。明日もたっぷり稽古してやるから覚悟しとけよ!」
「ううっ・・」
金太には、顔に落ちた雑巾を振り払う力さえ残っていなかった。
・
・
外はすっかりと静まり返り、暗闇が辺りを支配し始めていた。
「うっ・・くっ・・」
金太は傷ついた体で、四つん這いになって畳を雑巾で拭いていた。
時折、どうしようもなく切なくなり、涙が零れそうになる。
しかし、ギュッと目を瞑ってそれに必死で耐えた。
(俺は男だ。こんなことで泣くもんか・・!)
しかし、どんよりとした悲しさが金太の心を覆う。
この感情は、一体なんだろう?
──楽しいと期待していた柔道部に裏切られたから?
──体が痛くて、悲鳴をあげているから?
──誰も、自分に声をかけてくれないから?
金太はその理由が分からないまま、黙々と畳を雑巾がけしていく。
(こんなことでやめるもんか・・・負けてたまるか・・)
しかし、畳の色が涙が混ざって、何色だか分からない。
ガラッ・・。
静まり返った道場の扉が開く音。
そして、ノシリノシリとした乾いた足音が、金太に近づいてきた。
「だ、誰・・?」
急いで、目に溜まった涙を、柔道着の袖でぬぐう。
目を真っ赤に腫らしながら、足音のする方向に振り返った。
すると、そこには大きな1つの影。
薄暗い道場で、顔はよく見えない。
「・・・キンタ、大丈夫か?」
顔を見なくとも、その声の主は容易に想像できた。
低くて、大人びた、落ち着いた声。
いままでその声に好意を感じたことはないのに、いまは、その声が優しく心に響いてくる。
「ご、権藤・・?」
「お前と話がしたくてよ。更衣室でずっと待っていたんだが、全然こねーからさ。心配で来てやったぜ」
よく見ると、権藤は柔道着のままだ。
まさか1時間以上も着替えずに、自分のことを待っていたくれたというのか?
(俺のことを心配してくれていたのか・・・)
金太は顔を下に向け、目をギュッと瞑る。
権藤は穏やかな口調で、金太に話しかける。
「キンタ、体中が痛いんだろ? 絆創膏と湿布は持ってきたぜ。上着を脱いで背中見せてみろよ」
「で、でも・・」
「遠慮することないぜ。早くそこに座って背中をみせろ。手当てしてやるからよ」
「う、うん・・」
金太は、弱々しい声で権藤の言葉にコクンと頷く。
その場に、あぐらをかいて座る。
何の迷いもなく、自然に帯を外して柔道着を脱ぐ。
気がつくと、権藤に背中をみせていた。
「随分と、ひどくやられたもんだな・・真っ赤に腫れてるぞ」
あちこちがヒリヒリと腫れている、金太の背中。
きっと竹刀で何発か叩かれたのだろう。
権藤は金太の背中をジッと見つめながら、優しく手のひらで傷口を撫でてあげる。
権藤の大きくて温かい手。
ジンとした暖かい感触が、背中全体に広がっていく。
その手の感触に、金太はいままで抑えていた感情が一気に溢れでてしまった。
「うっ・・うっ・・」
「どうしたんだ? キンタ?」
「な、なんでもないよ・・」
「お前、泣いているのか?」
「そ、そんなこと・・ううっ・・あるもんか・・」
ポタポタと透明な雫が、金太の道着の上に滴れ落ちる。
(どうしちまったんだ・・涙がとまらねぇ・・・)
泣いている自覚はなかった。
しかし、頬に涙が勝手に零れ落ちて、それが止まることはなかったのだ。
権藤の手は、いままで孤独に耐え抜いた金太にとって、十分すぎるほど暖かかった。
肩を震わせる金太に、権藤はやんわりと言葉をつないでいく。
「キンタ、お前寂しかったんだろ? 苦しかったんだろ?」
「わからないよ・・」
「俺が痛みをとってやるぜ。お前の心の痛みをな」
「え・・?」
「さぁ、暖めてやるよ。たっぷりと時間をかけてさ」
「ご、権藤!?」
その言葉が終わらないうちに、権藤は背中から包むように金太のことを抱きしめていた。
やっと権藤×金太に持っていけたかな?