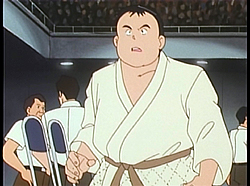 金太君です。
金太君です。
春風中柔道部はエロい子が多いなぁ・・。(←ォィ)
登場人物
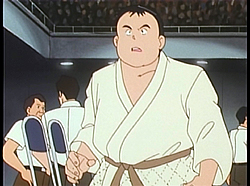 金太君です。
金太君です。
 権藤大三郎です。
権藤大三郎です。
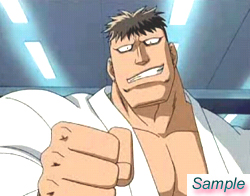
── 一週間が経とうとしていた。
「おい白金! 何やってんだ!」
「がはっ・・うぐっ・・」
道場に響く、うめき声。
一週間の間、土門たちは毎日、金太に稽古をつけていた。
いや、それは稽古ではなく、誰から見ても露骨な嫌がらせだった。
<ぐずぐずしてんじゃねぇ>
<いつまで寝てるんだよ。日が暮れちまうぞ>
<おめーのために、貴重な時間割いてやってるんだろうが!>
土門とその取巻きは、受身の練習といって、金太ひとりを道場の端に追いやる。
そして、寄ってたかって、得意の投げ技や締め技で、金太の体力を奪い続けていた。
当然、金太が反撃をすることは、許されない。
「ううっ・・こんなことで負けてたまるか・・!」
しかし、金太は罵倒されても、何度も根性で立ち上がっていた。
もう体は傷だらけで動けないはずなのに。
<チッ、なかなかバテないぜ・・!>
<すぐに嫌気が差して、退部すると思ったのによ・・>
<いや、それどころか、この特訓に慣れはじめているぞ>
土門たち3年生は、この稽古に耐え続ける金太のド根性に驚きを隠せなかった。
土門は体力の限界が見えない金太に、イラついていた。
(クソッ、白金太郎・・なんてヤツだ。普通のヤツなら、もうギブアップしているはずだ。
ましてコイツは、完全に孤立しているんだぞ。現に1年生も2年生も、全員が白金を見てみぬフリをしている。
なのに、なぜだ・・どうして、コイツの心は折れない?
一体、なにが白金をここまで動かしているんだ? 早くしないと俺の立場が危うくなってしまう・・)
この一週間、ずっと金太ひとりに対して、稽古をつけている土門に対し、
周りの1年生や2年生も、不信感を持ち始めているように思える。
土門は憤然とした様子で、畳に竹刀をグニュッと押し付けた。
そんな主将をみて、取巻きの1人が汗を掻きながら尋ねる。
「土門主将、どうしましょう? このままじゃ・・」
「いや、白金はこの一週間で確実に疲れているさ。もう俺に技を掛ける力はないはずだ」
「じゃ、いまから寝技で触診を・・?」
「それはダメだ。万が一、全員の前で寝技を跳ね返されたら、今度こそ俺の威厳は地に落ちてしまう」
「では、どうするんです?」
「いまの白金は、根性で立ち上がっている。だから、白金の心を折らなければ俺に勝ち目はない」
「でも、どうやって・・?」
取巻きの質問に対し、土門はアゴに手をあてて、しばらく考える
そして、なにかアイデアが浮かんだのか、ニタッと笑みを浮かべた。
「今日で決着をつけてやる。"アレ"をやるぜ」
その言葉を聞いて、4人の取巻きたちは薄気味悪い笑みを浮かべる。
「"アレ"をやるんですか? 俺もやりたいと思っていたんすよ!」
「バカヤロウ、やるのは俺だ。お前らには白金はもったいないぜ。
誰もいなくなった後で、居残りでやるぞ。
白金のような硬派な男に"アレ"をすれば、ショックで立ち直れなくなるはずだ。
少し過激な方法だが、一気に白金にトラウマを植えつけてやるぜ」
そういうと、土門はケケッといやらしい笑みをする。
・
・
「よし、今日の練習はここまで。解散だ!」
道場に響き渡る、土門の大声。
金太を含めた下級生たちは、横一列に整列して礼をする。
みな額の汗を拭いながら、ガヤガヤと笑顔で更衣室へと流れていく。
厳しい練習が終わった後の開放感とでもいおうか。
しかし金太だけは、誰からも声をかけられず、下を向いたまま無言で更衣室に歩を進めていた。
その姿は、明らかに疲れきっていた。
「待て。白金太郎は残れ!」
その言葉が土門から発せられた瞬間、道場全体がシーンと静まり返る。
全員の目が、一斉に金太に集中する。
金太は土門の声に、反射的にビクッと体を震わせた。
「あの・・どうして俺だけ・・?」
「いちいち理由言わなきゃいけないのか。お前は居残り稽古なんだよ!」
「で、でも・・」
「デモもヘチマもねぇ。俺たち3年生が残ってまで稽古つけてやるって言ってんだ。ありがたく思え!」
「ハイ・・」
「なんだ、その気のない返事は? 先輩を侮辱してるのか?」
「そ、そんなことありません。よろしくお願いします!」
「そうだ、それでいい」
土門は、くくっと押し殺したような笑いをする。
金太が土門たち3年生の場所へ、向かおうとしたとき・・。
誰かに肩をグイッと掴まれた。
「ご、権藤・・?」
「キンタ、居残ってまで稽古するのはやめたほうがいい。断るんだ」
大きくて暖かい、権藤の手。
いつになく真剣な顔。
「おい、キンタ。聞いているのか!?」
「やめたほうがいいって・・・どうしてだよ・・?」
「なんとなく分かるんだ。アイツら、絶対になにか企んでるぜ」
「企むって・・?」
「とにかくやめるんだ」
「土門主将は、お前みたいに、リョウジョクするわけじゃないんだ!」
「なにっ!?」
「お前には関係ないだろ! 柔道の稽古なんだ。邪魔するな!」
そういうと、金太は権藤の真剣な目から、視線を逸らした。
そして、その腕を大きく振り払う。
「ホラ、全員さっさと出て行かないか!」
取巻き連中は、グズグズしている下級生を道場から締め出す。
土門は取巻きの連中に、目で合図を送る。
すると、1人は道場から外に出て行った。
さらに、別の男は、木製の扉をスライドさせて、隙間なく締めた。
(ヘヘッ、1人は外で誰も道場に近づけぬように監視役だ。
扉は完全にシャットアウト。これで白金をどうしようと、誰もみているヤツはいねぇ・・)
ゆっくりと道場の中央に歩を進める金太。
疲れがピークに達しているのか、足元がおぼつかない様子だ。
そんな金太を見て、土門は竹刀を畳に叩きつけて怒鳴った。
「白金、なにゆっくり歩いてるんだ!」
「ス、スミマセン・・」
「たるんでんじゃねーぞ、コラッ!」
「ハ、ハイ!」
金太は土門の逆鱗に触れぬよう、額に汗をかきながら道場の中央に進む。
そして、背筋をピンと伸ばして、直立した。
そんな従順な金太を見て、土門はほくそ笑む。
(ヘッ。穢れを知らない可愛い1年坊じゃねーか。これからお前をたっぷり愛撫してやる。
いままで味わったことがない快感と恥辱にまみれるがいいさ。
そして、トラウマにさぞ打ちひしがれるがいい。今日で、柔道が嫌になっちまうかもな。
ククッ、柔道部に、俺よりも強い男は必要ないんだからな!)
金太は何の疑いも持たず、道場の中央で稽古を待っていた。
土門は竹刀を肩を置きながら、金太の前に進む。
「では、居残り稽古を始めようか」
「ハイ」
「ところでお前、よくみると1年生のくせに、いい体してるじゃねーか」
「えっ・・?」
「お前の体が柔道に向いているかどうか、俺様が見てやるぜ。ちょっと柔道着脱げや」
「ど、どうして・・!」
土門の脈絡のない話に、金太の表情が固まる。
「どうしたんだ、白金? まさか、主将の言うことが聞けないっていうのか?」
「そんなことありません・・だけど・・」
「脱げっていってるのが、聴こえないのか!!!」
「ハ、ハイ!」
まるで雷が落ちたような土門の怒声に、金太は圧倒された。
そして、キョロキョロと周りをみながら、柔道着に手をかける。
そのまま、上半身の道着をバッと脱ぎ捨てた。
金太の引き締まった上半身。
筋肉と脂肪がほどよくつき、綺麗な曲線を描いている。
その引き締まった体に、その場にいる取巻きたちは思わず呟いた。
<すげーいい体してるじゃん>
<1年生のくせに、胸板は俺たちよりも厚いかもな>
<胸板ってより、おっぱいみたいじゃね?>
周りを取り囲んでいる取巻きたちは、金太の体をみて感嘆やら、からかいの声をあげる。
取巻きたちの視線に、金太はギュッと目を瞑って震えだした。
そんな金太のウブな姿をみて、土門はクッと笑いを堪える。
(ヘヘッ。白金のヤツ、連中の視線と言葉に、恥辱を感じてるな。
それにしても、引き締まったいい胸の膨らみしてるぜ。じっくり揉んで、舐めてやりたいぜ。
こんな硬派な男が、どう反応するのかも興味あるしな。さぞショックを受けるだろうよ)
土門は金太に、鋭い視線を向け、再び怒声をふるう。
「おい、白金! なにボケッとしてんだよ」
「えっ・・?」
「下だよ。下も脱げ」
「ええっ? 下もですか?」
思わず声が、裏返ってしまった。
「柔道着脱げってさっきから言ってるだろ。上だけ脱いでどうすんだよ、日本語わかんねーのか」
「で、でも・・」
「早くしろ!」
「ハイ・・」
土門の勢いに押され、金太はグッと屈辱に耐えながら、道着の下に手をゆっくりとかけた。
先輩たちの前でパンツ一丁になるという恥辱。
道着を脱ぐと、白いパンツがそっと顔を覗かせる。
新品を卸したばかりなのか、まだシミひとつ無い綺麗なブリーフ。
はち切れんばかりに、肢体にぴったりと張りついている。
真ん中にポツッとした膨らみ。
(へぇ。白金は、柔道着の下に清純な白パンツ履いてるのか。てっきりスッポンポンかと思ったのによ)
土門の口元が緩む。
パンツ一枚にされてしまった金太は、
モジモジと落ち着かない様子で、両手はパンツの膨らみを隠していた。
先輩たちのジロジロと嘗め回すような視線。
<かなりケツがでかいな>
<体の割りには、アソコは小さいんじゃねーの?>
<毛は生えてんのか?>
わざと聴こえるように言っているのだろうか?
パンツの中身を詮索するような会話に、金太は下に向いて真っ赤になる。
そんな純情な金太に対し、土門とその取巻きたちはゆっくりと金太に近づいてきた。
前後左右を4人の先輩に囲まれてしまった、パンツ一枚の金太。
「ヘヘッ。いい眺めだぜ」
「うううっ・・」
「白金は、純白のブリーフ履いているのか。まだお母さんに買ってもらってるのか?」
「・・・・」
「なかなか似合ってるぜ。パンツのはち切れ具合もいい感じだしな」
「くっ・・」
羞恥心で一杯になる金太。
自分のパンツ姿を四方八方から眺められるという屈辱。
猫背気味になり、必死に股間を隠すのが、精一杯だ。
そんな金太の姿に、ニタッと笑みを浮かべる土門。
(コイツ、裸になるといい体躯してるぜ。いままで最高かもな。
さすがは白金太郎ってことか。ヘヘッ、ますます触りたくなってきたぜ。
さてと、まずは乳首を触ってやろうか。白金くんはこの衝撃にどう反応するかな? 楽しみだぜ!)
土門は、綺麗な逆三角形をした金太の胸の膨らみに、スッと手を伸ばす。
そのまま、金太のピンク色をした乳首を、力一杯ギュッと摘んでみる。
「ぎゃあっ!」
悲鳴に近い声を、なんとか飲み込んだ金太。
(なんだ白金のヤツ、もしかして、いま刺激に反応したのか・・?)
土門はそのまま、指で乳首を小刻みに動かしたり、反対方向に捻ったりする。
いきなりの土門の触診攻撃に、金太の体はブルブルと震えて凍りつく。
「や、やめろ!」
条件反射のように、土門の手を握り、力ずくで乳首から離した。
「おい白金、痛えーぞ。お前なにやってんだ?」
「だ、だって・・どうして胸を触るんですか!?」
「触っちゃいけないのか?」
「だって・・その・・こんなところ・・」
「はぁ? 白金、なに勘違いしてるんだ?」
「えっ?」
土門は金太に手首を握られながらも、いつもと変わらない口調で語りかける。
「俺はなぁ、白金のためにやってるんだぜ」
「ど、どういう意味ですか・・?」
「お前の精神力を試しているんだ」
「精神力・・?」
「そうさ。中学の柔道の試合ともなれば、胸や乳首ぐらい触られることなんて当たり前なんだよ。
お前はまだ経験がないだろう? いきなり試合で触られたら、気が動転しちまうと思ってな。
すべてはお前のためだ。俺がわざわざ稽古してやってるのに、その生意気な態度はなんだ?」
「・・・」
「それが主将に対する、お前の態度なのか?」
「ス、スミマセン・・・」
「分かったら、その手を離せ」
「ハイ・・・」
金太はションボリと下を向いて、土門の手首を離した。
「お前はまだ慣れていないようだからな。特別に鍛えてやるぜ。ちょっと拘束するか」
「こ、拘束って・・」
そういうと、土門は目で、左右にいる取巻きたちに合図を送る。
すると、取巻きの1人が、金太の後ろに回り込む。
そして、後ろから金太の脇の下に腕を廻し、しっかりと羽交い絞めにした。
後ろから、腕を羽交い絞めされて、身動きができなくなった金太。
さらに2人の取巻きは、金太の逞しい太ももをしっかりと握り締める。
(そ、そんな・・・!)
手も足も出せない格好にされてしまった金太。
しかし、この状態を拒絶することはできない。
正面にいる土門には、上半身を含め、パンツの膨らみまで丸見えだ。
金太の肉体のほとんどが、土門に晒されたと言っても過言ではない。
「ホラ、土門主将に、ちゃんとパンツをみせてやれよ!」
「こ、ここまでしなくても・・・」
ぐずぐずとしている金太に、土門が話しかける。
「まったく、白金はいちいちうるせーな。なにをビクついてるんだ!」
「ス、スミマセン・・」
「へぇ。こうしてみると、お前、本当にいい体してるな。穢すのがもったいないぜ」
「け、穢すって・・?」
「何でもねーよ。先輩として、お前の体をきちんと確認してやるからよ」
金太は「くっ」と諦めに近い声を漏らす。
真っ赤になって、下を向いて恥辱に耐える。
土門は再び、金太の乳首をギュッと摘む。
「うぐっ・・!」
「へぇ、意外とコリコリして、でかいんだな。お前の乳首はよ」
そう言いながら、土門は金太の乳首の先端を、親指と人差し指で思いっきり摘んでみる。
ビビッと電気が走るような感触。
「あぐぐぐっ、そ、そこまで触らなくても・・」
「胸の筋肉のつき具合を見ているんだ。それに精神力も鍛えられるぜ」
「で、でも、そこは・・・」
「クククッ、まさかお前・・・触られて感じてるんじゃないだろうな?」
「そんなことあるわけ・・」
「だよなぁ。まさか男が男に触られて、感じるなんてことないよな」
そういうと、土門はもう片方の手で、乳房をガシッとわし掴みにする。
そして、いやらしい手つきで、上下に揉みしだき始めた。
「はんぁっ!ぐぐっ!」
「へぇ。なかなか揉みやすい乳房してるじゃねーか。1年生でここまで揉み応えがあるヤツは珍しいぜ」
「はぐっ・・そんな・・!」
胸の快感に、反射的に喘ぎ声を出してしまう金太。
(ヘヘッ、さぞ恥辱に打ちひしがれるがいいさ。これからが本番だぜ)
無抵抗な金太に対し、圧倒的優位に立った土門は、悪魔の笑みを浮かべていた。
「居残り稽古」は、某同人誌に影響受けまくってます。