 我らが金太君です。
我らが金太君です。
今回の小説、なんか無意味に長いかな?
登場人物
 我らが金太君です。
我らが金太君です。
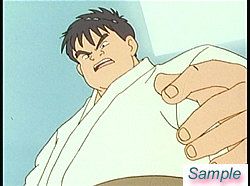 権藤大三郎です。
権藤大三郎です。
 大河原。権藤の舎弟らしく、以前金太を陵辱したこともある。
大河原。権藤の舎弟らしく、以前金太を陵辱したこともある。
──夕陽が小窓から降り注ぐ中。
誰もいなくなった道場。
緑の畳が、橙色に染まっている。
その中央で、金太は1人ポツンと膝を抱えて座っていた。
つい先ほどまで、この場所で自分が陵辱されていたとは思えないほど、静まり返っている。
(どうして、こんなことになるんだよ・・・)
金太の気持ちは複雑だった。
(俺はただ、柔道したいだけなのに・・。
土門主将も権藤も、みんな柔道が好きなはずたろ・・。
どうして、土門主将は俺をリョウジョクしてきたんだ?
どうして、権藤が責任取らされて柔道部をやめなくちゃいけないんだ?
俺には柔道がなんなのか分からなくなってきた・・。全てがおかしいじゃないか!)
金太は心の中で、自問自答を繰り返す。
どうしようもなく虚しくなり、畳を爪でガッと掻きむしる。
「白金太郎! なにボケッとしてるんだ!」
聞き覚えのある声だったが、いまは誰とも話したくなかった。
視線を下に向けて、貝のように口を閉ざした。
「てめぇ、ふざけんじゃねーぞ!」
「えっ?」
いきなり襟を掴まれて、強引に立たせられた。
「お、お前は・・大河原!?」
「白金! お前のせいで・・お前のせいで、権藤さんは柔道部を・・」
「す、すまない・・」
「謝って済む問題じゃねーだろ!」
「・・・・」
金太は、なにも反論できなかった。
もし権藤の忠告を素直に聞いていれば、こんなことにはならなかったのだから。
大河原に殴られても仕方ないことだと、金太は歯を食いしばった。
──大河原。
結花が人質にされたとき、権藤と一緒に俺をリョウジョクした許せないヤツ。
でも、いまはもう大河原には、なんの恨みもなかった。
コイツはただ権藤に従っているだけなのか?
それとも権藤を尊敬しているのか?
いままで、そんなことは考えたこともなかったが、
大河原の取り乱した様子を見る限り、大河原にとって権藤は単なる絶対者ではないようだ。
まさか、コイツは権藤の友達なのだろうか?
もしそうなら、権藤とどんな会話をしているんだ?
襟をつかまれた一瞬の間に、金太はそんなことを想像した。
大河原はゆっくりと金太の襟首を放すと、そのまま金太のことをジッと見つめる。
そして、先ほどまでとは違い、真面目な感じの声で話してきた。
「白金、お前ここで何を考えていた?」
「権藤のことを考えてた・・」
「お前は、権藤さんのことをどう思ってるんだ?」
金太はその質問に即答できなかったが、少し時間をおいて、言葉を詰まらせながら返事をする。
「俺はアイツと友達になりたいだけなんだ・・。でも、俺にはアイツのことがさっぱりわからない。
アイツは俺に言ったんだ。『お前だけを愛してやる』ってさ。どういう意味なんだ・・。
俺たちは男同士なんだぞ。そんなことあるのかよ・・」
気がつくと、金太は大河原に必死に気持ちを伝えていた。
いままで、権藤のことを他人に相談しようとは思ったことは、一度もないのに・・。
大河原は、金太の言葉にフッと息をついた。
「そうか、お前にはその意味が分からないかもな。俺だって理解できる自信はない。
権藤さんには止められていたが、お前には権藤さんのことを知る権利がある。いや、知らなくてはいけないんだ。
なぜなら、権藤さんがあんな風に変わってしまったのは、お前に原因があるんだからな!」
「お、俺に・・どうして!?」
「別にすべての責任があるわけじゃない。でも、最初の原因はお前かもしれないんだ」
その言葉を聞いて、金太は額に薄っすらと汗が流れる。
「ど、どういう意味なんだ・・」
「権藤さんの何が知りたい? 俺が分かることはなんでも話してやる。ただ、俺から聞いたって権藤さんには言うなよ」
そういうと、大河原は真剣な眼差しで、金太のことを見つめた。
その目を見て、金太は彼を信用できる人間であると感じた。
金太は真剣な顔つきで、大河原に尋ねる。
「さっき、『権藤があんな風に変わった』って言ったよな? それはどういう意味なんだ?」
すると、大河原はゆっくりと返事をしてきた。
「4年前の5月5日に、権藤さんと春風小学校で対戦したときのことを覚えているか?」
「あ、あぁ。もちろん覚えてるさ。俺が初めて出場した大会で、決勝で権藤に負けたんだ」
「権藤さんはあのときから、お前のことを気にかけていたんだ」
「気にかける・・? 柔道のライバルとしてか?」
「それもある。だけど、もっと別の意味だ」
「どういうことだよ・・」
「お前、好きな子いるだろ?たしか結花とかいう、可愛い女の子」
「あぁ」
「その子のことを思うと、胸がキュンと痛くなったりしないか?」
その言葉に金太の顔はポッと赤くなる。
急に腕を組んでプイッと斜め上を見上げる。
「べ、別に、そんなことないよ・・」
「お前、いま結花って子のこと思い出して、赤くなっただろう?」
「ちょ、ちょっとな」
「簡単にいえば、それと同じ感情さ。権藤さんはお前に対してそういう感情をもっているんだ」
大河原の言葉を聞いて、金太は大きく目を見開いた。
「いま、なんて言ったんだ・・?」
「権藤さんは、お前のことが好きなんだよ。文字通り"好き"なんだ」
「なっ・・!」
大河原から聞いた衝撃的な発言に、金太は口から心臓が飛び出るほど驚いた。
「ちょっと待て! 俺たちは男同士なんだぞ。好きとかそういう問題じゃ・・・」
「俺にだって、完全には理解できないさ。だけど、本当にそうなんだから、しかたないだろ」
「まさか、『愛してやる』って・・・」
「その通りの意味さ。言葉はちょっと変かもしれないけど、権藤さんはお前のことを愛しているんだ。
お前と一緒にいられるならば、たとえ柔道をやめてもいいと思うくらい好きなんだ」
「そ、そんなバカなことが・・・」
「だから、ムリに理解しようとするなよ。
俺だって、最近になってようやく権藤さんの言っていることを少しだけ理解できたんだ。
いくら考えたって、理解できない者には理解できない話だ」
「・・・」
「たぶん、理屈じゃないんだ。人が人を好きになることなんて、理屈じゃ説明できないだろ?」
「だ、だけど・・」
金太はフゥーッと大きく息を吸って、吐き出した。
そうでもしないと、大河原の言っていることを受け入れることができなかったからだ。
混乱状態から少し落ち着いた金太は、さらに尋ねた。
「4年前に対戦したときから、そうだったというのか?」
「俺にはわからないけど、たぶん始まりはあの大会の決勝戦だったんだ。
権藤さんはそれ以来、お前と対戦するのを毎年楽しみにしていたんだと思う。
もっとも、権藤さん自身にも、"男を好きだ"という明確な意識はなかったかもしれないけどな。
あのころは、今みたいにひねくれてなくてさ。純粋にお前のことを影から見ていたんだ。
決勝まで勝ち残れば、必ずどこかでお前と対戦できるだろう? だから権藤さんは毎日必死に練習してた。
それは俺が見ても異常だと思うほど、柔道の練習をしていたよ。
その練習はすべて、白金・・お前と対戦するため、いや、お前と柔道で体を合わせたかったからなんだ」
「なんだって・・!」
「権藤さんが柔道が強いのは、柔道が好きだからじゃない。
お前と対戦したいという心が、権藤さんをあそこまで強くさせたんだ」
「・・・」
「でも、それを不純な動機といって、軽蔑しないでほしいんだ。
権藤さんには元々、柔道の才能があったんだ。生まれついての肉体の強さとセンスさ。
つまりお前という存在が、皮肉なことに権藤大三郎という柔道の天才を生んでしまったんだ」
「天才って・・・」
「だって小学3年生から、4年も連続して優勝するバケモノは10年に1人いるかいないかだろう?」
「そ、そりゃそうだけど・・」
金太はゴクリと唾を飲み込んで、心を落ち着けた。
たしかに権藤は以前に『柔道なんか好きじゃない』と言っていたが、まさかそれが本当のことだったなんて・・。
しかし、金太には別の疑問もあった。
「もう1つ教えてくれ。もし、権藤が俺のことを・・その・・"好き"だとしたら、
どうして俺に暴力を振るったんだ? どうしてリョウジョクみたいな卑劣なことをしてきたんだ?」
その質問に、大河原は視線を下に落として、話しづらそうな顔をする。
「権藤さんは、昨年の柔道大会のあと、変わってしまったんだ」
「変わった? 俺が途中棄権したからか?」
「原因はお前じゃない。家庭の事情なんだ・・両親が離婚したのさ」
「り、離婚?」
「権藤さんの家は元々金持ちだっんだ。青空第二小学校に専用の道場があっただろう?
あれは権藤さんの父親が、柔道に夢中だった息子のために寄付したものさ。
でも、離婚したあと、権藤さんは母親に引き取られて、生活が大変になったみたいでさ。
しかも母親は、他に男を作って権藤さんに見向きもしなくなったんだ。
だから、それまで優しかった権藤さんは、いつのまにか荒れて、部活で暴力を振るうようになった。
そして、俺たちをリョウジョクで従わせるようになっていったんだ」
「従わせるって・・」
「俺たちも悪かったんだ。最初は、暴力を振るう権藤さんをみんなで無視して、仲間はずれにした。
でも、権藤さんにリョウジョクされたら癖になってしまって、みんなが権藤さんを求めてしまったんだ。
それに味をしめた権藤さんは、1つの単純な結論を導き出した。
長年思いを馳せていた白金太郎を、自分のものにする方法を・・。それがリョウジョクだったんだ」
「そ、そんな・・」
大河原の話に、金太は半ば放心状態になっていた
いままでの権藤の陵辱や言動が、嫌がらせやイタズラではなく、すべて自分を求める行為だったなんて・・。
ウツロな目をした金太に、大河原は言葉をつなげていく。
「俺と権藤さんは、以前は友達として仲良く接してきたんだ。
でも、いまは舎弟みたいな存在になっちゃってさ。もう元の関係に戻れないんだ。
権藤さんはいま、何も見えなくなってる。暴力やリョウジョクで他人を従わせようとしている。友達を作ろうとしている。
それが一番簡単な方法だから・・。自分が常に上に立って、相手をコントロールできるから。
でも、そんなことで友達や恋人ができるなんて幻想だ。それは白金、お前にも分かっていることだろう?
権藤さんは中学生になっても、それをやめようとしない。俺はどうしたらいいのか分からない・・」
「・・・」
「権藤さんは、ずっと昔に、俺に話したことがあるよ。
"いつか白金太郎は、自分の手の届かない柔道家になるんだろうな"って。
"そのときは、俺は柔道をやめて、白金太郎に本当の気持ちを伝えられたらいな"って。
"もし、白金太郎が俺を受け入れてくれなくとも、影から見守る存在になれたらいいいな"って。
権藤さんとお前は、柔道に対する考え方が根本的に違うんだ。
権藤さんにとっての柔道とは、お前との唯一の接点にすぎないのさ。
だから、権藤さんがお前を求めることを諦めたとき、たぶん柔道もやめるんだろうな」
その言葉に対して、金太は少しの間、目を瞑ってギュッと拳を握り締めた。
そして、ゆっくりと口を開く。
「そんなことないよ・・」
「えっ?」
「俺はそんなの絶対に認めない。権藤は柔道が好きなはずだ。
だって、アイツは柔道部を退部するように告げられたとき、とても悲しい顔をしていたんだ。
俺の言葉さえ、受け付けなかったんだ。俺はいまからアイツの本当の心を確かめてくる!
アイツと同じ目線に立って、アイツの心を理解するように努力するよ。大河原、いろいろとありがとうな!」
そういうと、金太は道場を勢いよく飛び出して行った。
そんな金太の姿を見て、それまで強張っていた大河原の表情が、少しだけ和らいだ。
(頼むぜ、白金。いまの権藤さんを変えられるのはお前しかいないんだ・・。悔しいけど、俺じゃムリだ・・)