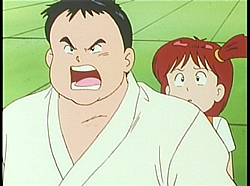 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校1年生の柔道部員。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校1年生の柔道部員。
この小説は金太君小説(第4部)の続きとなります。読んでいない方は第4部を先にお読みください。第4部で内容的には完結しているのですが、今回は番外編みたいなものということで(^^;
登場人物
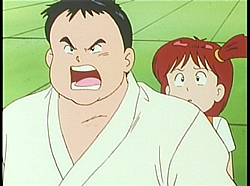 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校1年生の柔道部員。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校1年生の柔道部員。
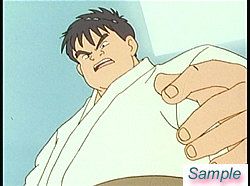 権藤大三郎。金太のライバル。以前は春風中にいたが、現在は東京に引っ越しており、明法大付属中の1年生で柔道部に所属。
権藤大三郎。金太のライバル。以前は春風中にいたが、現在は東京に引っ越しており、明法大付属中の1年生で柔道部に所属。
ボケッと夜空を眺めながら、考えている。
男同士の恋愛の先に、なにがあるのかを。
そして、俺は心配している。
アイツの将来のことを。
・・・
俺はアイツを愛していない。
でも、アイツを助けるために、仕方なかった。
唇と唇を合わせて、体と体を合わせた。
アイツはどんな気持ちだったんだろう?
そんなことをしたら、余計にアイツを苦しめることになると分かっていたのに。
・・・
どうすれば、元に戻る?
どうしたら、夢中になった日に戻れる?
時間は過去には遡れないんだぞ。
・・・
俺はアイツをこれ以上傷つけたくない。
だから、アイツが求める答えを見つけなくちゃいけない。
アイツとどう接するかを考えなくちゃいけない。
必ず答えはあるはずなんだ。
だって、俺が求める答えを出したヤツが、いたんだから。
・・・・
・・・
・・
「わぁ」という柔道大会の歓声が聴こえる一室。
薄暗くて狭い倉庫の中。
「キンタ・・・」
「権藤、やめるんだ」
「このときを、ずっと待っていた・・」
金太は冷たい床に仰向きに倒され、天を見上げる。
お腹の上には権藤大三郎がまたがっていた。
金太が下で、権藤が上。
いつもの体勢。
権藤は金太の両手首を、床に食い込むように、しっかりと押さえつける。
「キンタ、会いたかったぜ。ずっと会いたかった」
「バカヤロッ。倉庫に入って、いきなりこの体勢はないだろ・・」
「ス、スマン・・・」
誰もいない倉庫に、2人だけの声が僅かに響いていた。
まだ汗がほんのりと染みた柔道着。
しばらく2人は、数十センチの距離で、顔と顔を見つめ合った。
久しぶりにみる権藤の顔は、以前よりも逞しく、精悍に映る。
「キンタ、もう我慢できねぇ」
「待ってくれ。少し話がしたいんだ。だって半年振りに会ったのに・・・」
「そ、そうだよな・・・」
照れくさそうな権藤の顔。
金太は真下から権藤の瞳を見つめ、そしておもむろに口を開いた。
「さっきの試合のことだけどさ・・。
俺の完敗だったよ。俺は何もできなかった。
俺の足技も、得意の背負い投げも、何一つお前には通用しなかったよ。
権藤、お前は本気で柔道に取り組んだんだな?」
権藤も金太の瞳を見つめながら、返事をしてきた。
「あぁ。キンタと別れたあの日から、俺は真剣に柔道に取り組んだ。
それがお前と約束したことだったから。お前が愛する柔道を、俺も命がけで打ち込んだんだ」
権藤の言葉に、金太は満足するようにうなづいた。
「そっか・・。
悔しいけどお前はすごいよ。たった半年でこんなに強くなるのか・・」
「そんなことはない。いまの試合はどちらが勝ってもおかしくなかった」
「でも、お前はいつも俺の上を行く。もう俺の手の届かないところに行っちまったんじゃないのか」
「そんなことあるか。俺の柔道のライバルは、永遠にキンタだけだ」
「権藤・・」
権藤の真剣な返事に対し、金太はうれしかったのか、少し鼻の上を赤くして照れていた。
金太と権藤が再会したのは、権藤が東京の中学校に転校してから半年後の全国大会だった。
団体の一回戦で、金太のいる春風中と、権藤のいる明法大付属中が対戦することになったのだ。
金太と権藤は1年生同士、先鋒で対戦したが、権藤大三郎の強さは圧倒的だった。
金太は、権藤と対戦して肌で感じた。
権藤の体は一回り、いや二回りは大きくなっていた。
そして、柔道の技術も以前とは比べ物にならないくらい、進歩していた。
金太はうれしかったが、その反面、権藤大三郎の圧倒的な強さに、寒気さえ感じた。
権藤が、やんわりと口を開く。
「なぁ、キンタ?」
「な、なんだよ・・?」
「良かったら、黙って俺の話を聞いてくれないか?」
「あぁ」
「キンタ、ありがとう。
俺はあの日、お前に「好きだ」と告白をして別れた後、しばらく何も手につかなかった。
お前と体を合わせて、お前が俺に甘えてくれて・・・そのときの記憶が脳にこびりついたままだった。
思い出すだけで、他に何もできなかったんだ。
もう二度と会えないんじゃないかと考えただけで、気持ちが落ち込んだよ。
でも、それじゃダメだと気がついたんだ。
だから、俺はずっと柔道に打ち込んだ。
柔道をしているときは、なぜか気持ちが落ち着いたんだ。
たぶん、柔道をしていれば、いつかまたキンタに会えると思って、安心できたんだと思う」
権藤は言葉を喉につかえながら、必死に話しかけていた。
そんな権藤の表情や仕草を見ながら、金太は真剣に話に聞き入っていた。
「俺は、いまでもキンタのことが好きだ。大好きなんだ。
ずっとお前のことを考えている。
こんなことを言っても、お前を困らせることは分かっているんだ。
でも、我慢できない。
全国大会の会場でお前を見つけたときから、ずっと胸が張り裂けそうなんだよ。
もう一度、お前をを抱きたい。お前と体を合わせたい。
だからお前との試合が終わってすぐに声をかけて、この倉庫に連れ込んじまった。
まだ次の試合があるってのにさ・・。
俺は、お前のことを押し倒して、自分の欲求を満たそうとしている。俺は昔とちっとも変わってない。
本当に済まないと思っている・・最低だろ・・。欲求を抑えられない自分が、恥ずかしいんだ・・」
そういうと、権藤は少しだけ横に視線をそらした。
権藤が素直な気持ちを伝えてきたことに対し、金太はなぜか心臓が高鳴った。
どうして心臓の鼓動が速くなるのか、金太自身にも理解できなかった。
権藤はさらに言葉をつなげる。
「キンタ・・お前は言ったよな。
"男が男を愛するなんて理解できない"って。いまもそうか?」
「あぁ、そうだ」
「・・・。もしよかったら、1つだけ俺の願いを聞いてくれ。たった1つだけでいい」
「願い?」
「キスを・・キスをさせて欲しい」
「・・・」
「頼む。お前の唇の感触を、もう一度だけ確かめたいんだ」
必死に気持ちを伝えようとする権藤に、金太は自然に言葉が出ていた。
「分かったよ・・キスだけなら・・」
「ありがとう、キンタ。うれしい・・」
権藤は、金太のふっくらとした頬に両手を当てる。
そして、まるで子供の肌を触るかのように、頬を優しく撫でた。
そのまま頬を両手で抱いたまま、権藤は唇をゆっくりと近づける。
目を閉じて、そして金太の唇に自分の唇を重ねた。
(はうっ・・)
(ううっ・・)
権藤は、ただ軽く唇をかぶせただけだった。
いままでの権藤ならば、強引に唇をこじあけて、愛撫してきたに違いない。
しかし、今日は違った。
(な、なんだ・・この唇の震えは?)
権藤の唇。
ブルブルと震えていて、緊張感が伝わってくる。
(どうしたんだ、権藤・・お前はどうしてこんなに震えているんだ・・?
これが、いまのお前の気持ち・・権藤大三郎の本当の気持ちなのか・・? )
権藤の震えを感じた金太も、なぜかドキドキと心臓の鼓動が速くなった。
しばらく唇と唇を重ねる。
お互いの唇の感触を確かめあったあと、権藤はゆっくりと顔を起こした。
そして、少し涙ぐんだ声で話しかけてきた。
「キンタ、ありがとう。
やっぱりお前は優しいんだな。だから俺はお前のことが好きだ。
もっともっと体を合わせたい。
でも、それがわがままなことは分かっているんだ」
「・・・」
「俺のことが嫌いならば、このまま俺を突き飛ばして、出て行ってくれ。
もう俺は、お前のあとは追わない。でも、もし俺の気持ちを理解してくれるのなら・・。
このまま・・俺と一緒に・・キンタ・・」
権藤の真剣な眼差し。
金太はその真剣な瞳を見つめているうちに、あの日の気持ちを思い出した。
半年前、権藤の家で体を合わせて、気持ちが1つになった瞬間のことを。
「権藤・・俺は・・」
「キンタ?」
「俺はどうしたらいいのか分からない。だって、俺はお前のことが嫌いじゃないんだ。
それにお前を見つめていると、なぜか心臓がドキドキするよ。
だから、お前を突き飛ばすこともできない・・。
自分でも分からないんだ。俺は、もしかしたらお前のことが・・・」
そういうと、金太はギュッと目を瞑り、黙って体を権藤に委ねた。
これから起きるであろうことを想像して、ほんの少し震えながら・・。
「ありがとう・・キンタ。すごいうれしい・・」
再び、唇に暖かい感触が走る。
権藤の湿った舌と唾液が、金太の唇をたっぷりと舐めつくす。
(あんっ・・)
(はんむ・・)
やがて、その舌は唇をこじあけて、柔らかい舌と舌が絡み合う。
舌が絡み合った瞬間、金太の脳裏にあの日の快感が蘇った。
打ち震えるような快感・・。
権藤の暖かい舌と、溶けるような唾液。
身震いするような、気持ちよさ。
その感触を欲して、何度も何度も確かめ合った。
(はんっ・・権藤・・)
(キンタ・・!)
金太は「いけない」と心のどこかで思いながらも、求めてしまっていた。
(もっと・・)
権藤の舌が金太の舌を追い求める。
2人は唇を重ねあい、舌を何度もお互いに絡ませて、心を通わせ合った。
やがて、権藤の舌は唇から離れる。
金太の口からも、権藤の口からも、唾液の糸がツーッと滴り落ちた。
さらに、権藤の唇は、金太の首筋を通り越し、胸の膨らみに移動していく。
(ああっ・・!)
さらに権藤の手のひらが、金太の乳房に伸びて、ゆっくりと鷲づかみにする。
乳房を上下に揉みしだき、時に円を描くようになぞっていく。
そして、同時に舌で乳首を濡らしていく。
「くっ・・んあっ・・大三郎・・」
「キンタ、いまなんて言った?」
「大三郎、もっと舐めて」
「俺のことを"大三郎"って呼んでくれるのか?」
「うん、早く・・」
「俺のことを受け入れてくれるんだな?」
「・・・・」
「ど、どうして答えてくれないんだ・・」
「早く・・!」
「わ、分かった・・」
権藤は金太の柔道着をめくり、逞しい胸板を眼前に晒させた。
そして下の道着も、すべて脱がした。
金太の肢体は、ほどよい脂と筋肉が交じり合っている。
以前よりも、肉付きが立派になった金太の裸。
権藤の目は血走り、自分も柔道着を放り投げた。
そして、裸で金太の上に覆いかぶさる。
(ああっ!)
ゾクッとするような肌の密着感。
お互いの肌と肌が生で激しく絡み合う。
権藤は鼻から荒い息を吐き出し、金太の胸を揉みくしゃにして、触りまくった。
「たまんねぇ・・」
「あっ、そんな、うひゃあっ・・」
「俺が半年間、ずっと求めていたもの・・キンタの体・・」
権藤は舌を立てて、金太の首筋をベロンッと舐める。
「ああっ!」
そのまま首筋をペチャと音がするくらい愛撫する。
そして、舌を乳房までを一筆書きをするように舐めていく。
「んっ、くっ、ふあっ!」
「俺が舐めただけでこんなに快感に打ち震えるなんて・・。
やっぱりお前は感度がいい。俺が思ったとおりに反応してくれる。
俺はお前とずっと一緒にいたい。お前と体を合わせていたい」
「はっ、あっ、俺は・・」
金太がなにか言おうとしたとき、ペチャッという唾液の音が乳房に流れる。
「あわ・・」
自然に金太の体は自然に悶えていた。
「これが、いまのキンタの体・・あのときよりも大きくなって・・。
すべてを舐めたい・・すべてを俺のものにしたい・・」
「んあっ」
「お前のおっぱいの感触、たまんねぇ・・すげぇ・・」
「大三郎、そこは・・ひぃっ!」
権藤は、金太の乳房からお腹を、丁寧に舐め尽くしていく。
ひと舐めするたびに、金太は体をくねらせ、全身を震えさせた。
「舐めるぜ。お前の一番大切なところ」
「う、うん・・」
いつのまにか、権藤の舌は、金太の最も大切な部分に達していた。
下半身に感じる権藤の荒い息遣い。
鼻息が金太のおちんちんに届くたびに、モノは突き上げるように勃起していった。
権藤は金太の亀頭をスルスルと剥き、そこに容赦なくしゃぶりつく。
「ふあっ、あひゃ!」
「お前が一番感じる部分だぜ。俺のために大切にしていてくれたか?」
「大切もなにも・・ひゃあっ!」
キャンディーをしゃぶるように、亀頭を愛撫する権藤。
舌でねぶるたびに、金太は身悶えし、熱い息を吐いた。
「そこ、大三郎、すご・・」
「俺をこんなに求めてくれるなんて・・」
「そこは、感じちまう・・」
「うれしいぜ・・だってお前が俺の舌で快感に震えて、そして甘えてくれているんだから」
「だって、大三郎の舌が気持ちよくて、ああっ!」
「じゃ、もっと感じる場所にいくぜ」
権藤は金太の両足を持ち、少し持ち上げてVの字に大股開きにする。
そして、Vの字に開かれた足の中に、ゴソゴソと入り込む。
「キンタ、そのまま足を持ち上げてろよ。ケツの穴が見やすいからな」
右手で金太のおちんちんの付け根をしっかりと掴んだ。
「はあっ!」
「へへっ、ここから下だ」
そのまま右手を下へ下へと、ゆっくりとなぞっていき、人差し指で丁寧にお尻の穴を広げる。
「ひぃ!ぎゃあっ!大三郎!」
「おいおい、まだ触っただけだぞ」
「だって、そこは!」
「ちょっと、舐めてやるからさ」
権藤はゆっくりと顔を金太の股ぐらに近づける。
そして、舌でその部分をチロチロと舐めていく。
「はあっ! ああっ! おわぁっ!!」
「2本、指を突っ込んでやるか」
「そんなのムリだっ!」
レロレロと自在に動く権藤の舌、そして指。
意識が飛びそうになり、金太は体をもんどり打たせる。
興奮が絶頂に達する。
「あっ、やっ!やっぱ・・んあっ、ダメだ!」
興奮のあまり、普段からは想像もつかないような喘ぎ声を出す金太。
もはや「ああっ」とか「ううっ」と悲鳴に近い声をあげる以外に、なにもすることはできなかった。
全身が激しく痙攣し、僅かに残った羞恥心も、すべて捨て去るしかない。
「はんんんっ、もう逝きそう、大三郎・・・!」
「キンタ、お前のことを一生愛してやる」
「はああっ!」
「だから、俺と一緒になろう。1つになろう。俺とお前はそういう運命なんだ」
「俺の運命・・?」
「決まっていたんだ。俺を受けて入れてくれたあの日から・・」
「大三郎・・俺は・・」
「頼む、キンタ!『そうだ』と言ってくれ!」
「うっ・・・」
「キンタ!」
「・・・」
「どうして答えてくれないんだ」
「ううっ・・ダメだ、出ちまう!」
金太はそのまま、体中が白い液体にまみれた。
そして、まだ次の試合が控えている権藤を、ただ無言で送り出した。
いきなりエロくてどうしよう・・。