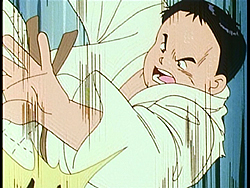 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
なかなか先に進みませんが・・。
登場人物
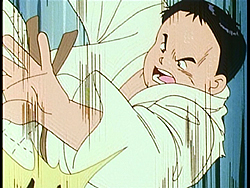 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
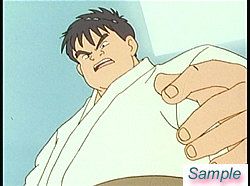 権藤大三郎。柔道のライバルだが、同時に金太に好意を持っている。
権藤大三郎。柔道のライバルだが、同時に金太に好意を持っている。
──「今日はこれまで!」
──「ありがとうございました!」
主将の掛け声。
そして、部員の元気のよい挨拶。
1日の厳しい稽古が終わる。
全員の柔道着がびっしょりと汗に濡れ、体育館の熱気が最高潮に達している。
部員たちは、ガヤガヤと会話をしながら、それぞれ帰宅の途についていく。
出口に人だかりができ、やがて人影がなくなる。
しばらく経ったあと・・。
道場の中央に、ポツリと人影。
厳しい顔つきをした、金太の姿だった。
シーンと静まり返った道場の中。
もう太陽も沈みかけ、体育館の中も薄暗くなっている。
「えいっ!」
「たぁ!」
前転して一回転。
手から肘までを使い、畳をバシンと片手で叩く。
畳にぶつかる際の衝撃を和らげる、柔道の受け身の稽古だ。
金太は、1人で何度も何度も、受け身を繰り返していく。
傍から見ると、とても地味な練習だが、これが金太の昔からの練習方法だった。
「はぁはぁ・・」
額から流れる汗を拭い、さらに受け身の稽古を続ける。
まるで、なにか迷いを捨て去るように、一心不乱でやりとおす。
(ふぅ・・。受け身は柔道の基本中の基本だ。
がんばらなくちゃ。基本ができていなければ、他には何もできないんだから)
バシンと響き渡る畳を叩きつける音。
何百回と繰り返しただろうか。
しかし、金太はゆっくりと立ち上がると、なぜか「クソッ」と大声で叫んだ。
(ダメだ・・・。受け身の練習をいくらしたところで、強くなれない・・。
昨年は3年生の土門さんに、稽古をつけてもらえたけど、いまは誰もいない。
こんなことで、俺は強くなれるのか?
このままじゃ、大三郎に勝てないに決まってる。
ただ、俺は自己満足で練習しているだけじゃないのか・・?)
いくら金太が1人で練習をしたところで、それ以上の成長は見込めない。
だからといって、金太の実力に見合う練習相手は、この学校には誰もいない。
「ちくしょう・・」
金太はギュッと目を瞑り、片手で畳をむしるように掴んだ。
・
・
その寂しい背中を、道場の入り口から1人だけ見つめるものがいた。
──その日の夜。
金太は母親とテーブルで向かい合って食事をしていた。
「ごちそーさま」
「太郎、元気がないわね?」
「そんなことないよ、母ちゃん・・」
「柔道部でなにかあったのかい?」
「ううん・・」
金太は夕飯を済ませて、黙って母親の皿洗いを手伝う。
その後、自分の部屋で宿題をする。
部活の疲れで、勉強との両立は大変だったが、そこは根性でカバーする。
それが金太のポリシーだ。
だから、勉強も手を抜くことは絶対にしなかった。
しばらく机に向かっていた金太は、ようやく宿題が片付いたのか、背伸びをしてほっと一息ついた。
(いい加減に、アイツに返事を書かなくちゃ・・・)
金太は勉強机の、一番右上の引き出しをそっとあける。
そこには、綺麗に折りたたまれたたくさんの手紙が積まれていた。
金太は一番上の新しい手紙を取り出す。
そして、少し照れくさそうな表情で、その手紙に目を通した。
『──金太へ。
何度も手紙を書いてゴメン。
ずっとお前からの返事がなくて、心配してるんだ。
まさか俺のこと、嫌いになっちまったのか? 俺の気持ちは変わっていない。だから時間のあるときに返事が欲しい。
秋の大会に向けて、仕上げは順調かい?
俺は毎日しごかれて、柔道漬けの生活を送ってる。
昨日は、高校生と練習試合までさせられてさ。
さすがの俺もキツかったぜ。
以前の俺は、柔道は大嫌いだったけど、だんだん好きになってきている。
それに最近になって、俺から柔道を取ったら何も残らないことに気がついたんだ。
だから、俺はずっと柔道を続ける。
柔道を続けていれば、お前にまた会えるしさ。
今年も全国大会に出てこい。俺と対戦しよう。約束だぞ。
昨年の全国大会で対戦した日、ムリヤリに倉庫でエッチしちまって悪かった。
俺はお前に久しぶりに会って、どうにも気持ちを抑えることができなかったんだ。
あの時、お前と交わしたキスの味も、お前の体の温もりも、すべてが俺の手に残ったままだ。
それにお前が俺のことを"大三郎"って呼んでくれたとき、心臓が破裂しそうになったよ。
俺は東京に引っ越して、お前との距離が離れた。
最近になって、俺はどうしたらお前の力になれるのか、そんなことを考え始めた。
どんな形でもいい、どうしたら遠くからでもキンタの力になってやれるのか、考えている。
だから、もし苦しいことがあったら、手紙に書いてくれ。
こんな俺でよかったら、いつでも力になってやる。
・・・
お前は俺を受け入れてくれるのか・・?
次に会ったときに答えを聞かせてくれ。
たとえ答えがNoであっても、俺はずっとお前のことを見守りたい』
金太は手紙を途中まで読んで、その手紙を折りたたんだ。
そして僅かに微笑んで、権藤の手紙を胸にあてる。
(大三郎のヤツ、少し変わったな・・。
昔の大三郎はすぐに体を求めていたのに、いまは男同士の恋愛を一歩引いて考えている感じがする。
でも、俺は男が男を愛するなんて、やっぱりよく分からないよ。
だから、お前がいくら俺を求めても、俺はなにをしたらよいのか分からないんだ。
全国大会の日だって、俺はお前の行為を拒絶するつもりだったのに・・。
・・・。
俺はこの半年間、お前と手紙でやりとりをしていて気がついた。
手紙を読むたびに俺は大三郎に会いたいと思っている。
俺はそれが怖い。大三郎と一緒にいたいと感じる自分が怖い。
だって、その先には・・。
その先には一体なにがあるんだ?
男同士の恋愛の先に、一体なにがあるっていうんだよ・・。
俺には分からない。答えを出すことなんて出来ないよ・・・)
金太はボケッと物思いにふけながら、しばし遠くを見つめていた。
そして、机から新しい便箋を一枚取り出し、ゆっくりと返事を書きはじめた。
「大三郎へ。
大三郎、しばらく返事をしなくてごめん。元気か?
昨年の全国大会で、個人優勝するなんてさ。やっぱり大三郎はすごいな。
俺はお前に一回戦で負けて、団体戦でも負けたから、通算で6連敗だ。
全部弱点を克服したはずなのに、やっぱりお前のほうが強かった。完敗だ。
でも、次はお前に勝ちたい。7連敗はごめんだ。
俺はこの春から、春風中の主将になった。
昨年に全国大会に出場したせいか、今年はたくさん新入部員が入ってきたんだ。
でも、伸び悩んでいてさ・・。このままじゃ、1年生はまだまだ時間がかかりそうだ。
俺は毎日、自分の稽古もできずに、1年生に付きっきりだ。
今度の地区予選を突破できるか、正直自信がないんだ。
だから、大三郎と戦えるか分からない。約束を守れるか分からない。
それに、いまの俺には練習相手だって、誰もいないよ。
大三郎がいてくれたらよかったのに。大三郎と一緒に柔道ができたらよかったのに。
明法大付属中はいいよな。全国から強いヤツが集まってくるんだろ?
いい環境だよな。俺もそんなところで、お前と一緒に柔道を・・」
・
・
金太はそこまで書いて、筆を下ろした。
(クソッ・・・なにを書いているんだ、俺は・・・)
途中まで書いた手紙を両手で握り、クシャクシャにしてゴミ箱に入れた。
(俺は、大三郎と一緒に柔道をしたいと思っている。
大三郎に会うために、全国大会に行きたいと思っている。そして体を合わせたいと考えている。
まるで、大三郎が以前に俺を求めていたのと同じように。
それに、大三郎だけが強くなったことに、嫉妬している・・。俺らしくねぇ)
すべてを迷いを断ち切るように、首を横に振る。
そして、机の上にある柔道の雑誌を手にとった。
イスにもたれながら、ペラペラとページをめくってみる。
そこには、小さな特集記事。
昨年行われた、中学生柔道大会のコラムだ。
『オール一本勝ちの中学1年生。期待の新星現る』
『将来のオリンピック候補、権藤大三郎君』
『10年に1人の天才現る』
コラムには、いかにも読者が喜びそうなキャッチコピーが書かれているが、実際に権藤大三郎の実力は本物だ。
中学1年生で全国の頂点に立つなんて、普通じゃ考えられない。
(柔道の天才か・・そうかもな・・)
権藤大三郎は、いまや柔道界ではちょっとした有名人になっていたのだ。
(俺はこのままじゃ一生、大三郎に勝つことは出来ない。
一体なにが違うんだ・・。アイツが残したノートに書いていた弱点はすべて克服したはずなのに。
俺と大三郎の間に、見えない壁を感じる。俺はなにをしたらいいんだ・・・)
金太は感じていた。
権藤大三郎との力の差が、どんどん開いている。
もはや権藤は、自分を柔道のライバルとして見てくれないのではないか?
遠い存在になってしまったのではないか?
そのことが、金太を余計に不安にさせていた。
(ちくしょう、俺はこんなところでなにやってんだ!)
金太は不安と苛立ちから、机を思いっきりバンと叩き付けた。
なかなか先に進まなくてアレですが・・。