 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
1人で練習に明け暮れる金太だったが・・?
登場人物
 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。

──翌日。
金太は稽古が終わった後に、1人で居残り練習を続けた。
「えいっ!」
体育館の中が暗くなっても、立派な照明設備があるわけではない。
それでも、すっかり空が暗くなるまで畳を叩きつけて、受け身の練習。
そして、柱にロープを結んで投げの練習。
額に汗を吹き出すようにかきながら、基本の型と受け身を1人で稽古する。
体を動かしているときは、無我夢中でそれなりの充実感はあった。
しかし、ふと気がつくと、自分がポツリと1人、広い道場に立っているだけだった。
(クソッ、こんな練習をいくらしても仕方がない。
これじゃ、小学生のときにドラム缶相手にやっていたことと同じじゃないか。
ちくしょう・・どうすりゃいいんだよ・・もし大三郎がいてくれたら・・)
金太の心には、虚しいすきま風が通るだけだった。
歯をギュッと食いしばって、襲い来る孤独感に耐えた。
「あの・・白金主将・・」
蚊の鳴くような小さな声だったが、静まり返った道場にはよく響いた。
「だ、誰だ!?」
金太は慌てて入り口に振り向く。
「あの・・オレです・・」
道場の入り口には、柔道着姿のまま立ちすくむ南条隼人の姿があった。
隼人は心配そうな表情をしながら、金太をジッと見つめている。
なぜこんな遅い時間に、隼人がまだ柔道着を着たまま立っているのか、金太は困惑した。
「南条じゃないか?」
「すみません、邪魔をしてしまって・・」
「こんな時間まで、どうして残ってるんだ?」
「それはオレが聞きたいです・・」
「えっ?」
「主将、どうしてこんな遅くまで練習してるんですか?」
「・・・」
「どうして1人で練習してるんですか?」
隼人の質問に、金太は後ろを向き、目を合わせずにただ黙っていた。
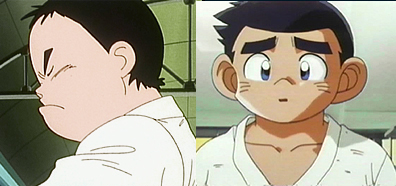
しばらくして、隼人が尋ねてきた。
「白金主将?」
「な、なんだ?」
「もしオレでよかったら・・オレなんかでよかったら、練習相手になります」
「南条が?」
隼人の提案に、金太は振り向いて笑顔を見せたが、すぐに厳しい顔つきに変わる。
「そりゃうれしいけど・・。でも、部活の時間はとっくに終わってるんだ。
俺は主将として、こんなに遅くまで部員を練習させることはできないよ。家族も心配するだろ」
隼人は、金太の言葉を否定するように、首を横に振った。
「かまいません。オレの父さんは、大学の柔道の講師をやっていて、
いつも帰りが遅いんです。だから、いつもオレは1人です。いつも1人で飯も食べてるッス。
だから、父さんのことなら心配する必要ありません。それよりもオレは主将と一緒に柔道したいんです!」
「だって、お母さんが心配するだろ?」
金太の質問に、隼人は視線をそむけた。
そして、おもむろに口を開いた。
「母さんはいませんから・・」
「えっ?」
「オレ、小さいときに母さんを亡くしたんです」
隼人の寂しそうな顔に、金太は聞いてはいけない質問をしてしまったと後悔した。
そして、グッと胸を詰まらせた。
2人の間に、気まずい空気が流れる。
しかし、それを打ち破ったのは隼人の明るい声だった。
「オレ、白金主将と柔道やりたいんです。
そのために春風中の柔道部にわざわざ入ったんです。だから、お願いします。
オレ、足を引っ張らないように、精一杯がんばりますから」
必死に言葉をつなげてくる隼人に、金太の表情は自然と柔らかくなった。
「南条、ありがとう。ならば、残りの時間、付き合ってくれるか?」
「オスッ! 喜んでつきあわせてもらいます!」
「じゃ、柔軟をしてから、軽く乱取りをしてみようか」
「任せてください!」
隼人は小走りに道場の中央まで進む。
そして、金太の目の前でニコッと微笑んだ。
ほんの少し、頬を赤く染めて照れながら。
「よし来い、南条!」
「うおーっ!」
道場の中央で向き合う金太と隼人。
乱取りとは、試合をある程度想定して、実際に柔道の技の掛け合いをする練習のことだ。
金太は隼人の足裁きを確認しながら、左右にフットワークをきかせる。
(南条、思ったよりも動きがいいな・・)
一瞬のスキをつき、襟をとって一気に引き付ける。
そして、隼人の懐に飛び込んで、体を密着させた。
「とりゃっ!」
そのまま右腕を、隼人の右脇に入れて担いで、あっという間に一本背負いを決めた。
隼人はドスンを音を立てて、畳に叩きつけらる。
久しぶりにすっきりするような背負い投げだった。
(やべ・・!)
しかし、それと同時に金太は背筋を凍らせた。
手加減せずに、思いっきり隼人を投げてしまったのだ。
もし隼人にケガでもさせてしまったら、それこそ一大事だ。
しかしよく見ると、隼人はきちんと片手を畳に叩きつけて受け身をとっている。
「痛ててっ」
「南条、大丈夫か!?」
「はい、大丈夫ッス。もう一回お願いします!」
「ふぅ、よかったぜ・・。南条の動きがあまりに良かったから、つい手加減しないで投げちまった」
「かまいません、オスッ!」
その後も、金太は隼人を、得意の背負い投げに持っていく。
ズシンとか、ドシンという畳に体が叩きつけられる鈍い音が、道場に響く。
金太にとっては、久しぶりに気持ちがいい音が続いた。
「ふぅ・・。南条、これくらいにしようか。疲れただろう?」
「いえ、これくらいへっちゃらッス。主将の背負い投げは分かっていても、防げないッス!」
「俺も久しぶりにいい感触だったよ」
「ほ、本当ですか!?」
「あぁ。南条はきちんと受け身を取れるんだな。驚いたよ」
「オレ、父さんに昔よく投げられていたから、受け身は体で覚えてます」
「昔? いまは父さんと柔道やっていないのか?」
「いやその・・春風中の柔道部に入ったから・・それで・・」
「そうか。南条には父親というコーチがいて、うらやましいな。また明日、時間があったら付き合ってくれ」
「オスッ!! 毎日付き合わせていただきます!」
金太は晴れやかな笑顔を浮かべて、隼人の肩を軽くポンッと叩く。
そんな金太の何気ない仕草に、隼人は幸せな笑みを浮かべていた。
全然進んでない(^^;