 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。後輩である南条隼人を育てたいと考えている。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。後輩である南条隼人を育てたいと考えている。
今回は少し長めの小説かも・・。
登場人物
 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。後輩である南条隼人を育てたいと考えている。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。後輩である南条隼人を育てたいと考えている。
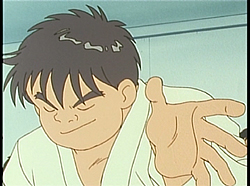 権藤大三郎。現在は東京に引っ越しており、明法大付属中の2年生で柔道部に所属。金太のことが好き。
権藤大三郎。現在は東京に引っ越しており、明法大付属中の2年生で柔道部に所属。金太のことが好き。

「ハァハァ・・」
息が苦しい。
勝てない。
またコイツだ・・。
体が大きくて、ビクともしなくて・・。
どうして、こんなに強いんだ・・?
柔道着の襟を掴もうとしても、すぐに剛力で弾き飛ばされる。
そして、あっという間に足を払われて、何度も畳に叩きつけられる。
さらに、寝技だ。
「ちくしょう、コイツ・・!」
ガッチリと押さえ込まれ、胸やアソコを好きなように鷲づかみにされる。
「はあっ!あっ・・あっ」
悶え苦しみながら、必死に寝技を外そうとするが、何もすることができない。
そして相手の姿がだんだんとはっきりしてくる。
押さえこんでいるのは・・。
「権藤大三郎・・!」
『お前、随分と弱くなったじゃないか』
「弱くなった・・? 俺が・・?」
『違うな。お前が弱くなったんじゃない。俺が強くなりすぎたんだ』
「そんな・・」
権藤は耳元でささやく。
『もうお前はライバルじゃねぇ。弱いお前なんか、魅力もなにもねーぜ』
「待ってくれ! 俺はお前と柔道したいんだ。お前と一緒にいたいんだ!」
『へぇ、いまさら俺のことを好きになったのか? 散々、拒絶していたくせに』
「・・・」
『俺のことが好きなら、俺に見合う強い男になってくれや』
権藤が技を解く。
そして、背中を向けて、ゆっくりと歩き始める。そして、遠くへと去っていく。
「大三郎、待ってくれ!」
いくら叫んでも、権藤は立ち止まろうとしない。
大きな背中が、だんだんと小さくなって・・。
・
・
「白金主将、大丈夫ですか!?」
「うぅ・・大三郎・・うーん・・」
「主将!」
「あ、あれ・・」
目をあけると、いつも見慣れた道場の風景。
天を向いて倒れた金太に、南条隼人が横から必死に呼びかけている。
ボッと隼人を見つめにながら、金太は呟いた。
「俺は・・そうか、南条に一本取られたのか・・」
「白金主将・・」
どうやら、居残り稽古中に、受け身を取り損なって頭を強打してしまったらしい。
数秒は気絶してしまったのだろうか?
金太は頭をさすりながら、おもむろに立ち上がった。
「痛てて・・」
隼人は相当に心配したのか、いまにも泣き出しそうな顔をしている。
「どうしたんですか、最近、主将らしくないです」
「大丈夫だ。情けないところを見せちまったな」
「もう予選は明日ッス。白金主将が最近は調子が悪くて、自分はすごい心配です・・」
「調子が悪いんじゃないよ。たぶん南条が強くなったんだ」
「そんなことないです」
「とりあえず、今日は早いけどこれまでにしよう・・。予選の前日にケガしたら元も子もないしな」
「オスッ!」
予選を明日に控え、金太と隼人は最後の仕上げを行っていた。
金太はすでに予選の団体メンバーを、部員たちに告げていた。
地区予選の団体戦は5人がそれぞれ先鋒、次鋒、中堅、副将、大将となり、一対一の勝負を行う。
先に3勝したほうのチームが勝利となる。
金太が選んだ先鋒は、南条隼人。
1年生の中でただ1人だけ、大抜擢をした。
1年生で元気のよい隼人に、チームとしての勢いをつけて欲しかったのだ。
そして次鋒、中堅は、前回の大会でレギュラーだった2年生。
副将は副キャプテンの大河原が努める。
そして、大将は白金太郎。
このメンバーの選択について、
他の1年生からは、<南条だけが選ばれるなんてズルい>とヤッカミがあがった。
隼人1人だけが金太に可愛がられている事実に、陰口が出るのは仕方がない。
いくら隼人に実力があることは分かっていても、人間は嫉妬心があるのだから、避けようがないだろう。
だから、南条隼人が他の1年生から、仲間はずれにされていたことも金太は分かっていた。
しかし、それは試合に勝って、実力を証明すればいいだけのことだ。
隼人にはそれだけの力と勢いがある。
だから、金太は確信していた。
先鋒の南条隼人、そして副将の大河原、そして自分で3勝して予選を突破できると。
そのために、隼人を猛特訓して育て上げた。
そして、全国大会で権藤大三郎と戦う。
金太は、この1年間をすべて、権藤大三郎と戦うために、練習してきたといっても過言ではない。
権藤大三郎に勝つことで、きちんと腹を割って話すことができるような気がしていた。
1つの壁を超えて、その先にある"何か"を金太は掴み取りたかった。
金太は心配そうに見つめる隼人に、ニコッと笑う。
「南条、明日は期待してるからな」
「ハイッ!」
「今日は家に帰って、きちんと飯を食えよ。ちゃんと食べないと力もでないしな」
「オス・・でも今日は父さんがいないから、またカップラーメンにしようかと思ってます」
「そんな食事じゃ、明日の試合に負けちまうぞ」
「でも、しかたないです」
ショボンと視線を落とした隼人に対して、金太は腕組みをして考える。
なにか名案が浮かんだのか、パチンと指を鳴らした。
「よーし、今日は俺ん家に来いよ。母ちゃんが美味いもの作ってくれるからさ。一緒に食事でもしよう」
「ほ、本当ですか!? 主将の家に行ってもいいんですか? うれしいッス」
「じゃ、このまま帰るか」
「オスッ!」
隼人は明るい声で返事をすると、にっこりと微笑んだ。
金太と隼人は、柔道着姿のままカバンをぶら下げて、ゆるゆると家路についていた。
体の大きな2人、しかも街中を柔道着姿で歩けば、かなり目立つだろう。
しかし、柔道を誇りとしている金太には、他人の視線は気にならなかった。
たとえ隣に、南条隼人が一緒に寄り添っていても。
「フンフン・・」
なにやら隼人は上機嫌で、鼻歌混じりで歩いている。
自分よりも年下で、なにも知らない純朴な少年。
南条隼人には、そんな言葉がピッタリと似合う。
そして、金太は隼人が明日に大会デビューをして、大活躍をすると思うと、とても清々しい気分になった。
「白金主将の家って、どんな家なんですか?」
「普通のオンボロの一軒家さ」
「オレ、なんかワクワクします」
普段見慣れぬ隼人のはしゃいだ様子に、金太は顔つきが自然と柔らかくなった。
人通りが少なくなった住宅街に入る。
「主将〜」
鼻歌交じりの隼人は、突然金太に寄り添うように腕組みをした。
反射的にビクリとする金太。
隼人は、金太の腕の感触を確かめるように、顔をすり寄せる。
「オレ、いま主将と一緒で、幸せッス」
「お、おい・・変なこというなよ・・」
「えへへ・・いいじゃないですか。こうしているとオレたち、どういう風に見られますかね?」
「どうって、男同士なんだから、変にみられるだろ」
「そうですか? 柔道の先輩と後輩って感じで、こういうのに憧れていたんです」
「あのな・・」
天真爛漫な隼人に対し、金太はフッとため息をついた。
恥ずかしいので腕を放そうかと思ったが、
嬉しそうな隼人の顔を見ていると、突き放すのも大人気なく感じた。
金太は仕方ないという表情で、腕を組んで歩き続ける。
とても幸せそうな顔をしている隼人に、つぶやいた。
「なぁ、南条? 1つ聞いてもいいか?」
「ハイ!」
「お前はどうして春風中の柔道部に入ったんだ?
だって、南条のお父さんは柔道のコーチなんだろう?
春風中の柔道部に入るよりも、お父さんの大学でコーチしてもらったほうが強くなるんじゃないのか?」
その質問に、隼人は急に表情を曇らせて、シュンとなる。
そして、しばらくして小さな声で返してきた。
「答えなくちゃいけないですか・・?」
「いや、別にそういうわけじゃ・・。でも俺はほとんど南条のことを知らないし・・」
しばらく無表情で考えていた隼人だが、重い口を開いた。
「分かりました。白金主将にだけは、本当のこといいます」
「別に無理に言わなくてもいいんだぞ」
「大丈夫です。実はオレ・・・その・・・柔道をやめようか思っていたんです」
「ええ!?」
「オレはいままでずっと父さんに振り回されてました。
父さんの仕事の関係で、毎年引越しばかりだったんです。
だから、オレには友達もできなかったし、春風中だっていつまでいられるか分かりません」
「それは本当なのか・・?」
「はい。父さんは『柔道で金メダルを取れ』って毎日厳しい稽古をつけてくれました。
父さんは自分が柔道でオリンピックに出場するという夢を叶えられなかったから、
オレにその夢を託しました。
オレに柔道で世界一になって欲しいと思っているんです。
でも、オレは学校の友達と遊びたかったし、別に柔道したくなかったんです。
オレは父さんの操り人形のように、毎日毎日、稽古ばかりで・・。
でもある日、ミニ四駆っていうおもちゃで師匠みたいな人ができて、
その師匠ととても仲良くなりました。もう2年も前の話です」
隼人から、先ほどまでの明るさがなくなり、なぜか悲しい表情になっていた。
元気が取り得の隼人が、こんな表情をするなんて。
金太は悪いことを聞いてしまったのかと、不安になった。
だから、隼人の肩にそっと暖かく手を回した。
「白金主将・・?」
「南条、もう話さなくていいよ。他人には知られたくないことってあるだろう?」
「ハイ、ありがとうございます。白金主将はやさしい・・手がとってもあったかい・・。
オレ、白金主将には自分のこと、たくさん知って欲しいんです。
だって、いまのオレが話せる相手は、白金主将しかいませんから・・」
「そんなことないよ。柔道部に仲間がたくさんいるだろ」
「でも、オレはあんまり友達いないんです。
柔道部のみんなはオレがレギュラーになって羨ましいのか、口を聞いてくれません。でも白金主将は特別です」
「俺は特別でもなんでもないよ。
ただ、俺は南条のことをもっと知らなくちゃいけないと思っていたんだ。
ずっと一緒に稽古してきたのに、俺は南条のことをあまりに知らなさすぎるんだ。
よかったら続きを話してくれよ。俺が力になれることはなんでもするからさ」
「白金主将・・うれしいッス・・」
隼人は少し落ち着いたのか、少し真面目な声で話しかけてきた。
「オレは2年前にミニ四駆の師匠と出会って、そのときに父さんと初めてケンカをしました。
オレはどうしてもミニ四駆をやりたくて、それで柔道の大会をすっぽかしてまで、ミニ四駆の大会にでたんです。
父さんは、その大会を見に来てくれて、オレの笑顔を初めて認めてくれました。
オレが柔道とミニ四駆を両立できるならば、ミニ四駆をさせてくれると約束してくれました。
そのときはうれしかったです。やっとクラスの仲間と遊ぶ時間ができたって。
・
・
その後、オレは引越して、ミニ四駆の師匠と別れました。
オレは引越した街で、新しい友達とミニ四駆ができると、心から楽しみにしていたんです。
でも父さんは、やっぱり許してくれませんでした。
あのときに父さんが言ったことは、その場限りのウソだったんです。
オレは再び父さんの操り人形になって、ずっと柔道をさせられました。
学校から帰ったらすぐに柔道、朝起きたらまた柔道・・オレ、もう耐えられなくなりました。
父さんといつのまにか口を聞かなくなって、柔道もやめました。
オレは、父さんが嫌いだ・・・。柔道も、大嫌いです!」
隼人は、怒りに全身が震えるような声をだした。
隼人が感情をむき出しにした姿に、金太は正直驚いた。
いつも明るくて、笑っている隼人に、そんな過去があったなんて。
金太は少し動揺したが、怒りに震える隼人の肩をギュッと握り締めた。
「南条、話してくれてありがとうな」
「スミマセン。オレ、ついカッとなっちゃって・・」
「いいんだ。しかし、驚いたよ。
まさか南条から『柔道が嫌い』なんて言葉が出るとは思わなかった。
だって、俺と居残りで柔道しているときのお前は、輝いていたぜ。
柔道が大好きって感じだった。
俺は南条か柔道部に入ったとき、お前のやる気の無さが気になっていたんだ。
実力はあるのに、まるで柔道に興味がないような、そんなお前を不思議に思っていた。
その謎が少し解けたような気がするよ。
でも、どうして春風中の柔道部に入ったんだ? 柔道は嫌いなんだろう?」
「それは・・・」
隼人は、そのまま貝のように口を閉ざしてしまった。
金太は隼人の心の内を察して、やんわりと言葉をつなげた。
「そっか・・。別に無理して話さなくていいよ」
「すみません。俺、どうしてもいま話す勇気がなくて・・」
「いいさ。俺はいまの南条は、柔道が好きになったと信じてるからさ」
「主将・・・」
金太は隼人の肩をしっかりと抱いたまま、ゆっくりと家に向かって歩を進めた。
(柔道が嫌いか・・。まるで昔のアイツとそっくりじゃないか・・)
金太は漠然と思った。
南条隼人の境遇が、権藤大三郎の境遇に似ていると。
次回をお楽しみに(←ォィ)