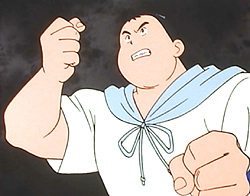 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。後輩である南条隼人を育てたいと考えている。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。後輩である南条隼人を育てたいと考えている。
隼人のとんでもない行動に金太は・・?
登場人物
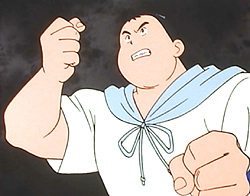 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。後輩である南条隼人を育てたいと考えている。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。後輩である南条隼人を育てたいと考えている。

・
・
「ううっ・・ごめんなさい・・」
隼人はいまにも泣きそうな表情で、畳の上に正座をしていた。
太ももの上の拳をギュッと握ったり、緩めたりして。
隼人は自分のしてしまった行為が、最低であることは分かっていた。
他人のパンツを脱がして、おちんちんを舐めるなど、無礼にもほどがある。
しかも、それが一緒に練習をしてきた柔道部の先輩であり、尊敬すべき金太に対してなのだ。
だから、金太に罵倒されようが、殴られようがかまわないと思った。
金太はブリーフ一枚の格好から、いつものパーカーがついた白い私服に着替える。
その間、一度も隼人に振り返ることはなかった。
その後も金太はしばらくの間、両腕を胸の前に組んで、ただ背中を向けて黙っていた。
金太の震える後姿から、彼が怒っていることは容易に想像がついた。
隼人には、その時間が永遠のように長く感じられたのだ。
(白金主将はオレのことを軽蔑したに決まってる・・。オレはなんてことをしてしまったんだ・・)
隼人は軽はずみな行動で、取り返しのつかないことをしてしまったのだ。
それが隼人の心に痛く、そして重くのしかかっていた。
沈黙を破ったのは金太だった。
「南条、自分のしたことが分かっているのか?」
「・・・」
金太の声は怒っているというよりは、隼人に問いかけているような感じだった。
てっきり、金太にぶん殴られると思った隼人は、ほんの少しだけ安心した。
「白金主将、スミマセン。
オレ、主将が寝ているところを、ちょっとイタズラしようと思ってやっただけなんです」
その言葉に、金太は隼人に振り向き、そして激しい怒りをぶつけた。
「イタズラだと! ふざけんな!」
「あの・・その・・」
「ウソつくなよ。もしイタズラだったら、力一杯ぶん殴るぞ」
「ス、スミマセン・・」
「南条、頼むから本当のことを言ってくれ。
どうして俺のアソコなんか舐めたんだ?
だって・・その・・おかしいだろ? こんなところ、普通舐めるモンじゃねぇんだぞ。
まさかと思うけど、お前は男のくせに、俺の体に興味があったのか? 触りたかったのか?」
「・・・・」
「黙っていちゃ、何も分からないだろ? 怒らないから本当のことを言ってくれ。
このままじゃ明日の試合は、お互いに平常心でできるわけがない。
勝てるものも勝てなくなっちまうんだ。このまま中途半端にしちゃいけないんだよ!」
金太は不満に口を尖らせたが、それは隼人の行為を怒っているのではなく、
隼人が真実を伝えずに、ただ黙っているのが許せないという気持ちからくるものだった。
しばらくして、隼人は蚊の泣くような声を振り絞った。
「分かりました・・白金主将・・。
オレ、いままで隠してきたけど、本当のこといいます。
でも、オレのことを嫌いにならないで欲しいです。オレと一緒にずっと柔道して欲しいです・・」
「当たり前だろ。俺の柔道のパートナーは南条しかいないんだ。だからこそ言ってくれ」
隼人は真剣に金太の瞳を見つめる。
そして、少し気持ちが吹っ切れたのか、はっきりとした口調で語り始めた。
「帰り道に、白金主将は"どうして春風中の柔道部に入ったのか?"って聞きましたよね?
だから、それから答えます。
オレ、さっき話したとおり、父さんと口を聞かなくなって、それで柔道もやめました。
柔道のことが嫌いになって、もう二度とやりたくないと思ったんです。
でも、ある日たまたまテレビを見ていたら、柔道の試合がやっていて、その試合にオレは見入ってしまいました。
いつの間にか手に汗を握りました。他人の試合で熱くなって、興奮したのは、そのときが初めてでした。
それが、昨年の中学柔道大会の、白金主将と権藤大三郎さんの試合だったんです。
たった1つ年上の先輩が、すごい試合をしているのを見て、オレはもう一度柔道やりたいって思いました」
「俺の試合で・・?」
「白金主将のことは、そのときからの憧れでした。
今年になって、オレが引っ越す先が春風町だと知ったとき、
オレは胸が躍りました。だって、春風町には春風中があって、そこには白金主将がいることを知っていたからです。
オレは春風中に入るとすぐに柔道部に入り、白金主将に挨拶をしました。
"白金主将に憧れてます。一緒に柔道やりたいです"って勇気を振り絞って言いました」
「あぁ。それは覚えているよ。夢はオリンピックで金メダルだったよな?」
「はい。でも金メダルなんてどうでもよかったんです」
「どういう意味だよ・・?」
隼人の発言を不審に思った金太は、再び尋ねた。
「金メダルなんてどうでもいいって、どういうことだ?」
「オレ・・白金主将のことが好きです」
その言葉に金太はビクッと反応する。
しかし、すぐに冷静を装って返事をする。
「"好き"っていっても、いろいろとあるだろ。友達として"好き"とか、先輩として憧れているとか。
お前の"好き"は、どういう意味の"好き"なんだ?」
「言葉のとおり、好きなんです。オレは男なのに、白金主将のことが大好きです。
おかしいッスよね・・。だって、普通は男は女の子を好きになるはずなのに。
白金主将のこと、毎日考えてるんです。毎日ビデオみてます。
そして考えてます。オレの部屋に白金主将がいて、優しく微笑んでくれるんです。
外では主将と腕を組んで歩いて、一緒にお風呂入ったりして、それで一緒に体を触りっこしたりとか・・」
「・・・」
「だから、主将がこの部屋で寝ている姿を見たとき、自分の欲求を抑えることができなくなりました。
毎日、あれこれ考えていることが、現実にできることを知って、居てもたっても居られなくなりました。
思わず、白金主将の一番大切なところを触りたくなりました。白金主将のすべてを知りたかったんです。
もうビデオを見ているだけじゃ、満足できないんです。
オレ、とんでもないことしちゃって、本当にスミマセン。ごめんなさい。
軽蔑されて当然です。男が男を好きだなんて、本当におかしいとは思っているんです・・」
隼人の声は徐々に震えだしていた。
そして、目に一杯の涙をためて、必死に言葉を伝えていた。
たとえ、それが金太に伝わらなくても、隼人は自分の正直な気持ちを話したかったのだ。
隼人の話に、金太は困ったように頬をかいた。
そして、改めて尋ねた。
「俺のことを"好き"っていうのは、俺のことを"愛している"っていう意味なのか?」
「・・はい。たぶん・・」
「俺の体を触りたいのか? 俺と・・その・・エッチみたいなこともしたいのか?」
「はい・・」
「寝技の練習のときに俺の体を触ったのは、本当はエッチしたかったのか?」
「すみません・・。父さんから教えてもらったというのはウソです。
白金主将の体をどうしても触りたくて・・・俺、最低なことしちゃいました。本当にすみません」
「リョウジョクを知らずにやったってことか・・」
「え?」
「いや、その・・なんでもない」
金太は再び、黙り込んでしまった。
隼人はそんな状況がいたたまれなかったのか、さらに会話を続けた。
「オレが柔道をしているのは、ただ白金主将と一緒にいたかったからです。
不純な動機ッス。白金主将は全国大会に出るために一生懸命がんばっていたのに、
オレは、ただ白金主将と柔道ができれば、それだけで満足だったんです。
そんなオレでも、これからも柔道をしてくれますか? オレのことを受け入れてくれますか?」
隼人の頬からは、いつの間にか涙が溢れていた。
グズンと喉を詰まらせながら、懸命に言葉をつなげていた。
そんな隼人に対し、金太は腕組みをしたまま、しばらく黙ったままだった。
2人の間に静寂が走った後、金太が重い口を開いた。
「南条。すべてのことをきちんと話してくれたことは感謝する。ありがとう」
「主将・・」
「でも、今日のことはすべて忘れよう」
その言葉に、隼人は表情を曇らせ、耳を疑った。
「それはどういう意味ですか・・?」
「言葉通りだよ。南条が俺のことを男として好きなのは分かったよ。
だけど、俺には理解できないんだ。だって、男が男を愛するなんておかしいじゃないか。
もし、俺が中途半端に南条に愛情をかけたら、お互いが苦しい思いをすると思うんだ。
だから忘れよう。忘れることなんてできないかもしれないけど、俺はこれからも南条を後輩として接することにする。
そしていままでどおり、柔道もしよう。元のままが一番いいんだ」
「そんな・・」
「それでいいだろう? 俺のことは悪いけどあきらめてくれ。男に興味はない」
金太のあまりに厳しい返事に、隼人の目から大粒の涙が落ちる。
もしかしたら、金太が男同士の恋愛に心を開いてくれるんじゃないか・・。
金太から「付き合おう」と言ってもらえるんじゃないか。
そんな淡い期待を抱いていた隼人が、最も聞きたくない返事だったから。
「ううっ・・うっ・・」
「お前は男だろ。だったらもう泣くな」
「うっ・・えぐ・・」
「頼むから、しっかりしてくれよ」
「白金主将は、あまり驚かないんですね。"男が男を好きだ"と言われても。
普通なら嫌悪感さえ抱きそうなのに、まるで以前にも誰かから告白されたような答えです。
もしかして、以前にそういうことが・・あったんじゃないですか?」
「そ、そんなことあるわけないだろ!」
「白金主将は、男同士は付き合っちゃいけないと思いますか・・?」
「それは・・」
隼人の質問に一瞬たじろぐ金太だったが、すぐに切り返す。
「南条・・。ならば、教えてくれ。
男同士の恋愛の先に一体なにがあるんだ? 体を合わせたその先になにがあるってんだ!?」
隼人は涙を必死に拭いながら、なんとか返事をする。
「オレは先のことなんかどうでもいいんです。
オレは白金主将と一緒に居たいだけなんです。だって白金主将のことが好きなんだから。
理屈でなんか言えません。それじゃいけないんですか・・?」
「そんなの答えになっていないじゃないか。納得できるわけないだろ。
南条にはすまないが、俺には男同士の恋愛は、どうしても受け入れられないんだ。
それに、男が男を好きだなんて、他のヤツには言わない方がいい。理解されるわけがない。
俺は・・その・・軽蔑しないけど、他のヤツはきっとお前のことを毛嫌いするぞ」
「そんなの構わないッス」
「お前自身が悲しい思いをするんだ。もし、南条が俺に恋愛の関係を求めるようならば、
これ以上、一緒に柔道はしないほうがいいと思う。南条が傷つくだけだと思うんだ」
「う・・うっ・・どうして・・?」
「俺は南条のことが好きだよ。だけど、それは"愛する"ってことじゃない」
「・・・」
「だから、お互いに忘れよう。ごめんな。お前のことを受け入れてやれなくて」
「"ごめん"だなんて・・そんなこと言われたら、オレはますます主将のことが忘れられません。
だって、白金主将は優しいんだもの・・。でも、忘れろなんて・・!」
たしかに、いますぐに忘れるなんて言葉は、隼人にはひどい言い方だと金太は胸が痛んだ。
なぜなら、金太自身にも心当たりがあったから。
権藤大三郎のことがあったから。
しかし、隼人に優しい言葉をかけるのは、ただいたずらに隼人を苦しめるだけなのではないかとも思った。
隼人はしばらく声を詰まらせて泣いていた。
金太は隼人のことを優しく抱いてあげようとしたが、もしそれをしてしまったら、
それこそ取り返しのつかないことになると思い、ギュッと拳を握ってただ耐えていた。
お互いが苦しい時間を耐え抜いたあと、隼人の声が耳元に届いた。
「オレ、今日はもう帰ります。
白金主将が受け入れてくれなかったのは悲しいけど、主将はオレのことを軽蔑しませんでした。
だから、オレなんとかがんばってみます。
明日の試合はでます。白金主将のために絶対に勝ちます」
「南条・・・」
「もしかしたら悲しくて、心が苦しくて、今日は眠れないかもしれないけど、
オレは元気だけが取り得だし、メソメソしているのはオレらしくないから・・。
明日は実力は発揮できないかもしれないですけど、そのときは許してください。
でも、精一杯やりますから」
「ごめんな。お前のことを受け入れてやれなくて」
「いいんです。じゃ、オレ帰ります」
「じゃそこまで送って・・」
「いいです。白金主将にこれ以上優しくされたら、苦しくなるだけですから・・えへへ」
そういうと隼人は作り笑いをして、走って部屋をでていった。
金太は「がんばれ」と言葉をかけてあげたかったが、喉元でその言葉は止まってしまった。
心の中で、ただそう叫ぶしかなかった。
ノンケの人って同性愛を理解できるんでしょうかねぇ。