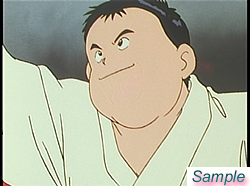 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
金太と権藤の恋の行方は・・?
登場人物
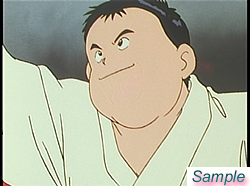 白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
白金太郎。愛称「金太」。春風中学校2年生で柔道部の主将。
 権藤大三郎。現在は東京に引っ越しており、明法大付属中の1年生で柔道部に所属。
権藤大三郎。現在は東京に引っ越しており、明法大付属中の1年生で柔道部に所属。
通路を駆け抜けていく隼人。
ただ、乾いた駆け足の音だけが、響いていた。
金太はポカンと口をあけ、一体どうしたらよいのか困惑していた。
「南条のヤツ、一体どうしたってんだ・・?」
そんな金太に、権藤が少し真面目くさった感じの声で話してきた。
「キンタ、一緒に帰ろう」
「でも南条が・・」
「アイツは分かったんだよ」
「なにをだよ?」
「お前のことが少しだけ理解できたんだ。だから1人にしてやれ」
「お前があんなにキツいことを言うから・・。南条が立ち直れなくなるかもしれないんだぞ」
その言葉に、権藤はフッとため息をついた。
「お前の優しさが、返ってアイツを苦しめることになる」
「し、しかし・・」
「たしかにキツいことを言っちまった。それは俺も分かっているんだ。
でも、アイツはキンタのことが好きなんだろう? だったらきちんと言った方がアイツのためになるんだ」
「・・・」
「あとはアイツ自身がどうするかだ。俺たちにはどうすることもできないんだよ」
「分かった・・」
「それよりも、久しぶりにオレのオンボロの家に来ないか? 話したいことがあるんだ。お前もあるだろう?」
「あぁ。俺は大三郎に話したいことがたくさんある。
本当は地区予選を勝ちぬいて、全国大会でお前と話すつもりだったんだ。
もちろん試合でお前に勝った後にさ。でも、もういまは叶わぬ夢になっちまったから・・」
「そうか・・。タクシーで近くまで行こう」
金太は柔道着姿のまま、一緒に権藤の家に向かった。
・
・
久しぶりに戻った青空町の権藤の家。
一年前まで、権藤が1人で生活をしていたが、いまは権藤の正式な家ではない。
権藤の母親がたまに来る程度で、ほとんど使われていないのだという。
家の中に入ると、相変わらず人の温もりは全く感じられず、初秋なのになぜかひんやりとしている。
金太は思い出していた。
この家には、2人だけの思い出がたくさんある。
初めてこの家にきたとき、権藤にリョウジョクされて、拳一が助けに来てくれた。
権藤が東京に引っ越す前に、権藤が初めて「好きだ」と気持ちを告白した。
その後、一日だけ心を許して、キスをして、体を合わせた。
一瞬だけど、権藤と自分の心が1つになった。
いろいろな思い出がある家だ。
部屋に入ると、金太はゆっくりと周りを見渡した。
以前は机に教科書が乱雑に並べてあったが、いまは布団と机が置かれているだけで、前よりもさらに広く感じられた。
しかし、ほとんど変わらぬ雰囲気に、なぜか安堵する。
なにもない部屋なのに、この部屋はたくさんの思い出がつまっているのだから。
感傷に浸る金太に、権藤がおもむろに口を開いた。
「キンタ、ゆっくりしてくれよ。お茶でもいれるか?」
「あぁ、頼むよ・・」
「それから柔道着は干してやるから、とりあえず脱げよ」
「うん・・」
権藤の優しい言葉に、金太は自然と表情が柔らかくなった。
金太は立ち上がって、上の柔道着を脱ぐ。
そして、帯を外して下の道着をスルスルッと脱いでブリーフ一枚の格好になった。
(ふぅ・・)
金太が額の汗を拭って、座ろうとした瞬間。
突然、背中にゾクッとする肌の密着感を感じた。
驚いて振り向くと、そこにはブリーフ一枚になった権藤の姿。
「なっ・・!」
「懐かしいだろ?」
こともあろうに、後ろからブリーフ一枚の権藤が抱きついていたのだ。
金太は振り向きざまに、声を荒げる。
「ちょ、ちょっと待て!」
「俺とお前は、この格好が一番いい」
「大三郎、俺はまだ心の準備が・・」
「心の準備? もうエッチしたいのか?」
「それはその・・。まだ何も話してないじゃないか」
「いいからキンタ、ゆっくりと体をこっちを向けるんだ」
「ど、どうして・・?」
「振り向けば分かるさ」
「う・・うん・」
権藤は後ろから抱きついた腕を、そっと解放する。
そして金太の両肩をしっかりと掴み、金太の体を180°回転させた。
パンツ一枚で向かい合う、金太と権藤。
すでに金太は頬を赤く染め、視線を横にずらしていた。
権藤は、金太の両肩に置いた手を、ゆっくりと背中に回した。
「キンタ、少しだけでいい。俺のわがままを聞いてくれ」
そう呟いた権藤は、金太の体をギュッと抱きしめた。
「あっ・・ああっ・・・」
「キンタ・・」
権藤の大きな胸板とお腹の肉が、ピッタリと金太の肌に触れる。
あまりに急な展開に、金太は顔を真っ赤にして、うつむいた。
心臓がドキドキとして、体が震える。
権藤とは何度も体を合わせているのに、なぜか今日はとても恥ずかしかった。
権藤と体を密着させるたびに、金太の心から恥ずかしさが徐々に消えていった。
やがて、それは気持ちよさへと変わっていた。
とても暖かい。
ただ、肌と肌をあわせただけなのに・・。
「大三郎・・・」
「また悪い癖がでちまった。俺は変わらないな。すまねぇ・・」
「いつも強引すぎるよ・・」
金太の言葉に、権藤は照れくさそうにヘヘッと笑う。
そして、金太に向かって、真面目な声で話しかけた。
「今日の試合のことだけどよ。
負けて悔しいんだろう。泣きたいんだろ? すべてを1人で背負うな。
お前の苦しみの半分でもいい。俺に分けてくれ。俺はいつでも受け止めてやるから」
「そんなこと言われても・・俺は別に苦しくなんか・・」
ウジウジとした金太の態度に、権藤は尋ねてきた。
「今日の試合、お前はいつもの実力の半分も出せていなかった。
お前が、南条隼人のことで随分と苦しんだことは、すぐに分かったさ。
お前は試合をする前から、もう負けていた。
心はあらゆるプレッシャーと緊張で締め付けられ、呼吸が乱れて体力も底をついていた」
「どうして分かるんだよ・・?」
「お前は誰よりも優しくて、男気があるからさ。
昨日、俺に電話したときに分かったんだ。
南条隼人のことを放っておけなかったんだろう? だいたい察しはつくさ。
大切な試合に集中しなければならなかったのに、お前は南条を守った。
その結果が、あのブザマな試合だ。試合をする体力も尽き、精神的にも疲労困憊だった。勝てるわけがない」
「・・・」
「でも、それがお前の美徳なんだ。試合では負けたけど、お前はやるべきことをやったんだ。
もし、南条隼人を守らない男であれば、それは俺が知っているキンタじゃない。だからそれでいいんだ」
「大三郎・・・」
「ただ1つだけ気になったことがあるんだ。お前は柔道の試合中に俺のことをチラッと見ただろう?
なにを気にしていた? どうして試合に集中せずに俺のことを考えた?」
「それは・・」
「全部吐き出してみろ!」
「・・・・」
「さぁ、言うんだ!」
「分かったよ・・」
金太は権藤とは目を合わさずに、呟いた。
「俺は・・俺は全国大会に行きたかった。そして大三郎と戦いたかった」
「・・・」
「だから大三郎に俺の強さを見て欲しかった。大三郎に笑われたくなかった」
金太が自分の気持ちを素直に語ってくれたことに、権藤は力いっぱいうなづいた。
そのまま目を閉じて、金太の上半身をさらにギュッと抱きしめた。
「大三郎・・痛いよ・・」
「俺はキンタが予選で負けて悔しい。お前がいない全国大会なんて、うれしくもなんともねぇ。
俺もキンタと戦いたかったんだ。キンタと柔道をして、また勝負をしたかったんだ。柔道の勝負さ。
お前が泣きたいのと同じくらい、俺だって泣きたい気持ちさ。
キンタのバカヤロウ! 俺の気持ちを踏みにじりやがって!
こうして、お前のことを抱いたまま、潰してやりたい気分だ」
その言葉に、金太はいままで抑えていた感情が溢れていた。
「俺だって・・ううっ・・俺が一番悔しいんだよ・・お前に分かってたまるか!」
「あぁ、分かんねーよ! だから分かるように全部俺に言って見ろよ!」
「俺は負けて悔しい。俺は大三郎以外の誰にも負けるつもりはなかった。
絶対に負けないと思っていた。それがこんな結果になって・・うっ・・うっ・・ちくしょう・・」
「キンタ、泣きたいのなら泣けよ。
男は涙を見せないのがお前の信条かもしれないが、泣かなくちゃ先に進まないことだってある」
「ううっ・・・ぐっ・・」
金太の泣き方は、号泣というものではなかった。
必死に堪えて、肩ですすりなくという、金太らしい男泣きだった。
いままで心に溜まった悲しみを、少しずつ権藤の逞しい胸にぶつけていった。
「うっうっ・・俺・・大三郎・・」
「あぁ。聞いている」
「俺はもう自信がない・・俺はまだ大三郎のライバルか・・?」
「・・・」
「俺はもう、お前のライバルじゃなくなったのかもしれない。俺は毎日不安なんだ。
だって、お前はどんどん強くなって、俺だけが取り残されて・・。お前は強くなって、俺だけが弱くなって・・」
「そんなことを考えていたのか」
「くっ・・ううっ・・」
「俺のライバルはキンタだけだ。ずっと変わらない」
「どうして、そういい切れるんだよ・・」
「俺はお前の強さを知っているから。誰よりもキンタのことを理解しているつもりだから」
「くっ・・」
金太はしばらくの間、権藤の胸の中で泣き続けた。
権藤の胸は、金太にとって分厚くて硬くて汗臭さかった。
でもそれでいて、暖かかった。
少しずつ嫌なことを忘れさせてくれた。
権藤の胸で泣いていると、心臓の音が聴こえる。
ドキッ・・ドキッ・・。
すごい音を立てて、脈動している。
もしかして、権藤も緊張しているのかと、金太は一瞬思った。
権藤の心臓の音を聞いているうちに、金太はなぜかホッと暖かい気持ちになった。
すべての苦しみを吐き出したとはいえないが、重圧から解放されたような気分になったのだ。
権藤大三郎の暖かさが、力を与えてくれたのかもしれない。
そう考えたとき、金太は自分には権藤大三郎という存在が必要なんだと感じた。
権藤の胸の中で泣き続けた金太は、ようやく胸から離れた。
そして、ジッと権藤の目を見つめる。
金太は自然と目を瞑り、唇を権藤にゆだねていた。
権藤も目を閉じて、金太の唇に自分の唇を近づけてそのまま唇を重ねた。
(はむっ・・)
唇が触れる湿った音。
権藤の舌は、すぐに金太の舌を求めて、唇をこじ開けていく。
金太もそれを受け入れて、舌と舌が絡み合う。
(大三郎・・はむっ・・んあっ・)
(キンタ、もっと・・!)
権藤の舌が、金太の舌に絡み、甘い唾液が口の中に広がっていく。
溶けるような舌の感触が、金太の体を突き抜ける。
その感触に、金太の心臓は高鳴り、身悶えした。
いつのまにか、権藤はキスをしたのまま金太を布団に押し倒していた。
(んっ、はむっ・・)
(ああっ・・)
しばらくして唇と唇が離れる。
金太がゆっくりと目をあけると、自分のお腹の上に権藤がまたがっていた。
金太が下で、権藤が上。
いつもの体勢。
権藤は金太の両手首を、布団に食い込むように、しっかりと押さえつけていた。
「キンタ・・どうしてキスをした? どうして俺を求めた?」
「・・・・」
「いまどんな気持ちだ?」
「すごい気持ちいいよ・・体中が熱くなって・・」
「俺だって同じさ。キンタと心が1つになれて、いまは心臓が破裂しそうだ」
「心が1つに・・」
「以前の俺は、お前に告白することだけで精一杯だった。
でも、いまは違うんだ。お前のことを大切にしたいと心から想っているんだ。ただそれだけなんだ」
「俺のことを大切に・・?」
「俺は、キンタが振り向いてくれなくても構わない。
だって、俺は自分なりに影からキンタを支えられる方法が分かったんだから」
権藤の言葉に、金太は満足な笑みを浮かべた。
「大三郎ってさ・・」
「どうしたんだ?」
「大三郎は変わったんだな。
なんていうか、以前よりずっと優しくなったよ。心も体も強くて大きくなった感じがするよ」
「そんなことはないさ」
権藤は金太の瞳を見つめながら、やんわりと話しかけた。
「なぁキンタ? 中学を卒業したら東京に来て、俺と一緒に柔道をやらないか?」
「大三郎と?」
「そうだ。俺と一緒に暮らしてみないか? 2人で支えあって生きてみないか?」
「・・・」
「俺とお前は一緒になれると思うんだ。なぜなら、お前も以前と変わったように見えるから。
以前のキンタは、ただ俺を拒絶するだけだった。でもいまは俺を見る目が優しいんだ。
俺たちが一緒になってすべてがうまく行くとは思わない。苦労だってあるさ。でも一緒にやらないか?
俺は答えを聞きたい。一年前の全国大会の日、答えてくれなかった返事を、いまここで聞きたいんだ」
その質問に、金太は言葉を詰まらせた。
お互いに瞳を見つめ、ただ静寂な時が流れるだけだった。
表情を曇らせた金太に対し、権藤は真剣な眼差しで聞き返す。
「キンタ、また答えてくれないのか?」
「・・・」
「キンタ!」
権藤の心の叫びに、金太はおもむろに口を開いた。
「俺は大三郎のことが好きだよ。
それに俺はお前の気持ちが分かったんだ。"男が男を愛する"って気持ちが、分かったんだ。
だって俺はこの一年間、ずっと大三郎と柔道をしたかったんだ。大三郎と柔道をして、体を合わせたかった。
お前が4年間、ずっと俺を求めていたのと同じように、俺も1年間、ずっとお前を求めていたんだから」
「本当なのか・・?」
「あぁ。俺は何度も大三郎に手紙を書こうとした。だけど、怖くて書けなかった。
大三郎に会いたくて、体を合わせたいと思っている自分を認めたくなかったのかもしれない。
ごめんよ・・半年も手紙を出せなくてさ」
「かまわないさ。でもうれしい。俺はいま心の底からうれしいよ。
キンタが俺の気持ちを理解してくれて、俺のことを好きになってくれたことに。
高校に進学したら、俺と暮らそう。毎日、俺と柔道をしよう。もう拒絶する理由はないはずだ」
「うん・・でも・・」
「まだなにか不満があるのか?」
「俺にはやっぱり分からないんだ。
男同士が愛するって、やっぱりどこかおかしいと思うんだ」
「・・・」
金太は権藤に向かって、真剣に尋ねた。
「俺には分からない。
男同士の恋愛の先に一体なにがあるんだ? 体を合わせたその先になにがあるってんだ!?」
「キンタ・・」
権藤は、金太の腕を押さえつけていた両手をゆっくりと解放した。
そして、自分の顔を、金太の顔と数センチの距離になるまで近づける。
「大三郎、またキスするのか・・。それでごまかすのか・・?」
「違うよ」
「なら、答えてくれるか・・?」
権藤は、ふぅと大きく息をついた。
「なぁ、キンタ。お前は昔から自分が納得しないとテコでも動かない性格だったよな。
自分がこうと決めたら、それを最後までやり通す、律儀で融通の利かない性格だ。
だから、お前がいま心の中でモヤモヤしているものを、俺が吹き飛ばしてやる」
「大三郎・・」
「俺にとって、キンタは一生の柔道のライバルであり、俺にとってかけがえのない人間なんだ。
簡単に言えば、キンタは俺のすべてさ。だから俺は男同士の恋愛の先になにがあるのかなんて、考えていない。
考える必要なんてないんだ。キンタがいてくれれば、それだけで俺のすべてが満たされるんだから。
俺はキンタを愛している。お前も俺のことが好きなんだろう。だったらそれで十分なはずなんだ。
・
・
でもな。お前が思っていることはそんなことじゃないだろう?
男同士じゃ、手をつないで歩けないし、街中でイチャつくことだってできないさ。
もっと先のことをいえば、結婚はできないし、子供も生まれないし、祝福だってされない。
世間や家族から冷たい目で見られるだろう。
お前が漠然と不安に思っていることは、たぶんそういうことだろう? 違うか?」
「うん・・」
「じゃ、逆に質問するぜ。男と女が結婚する理由はなんだ?」
「それは・・子供を作って、家族を作って・・」
「なんのために? 寂しいからか?」
「それもあるけど、たぶん幸せになりたいから・・」
「あぁ。誰でも幸せになりたいに決まってる。
でも、それ以上に結婚する理由があると思うんだ」
「どういう意味だよ?」
「人間はなにかを残したいと考えていると思うんだ。自分が生きた証を残したいんだよ。
でも、ほとんどの人間は自分が生きた証なんて、残すことは出来ない。
一部の天才的な発明家や芸術家は残せるかもしれないが、ほんの一握りの人間さ。
だから、子供を作る。自分の遺伝子を継いだ子供を作って、自分が生きた証を作るんだ。
つまり、自分の子供に自分の意思を託すんだ。
それを昔からずっと繰り返したきたんだ。だから、俺たちも生まれたんだ。
でも、俺とキンタじゃ、そんなことはできない。男同士なんだから。
だけど、俺とキンタでなければ、絶対に残せないものがこの世界にはあると思うんだ。
それがなんだか分かるか?」
権藤の問いかけに対し、金太はジッと権藤の瞳を見つめながら、考える。
そして呟いた。
「俺とお前で残せるもの・・・」
「あぁ」
「俺たち2人で残せるもの・・もしかして・・」
「柔道さ。俺とキンタの2人で、柔道の世界で永遠に名前を残そう。
柔道の世界は厳しいし、そんなに甘いもんじゃない。世界に名を残すなんて、そう簡単にはできない。
でも、俺とキンタの2人でならできる。1人じゃできないけど、2人で支えあえばできるはずだ。
だって、俺もキンタも柔道が大好きなんだから。そして、お互いのことを大切にできるんだから。
2人で切磋琢磨して、がんばろう。俺たちの未来を、俺たち自身で切り開いていこう」
「大三郎・・」
「これじゃ、ダメかい? 俺たちの進むべき道は間違っているか?」
「ううん」
「男同士の恋愛の先になにがあるのか、俺とお前で確かめよう」
そういうと、権藤は自分の言葉が恥ずかしかったのか、少し照れくさそうに微笑んだ。
金太は権藤の言葉に納得したような表情で、話しかけた。
「大三郎、ありがとう。俺はずっと心に引っ掛かっていたものが、やっと解けた気がする。
人生はたった一度しかない。いまこの瞬間だって、もう元には戻れない。時は過ぎてしまうんだから。
だから、俺は大三郎と一緒になって、人生を後戻りできないことが怖くて仕方なかった。
・
・
でも、俺は決めた。もう迷わないよ。たとえ戻れなくても後悔しない。
俺は、中学を卒業したら、東京に行くよ。そして大三郎と柔道をする。
だって、俺は大三郎のことが好きなんだから。
不安はたくさんあるけど、俺は権藤大三郎と一緒の道を歩いて見るよ。つらいことがあっても一緒に支え合おう。
そして俺は大三郎にも負けない柔道家になる。だから俺が大三郎を倒すまで、絶対に全国で負けるな」
「ああ。約束だ」
「本当に約束できるのか?」
「当たり前だろ。俺は負けない。だから約束を忘れないように、記念にエッチしようぜ」
「お前な・・」
「ヘヘッ・・」
・
・
権藤は金太のおちんちんの根元を握り、もう一方の手でスルスルと皮を剥く。
「はんあ、ああっ!」
「お前、皮剥いただけでそんなに気持ちいいのか?」
「だって・・んあっ」
権藤の目の前に、金太の勃起したおちんちん。
全く恥垢が付着していない清潔感のある亀頭。
「金太のチンチンは、いつみても清潔にしてあるな。俺のために洗っているんだな?」
「そんなわけないだろ」
「ヘヘッ。じゃあ、しゃぶるぜ」
(しゃぶる・・!)
金太は歯を食いしばって、おちんちんに力をいれる。
権藤はそんな律儀な金太の姿勢を見て、思わずプッと笑いそうになる。
「おいおい、あんまり緊張するなよ。でもそれがキンタの可愛いところだけどな」
「バカヤロ・・」
「すぐに逝くなよ。せっかくの愛らしいチンチンがもったいないぜ」
「そ、そんなことあるもんか・・」
「だって、もうガマン汁が垂れてるしな。
でも、キンタの亀頭は透き通るようにピンク色で、なにより形がしゃぶりやすいし、
愛らしいんだ。だから俺が夢中でしゃぶっているうちに、お前はあっという間に頂点に逝っちまうからな」
「バ、バカにすんな! 簡単に逝くもんか」
「行くぜ!」
「うっ!」
金太の桃のような亀頭を、一気にくわえ込む。
その途端、金太は全身を震わさせ、腰を浮かせて悶え始める。
「うわあっ!はっ、大三郎、やっぱり・・気持ちいい・・んあ!」
権藤は亀頭から甘味を吸い取るかのように、チュパチュパと音を立ててねぶっていく。
「はんあっ、あぎゃっ、うひゃあ!」
金太が仰け反る。
何度も亀頭を愛撫されれば、刺激に慣れそうなものだが、権藤の湿った舌の感触は金太にとっては特別なのだろう。
「ひやああっ」
「おい、あまり暴れるなよ」
「だ、だって・・そこは感じちまう!」
「くくっ、キンタはいつまで経ってもウブなんだから」
腰を浮かせる金太を、権藤はしっかりと体重を乗せて固定する。
権藤は尿道をチロチロと舐めたり、裏筋をリズミカルに変化させて舐めたりして、愛撫していく。
「うっ! はんあっ、あやっ!」
「このへんもキンタの性感帯だよな」
今度はまだ毛が生え揃っていない玉袋を、舐め、口に含み、吸い尽くす。
「うひゃあ、くあっ、頭が真っ白に・・ああっ!」
「ハハハ、お前の喘ぎ声は本当にいい」
「バ、バカなこというな・・うひゃひゃあ!」
「じゃ、今度は別の場所だぜ!」
権藤は金太の股をしっかりと広げ、Vの字に足を持ち上げる。
「この粘膜が快感になるんだぜ」
人差し指に唾液をたっぷりと含ませて、お尻の穴に突っ込む。
「んっ・・!? あひっ! ぎゃあああ!」
「ヘヘヘッ。舐めてやるよ。俺の愛を受け取ってくれ」
権藤は股ぐらに顔を突っ込み、お尻の穴をチロチロと舐めたり、唇を出し入れして、ソフトに刺激していく。
「はんああ〜っ!」
全身を悶えさせて、狂ってしまいそうな声を張り上げる金太。
「おいおい、ものすごい感じてるな」
「んあああ、頭が・・ふああっ、おかしくなっちまう!」
「俺もガマンできねぇ!」
権藤は自分のブリーフをバッと脱ぎ捨てる。
体を反転させて、自分の大きなモノを、上から金太の口に押し込む。
「ぶはあああっ、お前、やめっ、おぐっ!」
「たっぷり俺のも舐めてくれよ。俺だって逝きたいんだぜ!」
「ぶぉーし(よーし)」
「お互いに舐めっこしようぜ。先に逝ったらケツに突っ込んでやらねーぞ!」
「そ、そんなのムリだろ! んぎゃあ、出ちまうっ!」
2人の喘ぎ声は、夜まで続いた。
・
・
夜の電車のプラットホーム。
すでに東京行きの電車が到着し、発車時刻が来るのを待っていた。
権藤大三郎と白金太郎は、片開きの電車の乗車口で、お互いしっかりと手を握り合った。
「大三郎・・これでまた、しばらく会えなくなるな・・」
「キンタが手紙をくれれば問題ないさ」
「俺、寂しいよ・・。大三郎がいてくれたらいいのに。春風中に大三郎がいてくれたら、俺は・・」
「キンタ・・」
金太は真っ赤になった目で、権藤を見つめた。
「キンタ、そんな目で見るなよ。俺も悲しくなるじゃないか」
「だって・・」
「俺はいま、とても心が穏やかなんだ。どうしてだか分かるか?」
「・・・」
「だって、キンタが俺のことを好きだと分かったから。俺と将来を誓い合ってくれたから。
だから俺は何の迷いもない。これからまっすぐに柔道に打ち込むつもりだ。もちろん、お前のことを毎日考えながらな」
「大三郎、分かった。手紙書くよ。電話もするよ。俺、大三郎のことが・・好きだから」
「ありがとう。うれしい・・俺も・・」
その場で2人はゆっくりと手を取り合う。
そして、唇を合わせようとした2人だが、周りの視線に気がつく。
2人で一緒に下を向いて、ポッと赤くなった。
無言になった2人の間を切り裂くように、発車する音がジリジリ鳴り響く。
金太は慌てるように、話しかけた。
「大三郎、中学を卒業するまで、待っていてくれ」
「あぁ。東京で待ってるぜ」
「俺はまだ中学でやり残したことがあるからさ。それをきちんと片付けてから、東京に行くつもりだ」
「やり残したこと? 全国制覇か?」
「それもある。だけど、俺にはもう1人、放っておけない後輩がいるんだよ」
金太の切実な口調に、権藤はふっとため息をついて返事をした。
「そうか・・。アイツはまるで昔の俺と同じだ。
いまは真っ暗で、イバラのように険しい道を進んでいる。だがアイツ自身が解決するしかないと思う」
「でも、俺は力になりたいんだよ」
「・・お前らしい答えだな。お前は困っているヤツは放っておけない性格だからさ。
それが白金太郎の生き方ならば、お前なりに男同士の恋愛に答えを見つけてみろ」
「あぁ。俺は俺なりにアイツのための答えを見つけて見せる」
「分かった。がんばれ、キンタ」
金太は、手を振って電車が見えなくなるまで、見送っていた。
そして、ゆっくりと家路についた。
いまだ自分の進むべき道を見つけられない、もう1人の後輩のことを考えながら。
最後まで読んでいただいた方、ありがとうございました。
この小説は前回に書いた「太一くん小説」と対比したコンセプトで書きました。「太一くん小説」は太一と大二郎が同性愛を理解できる関係で、日常で同性愛を何事もなく受け入れる世界、巷で言うボーイズラヴ小説(BL)です。
BL小説はお決まりのパターンがあって、「大二郎が太一と出会いました。大二郎は太一が好きです。大二郎が思い切って告白したら、太一も偶然にホモで大二郎が好きでした。そして幸せになりました」というものです。BLを理解できる人には受け入れやすい小説だと思います。
しかし、「金太君小説5」の世界は、同性愛が背徳的なものであるという原則で作られています。だから金太は同性愛を拒絶しつづけます。南条隼人は最終的に行き場を失います。
筆者は、男同士の恋愛を一般社会において、論理的に肯定する小説をチャレンジングに書きたかったのですが、突っ込めば突っ込むほど、「同性愛を異性愛以上に肯定できる要素はない」という結論に達してしまいます。南条隼人はその現実に直面するキャラクターで、同性愛者の方は、彼に共感したり、まるで昔の自分を見ているようで嫌悪感すら覚えたかもしれません(南条君ファンのかた、ゴメンナサイ)。
一方で金太と権藤大三郎は男同士の恋愛に希望を見つけますが、彼らの答えはあくまで筆者の机上の空論です。男同士の恋愛に関しては、読者の方1人1人が答えを持っているかもしれないし、まだ出せていないかもしれません。
もし「男と男が愛することのほうがすばらしい」という説得力をもった先人の小説があれば、ぜひ読んでみたいです。