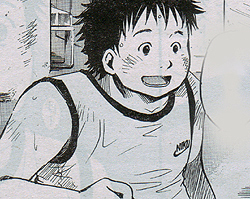 亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。
亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。
太一と大塚の関係は・・?
登場人物
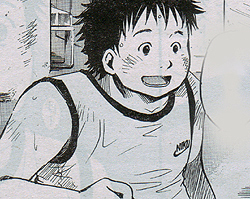 亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。
亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。
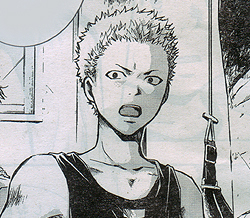 大塚。同年のプロボクサー。気性が激しく人付き合いが下手。太一ともうまくいっていない。
大塚。同年のプロボクサー。気性が激しく人付き合いが下手。太一ともうまくいっていない。
──次の日。
大塚が学校から帰ろうとすると、聞き覚えのある声に呼び止められた。
「ったく・・。てめーか、山下」
振り向きざまにガンを飛ばす大塚に対し、山下は「けけっ」と笑いをこぼした。
「もうお前とはケンカしないことに決めたぜ。いちおう礼を言うからな」
不審に思った大塚は、聞き返した。
「はぁ? 礼を言われる覚えはねぇ」
「お前がパシリでよこしたんだろ? 亀山太一くん、とっても素直でカワイイ子だったぜ」
「亀山だ? なんであのブタのことを知ってるんだ?」
「ボクシングの後輩なんだろ? でもこれからは俺のモンだ。お前から奪ってやった」
「何を訳の分からねーこと言ってやがる」
「ヘヘッ」
ニタニタと薄気味の悪い笑みを浮かべる山下に対し、大塚はハッとする。
「てめー、なにしやがった!?」
「さぁね、太一くんによろしく」
そういうと、山下はスタスタと歩いていってしまった。
一方、太一は学校が終わり家路に着いていた。
(痛てて・・。お尻の穴がズキズキする。困ったなぁ。
でも今日はボクシングジムはお休みだし、家でゲームでもするかなぁ)
しかし、昨日のエッチのことが頭から離れない。
そして別れ際の山下の言葉も・・。
<太一くんはずっと俺のモノだから。やりたくなったら、また気持ちよくしてあげるぜ!>
脳裏から、昨日の山下とのエッチが離れなかった。
おちんちんを舐められたときの快感、お尻を触られたときの高揚感。
(ボクは何を考えているんだ。早く忘れなくっちゃ。
山下さんはもう大塚くんに手を出さないって約束してくれたし、全部解決したんだ。
でも、なぜかスッキリしない。ボクは本当に良いことをしたんだろうか・・?
・・・・。
男と男がエッチするなんて、どう考えてもおかしいし、
こんなことで解決して、大塚くんは喜んでくれるんだろうか。
それにあのときのことを思い出すと、変な気持ちになっちゃう・・。
相手は男なのに・・ボクはおかしいのかな・・)
ふぅとため息をついて、歩き出そうとした瞬間。
「亀山!」
怒鳴るような声に、太一はビクリとして振り向く。
そこには大塚の姿があった。
「大塚くん!? こんなところでどうしたの?」
「亀山、俺と一緒にジムまで来い」
「今日はお休みなんじゃ・・それに大塚くんはケガしてるでしょ?」
「うるせー、いいから来い!」
大塚は髪の毛が逆立つような雰囲気で、もし逆らったら殴られそうだ。
あっという間に腕を掴まれ、太一は無理やりにジムに連れて行かされた。
休みの日のジムは物静かで、2人だけの室内は閑散として寒さを感じた。
いつもとは違う大塚の雰囲気に太一は緊張して、ゴクリと唾を飲み込む。
「あの・・大塚くん、今日は休みなのにどうしたの?」
「亀山、もう一度俺と試合をしろ」
「えっ?」
「俺はお前を許さない。だから試合で決着をつけてやる」
大塚の言うことがさっぱり分からず、太一は困ったように頬をかいた。
「大塚くん、あの・・その・・許さないって・・?」
「てめぇの心に聞いてみろ! さぁ早く着替えてヘッドギアつけな」
「ボクの心・・・」
「てめぇだけはタコ殴りにしないと気が済まねぇんだ!」
大塚の恐ろしいほどの剣幕に、太一はビビりながら、いつものシャツと短パンに着替えてヘッドギアをつける。
すでにリングの上では、大塚が左手に包帯をしたまま、右手にグローブをはめていた。
(大塚くん、ボクを許さないって・・。まさか昨日のことで・・)
太一は心のなかがざわざわとしたが、仕方なくリングにあがった。
「行くぜ、亀山!」
まだコーナーでグスグスとしている太一に、いきなり大塚が殴りかかる。
「ちょ、ちょっと待って!」
「うるせぇ!もう試合は始まってるんだ。タコ殴りにしてやる!」
「大塚くん!?」
秒殺する勢いで、右ジャブを繰り出す大塚。
太一はグローブを顔の前に突き出して、ガードするのが精一杯だ。
大塚はプロテストに合格しただけあって、右手一本で簡単に太一のガードを崩しにかかる。
「これでどうだ!」
ほんの少しガードが開いたところを、必殺のアッパーカットが炸裂した。
太一は何もできずに、マットに仰向けに倒される。まさに秒殺だ。
しばらく頭がグラグラした太一だが、ようやく起き上がった。
「ハァハァ・・大塚くん・・」
「これくらいで勝負がついちゃ、気が済まねぇんだよ。早く構えろ」
ムキになる大塚に違和感を覚える太一。
(いつもの大塚くんらしくない・・。なにをムキになっているんだ・・)

その後も大塚は右手一本で、太一の顔面を左右から流れるようなパンチで攻め続けた。
太一は高度な技術に対応できず、体を丸めて防戦一方だ。
「このメタボな腹が気に食わねぇんだよ!」
大塚はガードががら空きになった太一のボディに、強烈なストレートを放つ。
まるで腹の脂肪を突き抜けて、背中まで貫通しそうな強烈なパンチだった。
「げはっ!」
太一はその場で腹を抱えてうずくまり、がはっと胃液を吐き出す。
「ほら、立てよ!」
「がはっ、ぐぐっ・・」
大塚は太一の様子を見ていたが、太一はなかなか立つことができない。
相当にボディへの攻撃が堪えているらしい。
しばらくして立ち上がった太一に、ふて腐れたような声で話しかけた。
「やっぱりてめーはボクシングに向いてねーぜ!」
「はぁはぁ・・・大塚くん、一体どういうつもり・・?」
「お前こそ、何様のつもりだ。山下に会ったんだろ?」
「・・・」
「人のことを心配してる暇があったら、てめーが痩せろよ!」
「だって、大塚くんのことが心配で・・」
「山下と何を約束したのかは知らねーが、てめーは山下の言いなりになったんだろ?
そんなお人好しで意思が弱い人間は、ボクシングの世界で通用しねぇ。やめちまえ!!」
「大塚くん、違うよ・・ボクは・・」
「違わねーよ。てめーが俺のために何かしても、俺は感謝したくもねーし、嬉しくもねぇ」
「うっ・・ご、ごめん・・」
「謝るってことは、本当は悪いことをしたと思ってんだろ?」
「ボクは昨日、山下さんの言われるままに・・ごめんなさい・・ううっ・・」
太一は両手で顔を覆って、しばらく声を押さえて泣いた。
大塚のためとはいえ、昨日してしまった汚らわしい行為に、心のどこかで罪悪を感じていた。
そしてその行為は、大塚のプライドも傷つけてしまったのだ。
だから余計に虚しい気持ちになった。
しばらく涙にくれた後、太一は目元を真っ赤にして口を開いた。
「ごめんね、大塚くん」
「いつまで泣いてるんだよ」
「うん・・大丈夫。もう泣かないから」
「ったく・・そういうところがうぜぇんだよ」
大塚はフッとため息をついて、プイッと横を向いてふて腐れた。
それは、いつもの大塚の表情で、先ほどまでの怒っている顔とは違う。
太一はその顔を見て、なぜかホッとして落ち着く感じがした。
太一はゴシゴシと涙を拭って、真剣な表情で大塚に語り始めた。
「ねぇ、大塚くん?」
「・・なんだよ」
「少し話をしたいんだ。いいかな?」
「長い話はゴメンだぜ」
「うん・・。ボクは昨日、北高に行った。どうして大塚くんがケガをしたのか知りたかったから」
「それが余計なお世話なんだよ」
「うん。分かってるよ」
太一は先ほどよりもやさしい顔をして、率直に尋ねた。
「大塚くんはどうして友達を作ろうとしないの? みんな怖がっていたよ。
いつも怖い顔してちゃ、誰も近寄ってこないよ。友達もできないじゃないか・・」
「・・・。お前には関係ないだろ」
「大塚くんは友達がいなくて寂しくないの?」
「俺は群れるのは好きじゃねぇ。ボクシングがあれば友達はいらねぇんだ!」
ガンを飛ばすような大塚の鋭い目に対し、太一も真剣な眼差しで切り返す。
「ボクも学校でひとりぼっちだよ。クラスから『メタボでウザい』って言われて、
みんなから無視されているし、誰も話しかけてくれない。
お昼はひとりで食べるんだ。自分の机で誰とも話さず・・もう慣れたケドね・・。
体育の授業はずっと憂鬱だったし、学校に行くのも嫌だった」
「俺は学校は嫌じゃないぜ。まぁ、好きでもないけどな」
「うん。大塚くんは強いから・・。ボクは弱いもん。
でもね、いまは楽しいんだ。友達がひとりもいなくても、学校は嫌じゃなくなったんだ」
「それがどうした?」
「ボクシングに出会って、ずっと思っていた。
ボクシングをしていれば、友達はいらないのかなって・・・。
だって、ボクシングの練習をしていると、時間はあっという間に経つし、
練習は楽しいことだけじゃなくて、苦しいし、痛いし、何より強くなるためには自分と戦わなくちやいけない。
ボクシングに出会ったときは本当に夢中で、他に考えている余裕がなくって・・。そう思っていた」
「・・・。何が言いたいんだよ」
「ねぇ大塚くん? 大塚くんはずっと1人でボクシングをやってきたの?」
「当たり前だろ。俺はずっと1人だ。これからも1人でやっていくさ」
「違うよ・・。大塚くんは1人じゃない。たくさん仲間がいるじゃないか・・」
「なに!?」
大塚は太一に反論しようとしたが、なぜか言葉に詰まった。
それは、大塚がいままで友達や仲間のことなど、真剣に考えたことがなかったから。
そして、それ以前に話す相手がいなかったし、きっかけもなかったし、触れようとも思わなかったからだ。
「・・・いちいちうるせぇんだよ、てめーに俺の何が分かるってんだ!?」
すると太一は柔らかい表情をしながら、返事をした。
「ボクね、大塚くんと知り合ってまだ2ケ月しか経っていないけど、
なんとなく大塚くんの気持ちが分かるんだ。間違っているかもしれないけど、でも・・」
「分かるだと?」
「だってこのジムはさ、蔵田さんや市村さん、巌根(いわね)会長・・。
すっごくやさしい先輩や仲間がたくさんいて、大塚くんは中学のときからここに居たんでしょ?
だから、ボクは大塚くんの気持ちがなんとなく分かる。
学校に友達がいなくても、充実しているんだ。
ここには拳を合わせるだけで、心を通い合わせることができる仲間がたくさんいるんだもん」
「亀山・・」
大塚は思った。
語りかける太一の顔は、ボコボコに殴られた後なのに、とても幸せそうに見えた。
さきほどまで泣いていたとは思えないほど。
太一の表情を見つめているだけで、なぜか大塚も心が温かくなるのを感じた。
「ボクは大塚くんがうらやましい」
「お、俺のことが・・?」
「ボクももっと早くボクシングを始めていればよかった。
そうすれば大塚くんと一緒にボクシングが上達できたのに・・。
もう大塚くんと実力の差がありすぎて、ボクは殴られるだけで大塚くんの練習相手にもならない。
ボクはそれがすごい悔しい・・」
「お前・・」
「ボクは大塚くんと同い年なのに、練習の相手にもなれない。
蔵田さんやみんなの貴重な時間を割いてもらっているのに、ボクはみんなのために何も出来ない。
ボクはそれが嫌だった。どんなことでもいいから、みんなのためになりたくて・・。
だから大塚くんのために何かをしたくて、それで・・ボクは昨日・・・ごめんなさい・・」
太一は体を震わせて、必死に泣くのを堪えていた。
しかし、スッと頬に雫が流れる。
「ごめんね・・また泣いちゃった・・」
しかし、大塚にはその涙は先ほどのものとは違い、
太一の気持ちが詰まった、純粋で大切なものに見えた。
大塚はしばらく下を向いて黙ったままだった。
太一のグズッ、グズッという涙を堪えれる音だけが、周りを支配していた。
・・・。
長い静粛をやぶって、大塚が口を開いた。
少し気まずそうに、斜め下に視線をそらせながら。
「亀山・・俺はお前のことが好きなのか、嫌いなのか分からなかった。
デブでメタボで運動オンチで、ボクシングに絶対向いていない性格なのに、
蔵田さんたちはどうしてお前のことを面倒みているのか、分からなかった。
だからその・・なんかムカついて、お前のことを無視して、嫌いになろうとしていたのかもしれない」
「大塚くん・・」
大塚はうつむき加減のまま、話を続ける。
「だけど、蔵田さんがお前にボクシングを教える理由が、いまやっと分かった。
その・・なんかうまくいえねーんだけど・・。
・・・。
俺さ、初めてこのジムに来たときのことを思い出したんだ。
まだ中学2年生で、ジムの人が全員大人に見えて、いきがっていたけど内心は震えていて・・。
そのときに3つ年上の先輩が、俺に手取り足取り教えてくれた。
ロープの飛び方、構え方、そしてミット打ち。
全部楽しかった。俺はいつの間にかボクシングのことだけを考えるようになった。
いまじゃ、プロのライセンスまで取ってさ。
でも・・・俺、プロのライセンスじゃなくて、ずっと別に欲しいものがあったんだ」
大塚はふっと大きく息を吐いて、太一に向き直す。
そして太一の目をしっかりと見て、真面目に話し始めた。
「亀山がこのジムに来てから、俺はずっとお前のことが気になっていた。
お前と試合をした後はさらに気になって、練習中にお前のことを考えているときもあった。
自分でもどうしてか分からなくて、亀山太一という存在がなんなのか、分からなくて・・。
でも、さっきお前が俺のことを真面目に心配してくれたことが分かって、
だから、俺もきちんと話さなくちゃいけないって・・。
なんかうまく言えないけど・・」
「大塚くん・・」
太一は思った。
いままで決して心を開こうとしなかった大塚が、初めて自分に向き合って話をしている。
そんな大塚の気持ちが、太一の胸にグッと響いた。
だから、ますます涙が溢れそうになった。
大塚はしっかりとした声で言葉をつなげる。
「俺はこれからもボクシングを続ける。
だけど、これからは1人じゃなくて・・。俺と一緒に・・その・・がんばろうぜ・・・」
大塚は自分で言ったことが恥ずかしかったのか、そのままプイッと後ろを向いてしまった。
「大塚くん、いまなんて・・?」
「二度も言わせるな」
「ボクも・・大塚くんと・・ううっ・・」
太一は大塚に駆け寄り、後ろから自然に抱きついていた。
目から涙を流して、そして鼻水も垂らして。
「わ、バカ! 男同士で気持ち悪ぃじゃねーか! 鼻水つけんな!」
「ごめん、でもボク、とってもうれしくて・・うぐっ・・」
「デブがしがみつくな! 重くて疲れる。腕が痛い!痩せろ!」
「うん・・ごめん」
「お前ってホント、変なヤツ・・。けど嫌いじゃねーよ」
恥ずかしがりながら笑っている大塚の表情を見て、太一は心が自然と和んでいた。
きっと、これから長い付き合いになるであろう、"友達"を前にして。
・・・。
・・。
── 一方の北高の柔道部では・・。
<山下、この間のデブなカワイイ子はどうだったんだよ?>
その質問に山下はニンマリと笑みを返す。
「サイコーだったぜ。太一くんの味、太一くんの感触・・まだ手に残ってるぜ。
アイツはもう一度俺のところに戻ってくるさ。体が忘れないんだよ、俺とのエッチをな」
<お前、相変わらず手当たり次第なのな>
「いや、俺は太一くんにマジで惚れちまった。大塚なんかにはもったいないぜ」
<じゃあ、これからはあのデブと付き合うのかよ?>
「あぁ。お前らには太一くんのカワイらしさがわからねーんだよ。
ホラ、これ太一くんのブリーフ。帰りがけに奪っちまった。
しばらくはこれをおかずにさせてもらうぜ、太一くんの匂いだ。
待ってろよ、絶対に俺のものにしてやるからな」
そういうと、山下は不敵な笑みを浮かべていた。
最後まで読んでいただいた方、ありがとうございました。「もえタイ」小説の2本目でしたが、いかがでしたでしょうか? 前作はエロ少な目のほのぼの系でしたので、今回は思いっきり陵辱系にしてみました(^^; 大塚と絡めたかったのですが、書き終わったら大塚は最初と最後だけの登場になってしまい、もうちょっと突っ込んで2人の関係を書いてもよかったかなーと思いました。だから最後のほうはグタグタな感じで、あまり収拾が付いてなくてスミマセン。