 ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。
ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。
この物語は、アニメ三銃士の設定を元に書いたものです。映画「アラミスの冒険」の半年後くらいの設定です。ちなみにドS小説になる予定なのでw、ダメな方はご遠慮ください。
登場人物
 ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。
ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。
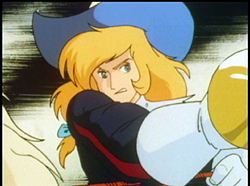 アラミス。ポルトスの親友で、剣術師範を務めるほどの腕前だが、女性であることを隠している。
アラミス。ポルトスの親友で、剣術師範を務めるほどの腕前だが、女性であることを隠している。
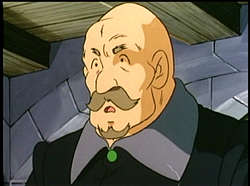 ベーズモー。シャトレの牢の看守で、囚人をいたぶる趣味を持つ凶悪な男色家。
ベーズモー。シャトレの牢の看守で、囚人をいたぶる趣味を持つ凶悪な男色家。
 ジュサック。三銃士と対立する護衛隊の隊長で、腹黒い男。男色家らしい?
ジュサック。三銃士と対立する護衛隊の隊長で、腹黒い男。男色家らしい?
「ぎゃああ!」
「この程度で悲鳴をあげているのか。つまらんヤツめ」
ローソクが灯す薄暗い牢の中で、1人の男が壁に手枷をはめられ、自由を奪われている。
「もう無理だ。この枷を外してくれ!」
「まだ愛撫もしておらんのだぞ。これからがお楽しみなのに」
「頼む、ベーズモー、放してくれ!」
「ケッ。"ベーズモー"と呼び捨てにしおって!」
そういうとスキンヘッドの男は、持っている皮のムチで、殴りつけた。
「うぎゃああ! やめろ!」
手枷をはめられた男は、身長が高くて肉付きがしっかりしている。
筋肉もなかなか隆々としており、囚人の中でも男らしい肉体を持っていた。
しかし、そんな男でも、ベーズモーの容赦ない鞭打ちの前に意識を失っていた。
「まったく・・・このフランスに、私を満足させられる男はおらんのか」
ふて腐れたように、ベーズモーはムチをポイッと投げ捨てる。
囚人に背を向けて、出口に向かって歩き始めた。
ベーズモーは、長年に渡り、フランスのシャトレの牢の看守をしている。
運ばれてくる囚人を毎日監視し、食事を与えるのが彼の仕事だった。
しかし、そんな仕事は当の昔に飽きていた。
ベーズモーの唯一の楽しみは、死刑の決まった囚人を地下牢に閉じ込め、
彼らに屈辱と恥辱を与え、打ちひしがれる姿を楽しむという卑劣極まりないものだった。
<囚人だから、何をしようと関係ない>
それがベーズモーの自分勝手な理屈だった。
どうせ死んでゆくのならば、自分の好みの男は、好きなように拷問する。
もし、拷問や陵辱している間に死んでしまっても、処刑する手間が省けるというものだ。
パリの治安を預かる警察隊には、獄中で自殺したと言えば、誰も気に留める者はいないのだ。
しかし、ベーズモーは最近、この狂ったゲームにすっかり飽きてしまっていた。
ベーズモーを満足させるような男が、いなくなってしまったのだ。
みな、ベーズモーの拷問と愛撫の前に、すぐに弱音を吐き、屈服してしまう。
『なんて根性のない囚人どもだ』
『処刑される前に、この俺様を楽しませてみろ』
それがベーズモーの言い分だった。
囚人を一方的になぶるという、非人道的な行為が許されるはずがない。
しかし、ベーズモーの感覚は麻痺していた。
いまのベーズモーは、麻薬中毒者のように、より屈強な男に飢えていた。
ベーズモーが地下牢から看守室に戻ると、そこには1人の狡猾な顔をした男が、酒を片手に待っていた。
男は十字架の模様のある赤い服を着ている。
「よう、ベーズモー」
ベーズモーは、その男にチラッと視線をやると、すぐにふて腐れた顔をした。
「なんだ。誰かと思えば、護衛隊長のジュサックか」
「"なんだ"はないだろう? 先日、俺が捕まえた男はどうした?」
「その男ならば、いま地下牢にいるぞ」
「ほう、お前も手が早いな。あの男はなかなかいいガタイをしていただろう?
俺も以前から目をつけていてな。お前が愛撫するのに飽きたら、俺にやらせてくれよ」
「フン、あの男のどこが屈強なんだ? 愛撫する前にギブアップしたわ」
「ギブアップ?」
「あの程度の拷問でギブアップする男など、陵辱する気にもなれん。
貴様は言ったな。『最近捕まえた罪人の中で、最も屈強な男だ』と。
貴様が捕まえられるのは、あの程度の力の男か。笑わせるな」
そういうと、ベーズモーは不満げに口を尖らせた。
ジュサックは、ベーズモーの投げやりな態度に、負けじと言い返す。
「お前の趣味のために、苦労して捕まえた囚人なんだぞ。その言い草はなんだ!」
「フン。あの男は私の趣味ではないわ。どうせお前が愛撫したかったのだろう?」
「そ、それは・・」
「護衛隊よりも、銃士隊のほうが、よほど強い男を捕えてくるぞ」
「なにぃぃ!」
ジュサックは、"銃士隊"という言葉を聞いて目尻を吊り上げる。
実は、ジュサック率いる護衛隊と、パリの銃士隊とは、犬猿の仲だ。
護衛隊はパリの宰相直属の部隊で、銃士隊は国王直属の部隊。
フランスの治安を守ることには変わりないのだが、なにかにつけてライバル心をむき出しにしている。
しかし、護衛隊は銃士隊とケンカをすると、必ず負けていた。
その原因は、銃士の中でも最強といわれる、アトス、アラミス、ポルトスの三銃士のせいだった。
三銃士は圧倒的な強さで、ジュッサックも手が出せなかった。
怒りで顔を震わせるジュサックを、ベーズモーはせせら笑う。
「ハハハ。先日も三銃士の1人、ポルトスが大きな囚人を抱えて運んできたぞ」
「三銃士・・ポルトスだと?」
 ←それらしい場面があったので入れてみました。
←それらしい場面があったので入れてみました。
「私の知る限り、いまこのフランスで、力ではポルトスの右に出る者はおるまい。
貴様はポルトスのツメの垢でも煎じて飲んだほうがいいな。ハーハハッ」
「くっ・・・」
ジュサックはしばらく地団駄を踏んで悔しがっていたが、
突然、なにかを思いついたのか、ふふ、と押し殺したような笑い方をした。
「おい、ベーズモー。お前、俺に吹っかけたつもりか?」
「なんのことかな?」
ベーズモーは、プイッと斜め上を向いて、とぼけたような顔をする。
「お前、やりたいんだろう?」
「言っている意味が分からんな」
「はっきり言ってやるよ。お前がいま一番愛撫したいのは、三銃士のポルトスだろう?」
「・・・」
ベーズモーはしばらく黙っていたが、やがて悪魔の笑みを浮かべてみせる。
「ジュサック、貴様は最近、鋭くなったじゃないか」
「分かるさ。俺も同じことを考えていたからな」
「ポルトスはよく囚人を連行して、このシャトレの牢にくるが、
あのムチムチした豊満な体を間近にみて、いつもうずいていたのだ」
いつのまにか、ベーズモーはご機嫌な調子で語りだしていた。
「あの男だけは別格だ。ポルトスをなんとかして私のものにしたいと、ずっと思っていたのだ」
「やはりそうか」
ベーズモーとジュサックは、珍しく意見が一致したのがおかしかったのか、お互いニヤッと笑みを浮かべた。
「ジュサックよ、ポルトスをなんとか捕まえられないだろうか?」
「あの巨漢だ。かなり難しいな。
ポルトスは三銃士と呼ばれるようになってから、一度も負けたことが無いのだから」
「なんとかならんのか?」
「フーム・・」
「もし、捕まえてくれたら、金をたっぷりやる。それに、貴様にも地下牢で、ポルトスを愛撫させてやる」
「ほ、本当だろうな!? では、1つだけ方法がないわけでもない」
その瞬間、ベーズモーの目が輝きだす。
「ジュサック、お前も隅に置けないな。きちんと考えているではないか。
それで、あの怪力無双のポルトスを、どうやって捕えるのだ?」
「たしかに、ポルトスの力は天下無双だが、頭は弱い。
まずはポルトスを誘い出す。誘い出して、罠にはめる。
そして、護衛隊でなぶってやるさ。いくらポルトスが十人力だといっても、護衛隊20人にはかなうまい」
「なるほど。しかし、護衛隊をそのような私事に使っても良いのか?」
「構わんさ。三銃士にはいつも痛い目に遭っていて、
特に喧嘩早いポルトスには、護衛隊の中にも恨みがあるものが、多いからな」
「そうかそうか。数で勝負となれば、いくらポルトスとて勝つことは難しいだろう。
よし、私からも1人応援をだそう。いま地下牢にハリツケにしている男だ。
私はアイツを金で雇う。あの男は剣が自慢のようだから、ポルトスといい勝負をするかもしれん。
それに、この仮面をつければ、ポルトスも萎縮して簡単には手をだせんかもしれん」
「ほう、その仮面は・・・フフ、おもしろそうじゃないか」
そういうと、ジュサックとベーズモーはガッチリと握手をする。
いつもは、仲が悪い2人だが、奇妙な連帯感で意気投合していた。
ジュサックは思い出したように、話す。
「それからベーズモー、1つ約束してくれないか」
「なんだ?」
「その・・俺が最初に・・ポルトスを愛撫させてくれないか」
なぜかジュサックは急に下を向いて、モジモジとしだす。
ジュサックが顔を真っ赤にする様子をみて、ベーズモーは思わず含み笑いがこぼした。
「クククッ。そうか、そういうことか」
「な、なんだ」
「ジュサック、貴様はポルトスに相当入れ込んでいるな? お前もずっとやりたかったんだろ?」
「べ、別にそんなことはない」
「そう恥ずかしがることではないぞ。私と貴様は同類なのだからな」
「チッ。お前なんかと一緒にするな。
予定が決まったら、追って連絡するからな」
そういうと、ジュサックはシャトレの牢から早々に立ち去った。
なんかストーリーが欲望丸出しw 一話目に主人公が登場しないなんて、いいのだろうか。