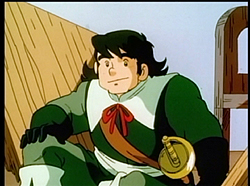 ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。
ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。
何気に初めてショタじゃない小説だったり・・。
登場人物
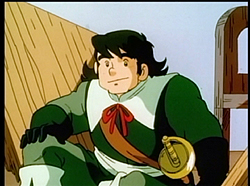 ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。
ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。
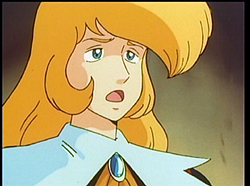 アラミス。三銃士きっての美形。剣術師範を務めるほどの腕前だが、女性であることを隠している。
アラミス。三銃士きっての美形。剣術師範を務めるほどの腕前だが、女性であることを隠している。
銃士隊とは、フランスの国王、ルイ13世を守るために集められた精鋭部隊。
その中でも、剣術の頂点と称せられる3人は、『パリの三銃士』として呼ばれていた。
──銃士隊の部屋。
国王の屋敷から、少し離れた閑静な場所にある。
2階建ての広い建物で、外には多くの馬が銃士の出立にそなえて世話されている。
「今日は運がいい。手札が絶好調だ」
「珍しいこともあるもんだな。なにか悪いものでも食べたんじゃないのか?」
いま部屋でポーカーをしているのは、三銃士の2人、アラミスとポルトスだった。

アラミスは金髪で細身でどことなく品格がある。
一方のポルトスは、銃士部屋が窮屈に思えるほどの巨漢で、どことなくのんびりしている。
「チッ、また負けた」
カードを机に投げ出し、アラミスが呟く。
「悪いな、アラミス。今日は負ける気がしない」
天を仰ぐアラミスを見て、ポルトスの声はとても穏やかだった。
「今日はどうなっているだ。ポルトス、本当に悪いものを食べたんじゃないのか?」
「おい、アラミス。それは言い過ぎってもんだ。食通の俺が、悪いものなんて食べるわけないだろう」
「食べることだけが、お前の取り柄だからな」
「食べることは生きることそのものだ。それが取り柄というならば、俺は人生を謳歌していることになるな」
「お前は、どんな苦難も謳歌して乗り切ってしまう気がするよ」
アラミスは、さんざん悪態をつきながらも、一瞬ポルトスに微笑みかける。
そして、机に放り投げられたカードを、手際よく集めて配りなおした。
アラミスはとても無口な男だった。
無口な上に、常にポーカーフェイスを保っており、何が起こっても動じることがない。
さらに、剣術指南役を務めるほどの、腕前をもっており、部下に対してはとても厳しい。
秘密主義でもあり、銃士隊の中でも近寄りがたい雰囲気がある。
しかし、ポルトスにだけは心を許しているのか、彼と一緒にいるときだけは、よく喋る。
一方のポルトスはとても体が大きくて、大喰らいで、イノシシを一撃を倒す怪力の持ち主。
"気は優しくて力持ち"という言葉を、地で行くような性格をしている。
いつも食べることばかり考えており、自称グルメではあるものの、どうみても単なる食いしん坊にしかみえない。
だが、意外にもおしゃれには気を遣っており、仕立て屋のボナシューのお得意様でもある。
細かいことを気にしないポルトスは、そんな性格ゆえに仲間をピンチに招くこともあるが、
それ以上にポルトスの怪力は、幾度となく三銃士とダルタニャンを救ってきたことも確かだ。
そんなおっちょこちょいなポルトスを、普段無口なアラミスは容赦なくツッコんていた。
一見して性格が正反対に思える、アラミスとポルトス。
<あの堅物のアラミスが、どうして陽気なポルトスと馬が合うのか?>
これは銃士隊の中でも、最も不思議とされていることだった。
手元のカードを切りながら、アラミスが話しかける。
「ところで、ポルトス? 今日はいつもにも増して、機嫌がいいじゃないか」
「そ、そうか!?」
「究極の珍味にでも出会ったのか?」
「いや、珍しい料理ではないが、珍しい出会いもあるもんでな」
「なんだよ、もったいぶらずに話してみろよ」
「いや〜、それがその・・」
「どうした? 俺とお前の仲だろ」
「実は・・」
そういうと、ポルトスは少し照れくさそうに、ポケットから一通の手紙を取り出した。
アラミスは、ポルトスが恥ずかしそうに渡した手紙を、手に取る。
そして、興味津々にそれを読み始めた。
「なんだ、この手紙の内容は。あて先を間違えているんじゃないのか」
アラミスの声は、少し不機嫌だった。
「失礼だな、アラミス。俺はこうみえても、けっこうモテるんだぞ」
「それは初めて聞いたな」
「俺がモテない男よりは、モテる男のほうが、お前もうれしいだろう?」
「どうして俺が、うれしいんだ?」
ポルトスは少し頬を赤くして、横目でチラッとアラミスの顔をみる。
「いや、だからその・・」
なぜか言葉に詰まるポルトス。
急に指と指をつけて、モジモジとしだす。
アラミスはポルトスの発言を不審に思ったが、いつも通りの冷めた口調でぼやいた。
「なぜ顔を赤らめているんだ?」
「べ、別に赤らめてなどいない」
「お前は食べ物にしか興味がないと思ったいたが、女性にも興味があったのか?」
「俺だって、男なんだぞ。女性に興味があるのは当然じゃないか」
「しかし、お前に好意を寄せるのは、仕立て屋のボナシューくらいだと思っていたが」
「人生はうまい料理を食べることにある。もし女性が一緒に食べてくれるのならば、これほどうれしいことはない」
「お前は女のことでも、やはり食べ物のことに結びつくのだな」
「まぁそう言うな」
呑気なポルトスに対し、アラミスは眉間にシワをよせて悩みだす。
ゆっくりと、手紙をポルトスに返した。
「ポルトス、まさかこの手紙を本気にしているんじゃないだろうな?」
「本気さ」
「やめろ。あまりにうさんくさ過ぎる。なにかおかしいぞ」
「おかしくなんかあるものか」
「お前に恋文がくるなんて、お前が絶食するくらいあり得ないことだと思うな」
その言葉を聞いて、ポルトスは負けじと切り返す。
「なんだと、バカにするのか、アラミス!」
「だいたい、お前は食べることしか考えて無いじゃないか。食べ物の話ばかりして、相手ががっかりするぞ」
「さっきから一体どういうつもりだ、アラミス! 俺が女にモテちゃいけないようなセリフだな!」
「こんなあやしい内容の手紙は、気をつけたほうがいいと言っているんだ」
アラミスは相変わらず涼しい顔をして、ポルトスが気にしていることを平然と言ってのける。
そんな失礼な物言いに、ポルトスは憤怒したが、
フッと我に帰った様子で、僅かな笑みを浮かべる。
「ははぁ、分かったぞ。アラミス、お前は嫉妬しているんだろ? 隠さなくてもいいぞ」
「嫉妬などするか!」
ポルトスの不躾な一言に、アラミスはバンッと机を叩きつけた。
珍しく、アラミスが怒気を漲らせる。
「ポルトス、いまの発言を取り消せ!」
「軽い冗談だ。そんなに怒ることではないだろう」
「黙れ。ともかく取り消せ!」
「いやだ」
「なんだと・・。いいか、その手紙は絶対におかしい。言葉があまりに浮ついている」
「そんなことはない」
「お前に、こんな手紙を書く女が似合うものか」
「だったら、どういう女ならば良いというのだ!」
「とにかく、やめろと言っているんだ」
「別に心配などしてもらわなくて、結構だ」
「なんだと・・・勝手にしろ!」
「あぁ。言われなくても勝手にするさ!」
そういうと、2人はプイッと反対を向いてしまった。
アラミスもポルトスも気が強い。
ああいえばこういう状態になってしまうと、お互いに自分の非を認めようとしない。
ポルトスは、いい加減な口調で、ぼやく。
「まったく、手紙の女性が気になるからって、ついてくるなよ」
「なにっ!」
さらに火に油を注ぐような発言をしたポルトスは、憤然としたまま、部屋を出て行った。
ポルトスは、銃士部屋から外に出ると、大きなため息をついた。
(なんだ、アラミスのヤツ・・。あんなに怒ることはないじゃないか。
俺だって、おしゃれには気を遣っているんだ。女にモテて、なにが悪いんだ。
ちくしょう、もうアラミスとは、口を聞くものか)
ポルトスは穏やかで優しい性格の持ち主ではあったが、少々気が短いところがある。
一度頭に血が上ると、周りが見えなくなり、抑えられない性格なのだ。
それがポルトスの唯一の欠点と言えるだろう。
銃士隊の屋敷を出たポルトスは、不満げに口を尖らせながら、
日が落ちてきたパリの街を、ゆっくりと歩いていった。
まじで話が進んでない。