 ポルトス(右)とアトス(左)。アトスは三銃士のリーダー格。
ポルトス(右)とアトス(左)。アトスは三銃士のリーダー格。
ちょっと展開が変わりますが。
登場人物
 ポルトス(右)とアトス(左)。アトスは三銃士のリーダー格。
ポルトス(右)とアトス(左)。アトスは三銃士のリーダー格。
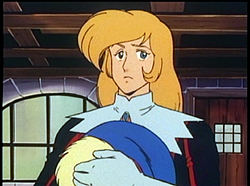 アラミス。三銃士きっての美形。剣術師範を務めるほどの腕前。
アラミス。三銃士きっての美形。剣術師範を務めるほどの腕前。

<みんなは一人のために>
<一人はみんなのために>
アトスとアラミス、そしてダルタニャンと剣を合わせて誓いあった言葉。
俺にはすばらしい友が、3人いる。
アトスは、俺が尊敬する剣の達人であり、頭も切れる。
1人で酒をたしなむのが好きで、大飯喰らいの俺とはまるで違う。
ダルタニャンは、まだ出会ってから1年も経っていないが、
曲がったことが大嫌いで、向こう見ずなところは、昔の自分を見ているようだ。
そして、アラミス。
アイツは、俺の・・いや、俺が一番大切にしている友達だ。
俺は友のためなら、命をかけられる。
そして、アラミスのためならば、命を捨てられる。
他人のために命を張るなど愚かな事だ、というヤツもいるだろう。
だが、俺にはそれが出来る理由がある。
それをしなくてはいけない理由もある。
たぶん、アトスにもアラミスにも、そしてダルタニャンにも、それぞれ理由があるのだと思う。
・
・
俺が銃士隊に入ったのは、いまから8年前、つまり俺が17歳のときだった。
当時から、俺は体が人一倍大きくて、力なら誰にも負けない自信があった。
だから、そのことを鼻にかけて、新米の銃士のくせにずいぶんと大きな顔をしていた。
中には俺のことを気に食わずに、ケンカをふっかけてくる者もいたが、俺は力でねじ伏せた。
当時、俺よりも剣術が優れた者は、アトスという年長者が1人いるだけで、
俺はアトスの冷静で博識なところに惚れていた。
アトスにだけは自分のことを隠さずに話すことができた。
だから、自然と仲が良くなった。
しかし、それ以外のヤツは眼中に入っていなかった。
そしていつのまにか、技のアトス、力のポルトスと呼ばれるようになり、俺はいい気になっていた。
人生で一番大切なことは、食べることだと考え、あちこちに美味いものを食いに歩き、剣術を磨くことを忘れた。
また、俺は気が短いので、たびたび護衛隊と揉め事を起こし、謹慎を命じられたこともあった。
今考えると、俺はトレヴィル隊長が、最も頭を抱える問題児だったかもしれない。
俺が20歳のときに、3歳年下の華奢な金髪の男が入隊してきた。
その男は、力はないが敏捷性があり、俺の剣術とは対極な位置にあった。
そいつは、えらく素っ気無い男で、自分自身のことを話すことは全く無い。
そのくせ、俺がうまい料理のことを雄弁に語ると、「ポルトスは食べ物のことしか頭にない」と皮肉を言いやがる。
一体、何を考えているのか、得体の知れない雰囲気が漂っていた。
だから、俺はそいつのことが嫌いだった。
俺よりも年下で、しかも後から入隊してきたヤツが、自分よりも優れていることを認めたくなかったのかもしれない。
ある日、パリの街で小さな内乱があった。
俺たち銃士隊は、反乱者が立て篭もる建物に突入した。
俺は血気にはやり、自分の剣術を過信して、1人で突っ走った。
しかし、反乱者たちは俺の行動を読んでいたのか、俺は罠にはめられて、銃で肩を狙撃された。
そして、俺を助けようとした仲間が、次々に死んでいった。
俺は目の前で、何人もの仲間が死んでいく光景を見た。
俺は強いはずなのに、弱いものを助けることができない。
それどころか、俺のせいで仲間が死んでいる。
俺は無力だった。
俺はただ、力一杯に剣を振り回すだけの、独りよがりの愚か者だった。
最後には、俺は肩と足に重症を負い、剣を喉元に突きつけられた。
死を覚悟した。
しかし、俺を間一髪救ってくれたのは、俺が大嫌いな金髪の男だった。
一瞬、俺は金髪の男に感謝したが、その考えはすぐに変わった。
そいつは、「"力のポルトス"の名が聞いて呆れる」と戦場の真ん中で、俺のことを堂々と笑いやがった。
そして、動けない俺の目の前で、金髪の男は1人で仲間を救っていった。
俺はその姿を、ただ呆然と見ているだけだった。
俺は半死半生のまま、なんとか生き延びた。
そして、戦いに散った多くの仲間の墓前で、俺はうまれて初めて号泣した。
銃士になるということは、ただ剣が強くて、力が強いだけでは、いけなかったのだ。
銃士とは、仲間とともに助け合い、時には仲間のため命をかけて、戦う者のことだったのだ。
それを教えてくれたのは、皮肉にも俺が"弱い"と眼中にも入れなかった、死んでいった仲間だった。
俺は大切な仲間を多く失って、初めて知った。
強いということは、他人を守れるヤツのことをいうのだと。
最も弱くて、惨めだったのは、俺だったことを。
俺はそれから毎日、死んだ仲間の墓前に足を運び、号泣し続けた。
ある日、俺が号泣する傍らで、もう1人、黙って涙を流しているヤツがいた。
金髪の男。
普段は黙って何も語らない男だが、そいつは、毎日墓前に花を供えにやってきていたのだ。
俺は 仲間のために涙を流している金髪の男を見て、初めて本当の心を見たような気がした。
金髪の男は、俺に視線を向けると、こう話した。
「ポルトス、お前はどうして毎日泣いているのか」と。
俺は答えた。
「ならばアラミス、貴様はどうして毎日花を供えに来ているのか」と。
俺はその場で剣を抜き、そしてアラミスに言った。
俺とこの場で、勝負しろと。
なぜならアラミスは、瀕死の俺をあざ笑ったから。
アラミスは黙って剣を抜き、俺に剣を向けて呟いた。
「剣は人の命を奪う。しかし、剣で人の命を救うこともできる。ポルトス、お前はどちらの人間になりたいのか」
俺はその言葉を聞いて、理解した。
俺の剣は、到底アラミスには及ばない。
剣の腕が強いとか、弱いとか、そういう次元の問題ではない。
俺の剣など、アラミスの剣に比べれば、何の役にも立たない、錆びた鉄くずと変わらない。
だから、俺は悔しくてさらに涙を流した。
そんな情け無い俺の頬を、アラミスは優しく拭いてくれた。
そして、柔らかい表情のまま語った。
「お前には誰にも負けない力がある。その力はどんな困難をも打ち砕くだろう。
仲間を守るために、私とともに剣術を磨かないか? 死んでいったもののためにも」

俺とアラミスは、その場で誓い合った。
俺たち2人は、これから永遠に友であり、良きライバルでいようと。
そして、銃士隊全員のために戦おうと。
<ひとりはみんなのために>
<みんなはひとりのために>
俺はアラミスと剣を天高く構え、誓ったのだ。
それから、俺は毎日アラミスと剣を交え、必死に剣術を磨いた。
月日が経つと、俺はアトス、アラミスとともに、パリの三銃士と呼ばれるようになった。
──仲間を絶対に裏切らないこと。
それが俺の信念。
そして、アラミスとの約束。
だから、俺はあのとき、護衛隊のジュサックが殺されそうになるのを見て、
見捨てることは、できなかった。
たしかに、俺たちは護衛隊と敵対しているし、ジュサックはいけ好かない野郎だ。
しかし、以前に鉄仮面を逮捕するために協力しあい、一度は信頼しあった仲間なのだ。
もう2度と目の前で仲間を死なせない。
仲間が殺されそうになったら、俺の命に代えても止める。
たとえそれが、ジュサックのような最低な野郎でもだ。
・
・
<"力のポルトス"の名が聞いて呆れる>
その声は・・アラミス・・!?
<こんな怪しい手紙に騙されるお前が悪い。お調子者もいいところだぞ、ポルトス!>
そうだな・・。
アラミス、お前の言うとおりさ。
お前が忠告をしてくれたとき、それを素直に聞いていれば、こんなことにはならなかったのに・・。
お前から見れば、俺は何年経っても、子供のように見えるのだろうな。
いま、とても後悔している。
お前とくだらないケンカをしてしまったことを。
なぁ、アラミス?
俺がジュサックを助けたことは間違っていたか?
俺はお前との約束を守りたかった。
しいてはそれが、俺のために死んでいった、多くの仲間に対する約束でもあるのだから。
しかし、その代償として、俺はベーズモーから逃れられなくなってしまった。
アラミス、俺はどうすればいい・・?
逃げることもできない。
戦う力も残っていない。
黙ってベーズモーの非道な行為を受けるしかないのか・・。
いまさら、こんなことを言っても仕方ないのは分かっている。
でも、俺はお前のことを誰よりも信じているから、まだ心のどこかで頼っている。
お前がきっと助けにきてくれると。
アラミス、早くきてくれ。
俺が頼れるのは、もうお前しかいない。
・
・
いや、待て・・。
なにを考えているのだ、俺は・・。
そうか、そうだったのか。
だから俺にはまだ、お前を受け止める資格がないのか。
だからお前は、俺に本当のことを話してくれないのか。
いつまでも、俺は"女"であるお前に頼って・・・。
こんなことだから、俺とお前の関係は、いつまで経っても・・。
あのときから、何も変わっていないじゃないか。
あのときの弱い俺のままじゃないか。
変わらなくてはいけないのに・・。
俺はどんなときでも、お前に頼られる男でなくてはいけないんだ。
・
・
なぁ、アラミス。俺はあのときの弱い俺のままか?
あのときの情け無い俺のままか・・?
頼む、教えてくれ・・。
次回、陵辱です(←ォィ)。