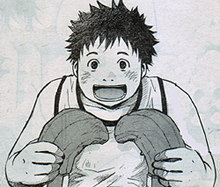 亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
太一と大二郎の関係とは?
登場人物
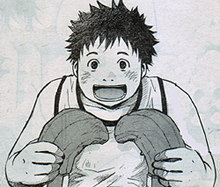 亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
暑さで焼けるようなアスファルトを見つめながら、太一は帰途についていた。
(僕、大ちゃんの機嫌を損ねちゃった・・どうしてだろう・・)
優しかった大二郎が突然怒った理由。
太一は、それをずっと考えていた。
(大ちゃんも、僕ががんばることを望んでないのかな・・がんばっちゃいけないのかな・・)
そう考えると、少しだけ、足取りが重く感じる。
無意識にポケットからハンカチを出して、額ににじむ汗を拭く。
汗かきな太一の、いつもの癖だ。
太一は大二郎の言葉を思い出す。
<俺がお前を守ってやる。そう約束しただろ?>
大二郎の言葉に、太一はいつも甘えていた。
それが当たり前のことだと、気にも留めていなかった。
(僕はずっと、大ちゃんに守ってもらってきた。
そういえば、いつごろからそうなったんだろう? どうして大ちゃんは、僕のことなんか・・?)
太一は、ボケッと歩きながら、小学生のころの大二郎を思い出していた。
・
・
僕と大ちゃんが、初めて同じクラスになったのは、小学3年生のとき。
それから小学4年生にまでの2年間、一緒のクラスだった。
僕は小さい頃から太っていて、小学生のときから"デブ"と呼ばれていた。
勉強ができるわけでもない。
体育の授業では、鉄棒は全然できないし、走るとすぐに息が切れるし、なにをやってもダメだった。
特に球技は、僕の大の苦手で、
ドッジボールやバスケットボールで、僕が同じチームになろうものなら、
みんなは「太一が一緒じゃ、負けちまうぜ」と不満を漏らしていた。
そんな僕は当然のように、みんなにイジメられていた。
<亀のようにノロマな太一>と毎日からかわれていたんだ。
一方の大ちゃんは、小学生3年生のときは少し太めで・・いや、いま考えるとけっこう太っていたかな?
そういえば、僕は色白で、大ちゃんは色黒だったから、
「太一は白豚、大二郎は黒豚」なんて冗談で言われていたような・・。
ただ、大ちゃんは僕なんかとは違って、スポーツができて、運動神経が良かった。
とても腕っ節が強くて、ケンカは誰にも負けなくて、クラスを支配している感じだった。
大ちゃんが「今日の昼休みはドッジボールな!」といえば、クラスの男子はみんなそれに従っていたと思う。
そういう存在だったんだ。
小学生のころは、同じクラスの中で、仲が良い友達で3つか4つのグループに分かれる。
僕はイジメられっ子で、あまり友達がいなかった。
がんばって友達を作ろうとか、考えたことがなかったから・・。
そんな僕は、なぜかいつも大ちゃんのグループに属していた。
気がつくと、そういうことになっていたんだ。
学校から帰ったあとは、いつも大ちゃんと僕と、4,5人くらいの友達が集まって、
鬼ごっこをしたり、ドッジボールをしたりして遊んでいたように思う。
僕が学校から帰ると、すぐにジャリンジャリン!という自転車のベルの音が鳴る。
大ちゃんが、僕のことを誘いにきた合図だ。
<太一、ドッジボールやろうぜ!>
<でも、僕あんまり・・>
<いいからやるの!>
家に引っ込み気味の僕の手を、大ちゃんはムリヤリに引っ張って、よく外に連れ出されたっけ。
それで運動オンチな僕は、いつもドッジボールで大ちゃんに狙われて、
真っ先にボールを頭や背中にぶつけられて、外野に追い出されてしまう。
大ちゃんの剛速球なんか、取れるわけないのに。
<うわ〜ん! 大ちゃん、僕のこと狙わないでよー!>
<ヘヘッ、いやだね>
あまり記憶にはないんだけど、母さんがいうには、
大ちゃんに誘われると、決まってイジメられて、メソメソと泣いて帰ってきたらしい。
母さんは、大ちゃんのことを『彼はイジメっ子だから遊ぶのをやめなさい』と嫌っていたらしい。
でも、僕は大ちゃんのグループに入らなければ、クラスで一人ぼっちだった。
だから、母さんに何を言われても、小学生のときはずっと大ちゃんと一緒に遊んでいたと思う。
遠足のグループ分けのときも、僕は真っ先に大ちゃんのグループに呼ばれていた。
昔のアルバムを見ると、僕の横には大ちゃんが必ず座っていて、
僕にちょっかいを出しながら、ピースサインをして写真に写っているんだから。
・
・
でも、本当のことを言うと、実際はあまりよく覚えていないんだ。
小学生のころの記憶はあまりなくて、すごい楽しかった思い出もないけど、すごい嫌な思い出もない。
大ちゃんが、僕のことをイジメていたことも、あまり記憶にはなくて、
母さんに話を聞いてなんとなく覚えている程度のことなんだ。
僕って記憶力が弱いのかな・・。
でも1つだけ、僕は大ちゃんのことで覚えていることがある。
小学4年のとき、たった一日だけど、大ちゃんの家に泊まりに行った事があるんだ。
どうして、大ちゃんの家に泊まることになったのかは分からない。
たぶん、僕の両親が、急な用事で田舎に帰るとかで、
たまたま大ちゃんが、家に泊めてくれることになったんだと思う。
僕は大ちゃんにイジメられていたけど、
大ちゃんのことは別に嫌いじゃなかったから、かなりはしゃいでいたと思う。
それに、他人の家にお泊りするっていうのは、すごいワクワクすることだったから。
大ちゃんの家で、なにをしたかはあまり覚えていない。
食事をしたり、ゲームをしたり、プロレスごっこをしたり・・そんなことをしたのかな?
それで、僕は大ちゃんと一緒にお風呂に入って、
そして大ちゃんの隣に布団を敷いて、一緒に寝ることになった。
電気を消して、真っ暗になる。
そして、数分たったとき──。
僕がウトウトとしていると、大ちゃんが僕の布団の中に入ってきたんだ。
そして、耳元でささやいた。
「太一、もう寝た?」
「う・・ううん・・まだ・・」
「寝る前に、体の触りっこしようぜ」
「え・・うん・・大ちゃんがしたいなら・・」
たしか、こんな会話をしたような気がする。
僕はパジャマを持って行くのを忘れて、シャツとパンツ一枚で寝ていた。
大ちゃんは、手探りで僕の胸を、シャツの上からゆっくりと触ってきた。
最初はくすぐったい感じだったけど、大ちゃんの手が僕のシャツをめくって、
直接触り始めたとき、僕はドキッとした。
一瞬、「やめて」と言おうと思ったけど、
大ちゃんが怒ると怖いし、胸を触られたらなんだか変な気持ちになって・・。
「あっ・・大ちゃん・・そこは・・」
僕も甘えた声を出していたかもしれない。
大ちゃんは、僕の体の上に乗っかってきて、両手を僕の背中に回した。
「太一、ちょっとだけな」
「・・!!」
僕は口から心臓が飛び出そうなほどびっくりした。
なぜなら、大ちゃんが、僕の上半身を思いっきり抱きしめて、
それで・・・僕の唇の上に、柔らかい唇を重ねてきたんだから。
(あうっ・・)
(はんむ・・)
僕はこの状況をどう理解したらいいのか、分からなくて、ボーゼンとした。
ただ、大ちゃんがチュッチュッと僕の唇を舐めてきたので、
僕も大ちゃんの唇の動きに合わせて、口をすぼめた。
そのうち、大ちゃんの舌が僕の唇をこじあけて、舌と舌が絡み合った。
あのときも気持ちは・・いまでも忘れない。
言葉じゃ、うまくいえないんだけど、
大ちゃんの心が、僕の体の中に流れ込んでくる感じっていうのかな・・。
このまま、大ちゃんとずっと一緒にいられたら・・なんて不思議な気持ちになった。
そう、僕が初めてキスをした相手は、大ちゃんだった。
もっとも、高校生になったいまでも、僕は彼女なんて出来たことがないから、
キスをしたのは、その日、大ちゃんとした一回きりだけなんだけど・・・。
その後のことは、あまり覚えていない。
大ちゃんは、僕のいろんなところを触っていたような気がするけど、
僕はただ目を閉じて、すべてを大ちゃんにゆだねていた。
抵抗する気は全くなかった。
なぜなら、僕はとてもうれしくて・・。
だって、クラスのガキ大将で、イジメっ子だった大ちゃんが、
僕のことを嫌いじゃないってことが分かって、とっても安心したんだ。
<太一、俺のこと好きか?>
<うん。大ちゃんのこと、大好き>
こんなことを話したような記憶もあるのだけど、
僕はただ大ちゃんの言うことにうなづいて、そのまま安心して眠ってしまった。
あの日、大ちゃんは僕になんて言ったんだろう?
そして僕は、大ちゃんになんて答えたんだろう?
頭の片隅に、うやむやしたまま残っているのだけど、どうしてもそれが思い出せない。
・
・
その後、僕と大ちゃんは違うクラスになり、離れ離れになった。
僕は大ちゃんと離れてから、あまり外に出て遊ぶこともなくなって、
毎日テレビゲームをして、家に閉じこもり気味になった。
体重がどんどん増えたのは、このころかな。
そして、僕が中学に入学したとき、再び大ちゃんと同じクラスになった。
(あ、また大ちゃんと同じクラスか・・)
僕はそれくらいにしか思わなかった。
小学校のときにイジメられていたのだから、
大ちゃんと同じクラスになったら、憂鬱になってもおかしくなかったのに。
僕は不思議と大ちゃんにイジメられるとか、そんなことは考えなかった。
入学式の次の日、授業が終わって帰ろうとしたとき──。
「太一!」
下駄箱で、僕は野太い声に呼び止められた。
「大ちゃん・・?」
大ちゃんは、僕が帰るのを急いで追いかけてきたのか、息を切らせていた。
そして、僕のすぐそばまで歩いてきて、少し照れくさそうな表情をした。
僕も大ちゃんににっこりと笑いかけて、返事をした。
「大ちゃん、また同じクラスになったね」
「太一・・ごめんな」
僕は大ちゃんが、何を言っているのか一瞬、理解できなかった。
「大ちゃん?」
「本当にごめんな。俺はもう太一のことをイジメないから、安心しろ。
約束する。だから許してくれるか?」
「ゆ、許すもなにも・・」
「そ、そうか。よかった。ずっと気になっていたんだ。
俺、これからは太一のことを守ってやる。あの日の約束だ。お前のことをイジメるヤツは、俺が絶対に許さねぇ」
「あの日・・」
「じゃあな。それだけ言いたかったんだ」
そういうと、大ちゃんは走って帰ってしまった。
僕はそれから、ずっと大ちゃんに守ってもらった。
中学になると、いろんな小学校からクラスのガキ大将が集まってくる。
でも、大ちゃんは体か大きくて、一番強かった。
僕がクラスでイジメられそうになると、大ちゃんはすっ飛んできて、そいつを殴り倒した。
<太一に手を出すんじゃねぇ!>
中学2年以降は、大ちゃんとは一度も同じクラスにはなっていない。
だけど、僕がイジメられたことを知ると、大ちゃんはいつも飛んできた。
だから、こんなに弱い僕でも、イジメられずに済んだんだ。
・
・
大ちゃんには、いくらお礼をいっても、言い切れないや・・。
でも、僕はいつまでも大ちゃんに頼っていちゃいけないんだ。
ボクシングをやって、少しだけ変われたんだから。
がんばろうと思ったんだから。
大ちゃんには悪いけど、僕はボクシングを続けたいんだ。
僕は自分でがんばって、そして大ちゃんのように強くなりたいんだ。
次回をお楽しみに。