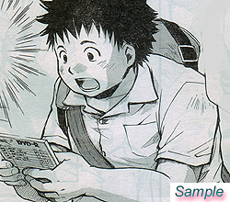 亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
いまだにボクシングを諦められない太一は・・?
登場人物
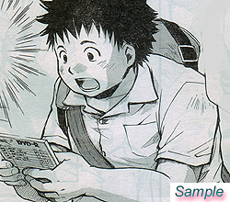 亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
「ほっ・・ほっ・・」
玄関先で聴こえる息遣い。
太一は夕食の前に、たるんだお腹を揺らして、縄跳びをしていた。
以前の太一ならは、この時間はテレビゲームに没頭していたはずだ。
しかし、一ヶ月間ボクシングをやり続けた習慣なのか。
ご飯の前に縄跳びをして、汗をかかずにはいられなかった。
 ←それっぽい場面があったので入れてみましたw
←それっぽい場面があったので入れてみましたw
縄跳びでかく汗は、ハンカチで拭く
よく「いい汗をかいた」というが、おそらくこの汗が「いい汗」なのだろう。
太一のトレーナーはびっしょりと濡れ、全身から汗が吹き出している。
縄跳びはキツイ。苦しい。
だけど、太一には分かっていた。
その汗をかいた後のシャワーが気持ちいいと。
そして、ご飯もグンとおいしいと。
だから、ジムに通わなくなった今でも、不思議と縄跳びを続けることができた。
ご飯を食べたあとは、太一は蔵田の試合のビデオを決まって見ていた。
以前、ジムから借りたものを、こっそりとダビングしたものだ。
蔵田の戦う姿。
なにかを追い求めて、「がんばっている」姿。
(そう、そこ! パンチ! カウンター!)
いつも同じシーンを見ているはずなのに、思わず手に汗握ってしまう。
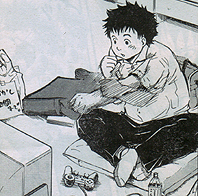
太一はいつのまにか、ビデオに映る蔵田の真似をして、部屋の中でシャドーボクシングの真似事をしていた。
周りからみれば、かなり格好悪くて、間抜けな姿だろう。
(僕もいつか蔵田さんのように格好良く、強くなれたら・・。
リングにもう一度あがって、蔵田さんや大塚君が話していたような「違う世界」を見られたら・・)
しばらくして、太一はため息をつき、シャドーをしていた腕をダラッと力なく落とした。
(でも、もう戻れないんだ。
負けたらジムをやめるって約束したんだから。
ちくしょう・・・。
僕はこんなにもボクシングが好きなったのに・・。
だから、余計に残酷だよ・・ひどいよ・・)
太一はそれから一週間、ロクに食事も取らずに、ただ学校に通った。
学校の勉強は相変わらず面白いものではなかったし、クラスに友達がいるわけでもない。
ただ、ボケッと窓から外を見て・・。
そして、宿題を忘れて、先生に怒られて・・。
クラスのみんなの嘲笑を受けても、恥ずかしくなかったし、凹むこともなかった。
休み時間は、誰もいない中庭の木陰でゴロンと昼寝をする。
ボクシングを始める前よりも、学校がさらにつまらなくなった気がした。
それでも太一は、学校から帰ると縄跳びをしたり、シャドーボクシングをしたりして、
嫌なことはすべて忘れようと必死になっていた。
もう一度、ジムに行ってみようかと何度も考えたが、あんなにブザマな負け方をして、
いまさらどんな顔をして、蔵田に会えばいいのか。
だから、太一にはジムに戻る勇気がなかった。
太一は、自分を情けなく感じた。
自分は本当にダメな人間なんだと痛感していた。
──数日後。
太一は思いつめたような顔をしながら、放課後の校庭を帰途につこうとしていた。
歩いていると、野太い声がする。
「おい、太一!」
太一がびっくりして振り向くと、そこには両手を腰に当てて仁王立ちした大二郎の姿があった。
(大ちゃん・・)
なぜか心臓が高鳴った。
太一は自然と、大二郎の大きな体に向かおうとしたが、途中で足が止まった。
(いま大ちゃんのところへ行ったら、僕は・・絶対に・・)
太一は、這い出さんばかりに慌てて校門に向きなおった。
「太一、待つんだ」
大二郎の腕が、背後から太一の腕をしっかりと握っていた。
ハァハァと軽い息をしていることから、大二郎は走って追いかけてきたらしい。
太一は大二郎に目を合わせられずに、視線を横にはずした。
「大ちゃん、ごめん・・」
「どうして謝るんだ?」
「ごめん、もう今日は帰るから・・」
「お前、顔色が悪いぞ」
「そんなことないよ・・」
太一の蚊の泣くような呟き声に、大二郎は表情を曇らせる。
大二郎は、腕をゆっくりと離した。
太一は、大二郎が怒っていないことに、ホッとひと安心する。
しかし、すぐに大二郎の声が響き渡った。
「太一、少し俺に付き合え」
「えっ?」
今度はさっきの倍の力で、大二郎は太一の腕をギュッと掴んだ。
「痛いっ! 僕は帰るって・・」
「いいから、来るんだ」
「放して」
大二郎の握力はめちゃくちゃに強くて、太一の二の腕が千切れんばかりだった。
「痛いよ、腕がちぎれちゃう」
「来るんだ。2人っきりになれる場所に行こう」
太一は引きずられるように、道場の裏にある倉庫に連れ込まれた。
──道場裏の倉庫。
冷んやりとして物音ひとつしない。
剣道や柔道の道具がたくさん置いてあって、なにかプーンとカビくさい。
床の一部には、柔道で使用する畳が敷き詰められている。
大二郎は、太一の背中を押して、倉庫に放り込んだ。
そして、しっかりと扉を閉めて、内鍵をかける。
いま、この倉庫の中は、太一と大二郎の二人だけ。
大二郎は、ショボンと無表情で立っている太一の前に、歩いてきた。
太一を見下ろしながら、話しかける。
「太一、最近どうしたんだ?」
「な、なにもないよ・・」
「目が左右に泳いでいる」
「え・・?」
「太一の癖だよ。ウソをつくときのな。
最近は宿題を忘れて先生に怒られているみたいだし、顔色も悪いじゃないか」
「どうしてそんなことを、大ちゃんが知ってるの・・?」
「太一のことは、俺が一番分かっているんだ」
「・・・」
「もう我慢しなくていい」
「えっ・・?」
「苦しいんだろ? 辛いんだろ? 俺には分かるんだ。隠し事はするな」
「うっ・・」
大二郎はゆっくりと両手を広げて、逞しい胸を突き出した。
「さぁ、こいよ。あの日みたいにさ、太一」
「大ちゃん・・」
大二郎の優しい言葉。
太一はずっと視線を落としていたが、大二郎の暖かさに感情が溢れてしまっていた。
「うっ・・えぐっ・・大ちゃん・・」
太一は、自分でも気がつかないうちに、大二郎の胸で泣いていた。
柔道着の襟を掴んで、顔をこすり付けるように。
「えぐっ・・うう・・うっ・・」
「しっかりしろ。俺がついてる」
大二郎は、太一を包み込むように抱いてあげる。
「ひっく・・うぐっ・・」
「全部話して見ろよ。俺が相談に乗ってやるから」
「うっ・・ひっく・・ありがとう・・」
太一は鼻水をすすりながら、ゆっくりとグシャグシャになった顔をあげた。
太一は目に溜まった涙を拭いながら、小さな声で呟いた。
「ボクシングをもう一度やりたい・・」
「太一?」
「大ちゃんは、僕にボクシングなんてやるなと言ったけど・・・」
「まさか、蔵田ってヤツに会いたいのか?」
「そんなんじゃないよ。僕はボクシングが好きになっちゃったんだ。本当だよ。
だって、僕は生まれて初めてがんばれたんだもの。ボクシングが心の底から楽しいって感じたんだよ」
太一の言葉に、大二郎はフッと深い溜息をつく。
「そんなに、がんばれたことがうれしいのか?」
「うん」
「がんばるなら、ボクシングじゃなくてもいいだろ?」
「ボクシングじゃないとダメなんだ。だって好きなんだから。
僕は大ちゃんみたいに、強くなりたいんだ。心も体も・・」
「俺みたいに・・?」
「うん。だって、大ちゃんは僕の憧れだもん。大ちゃんみたいに強くなりたいもん」
「太一・・お前、何を言ってるんだ・・」
「え・・」
「お前が強くなる必要はないんだ」
大二郎は、太一の両肩をそっと掴んだ。
そして、真剣な表情で太一に向かって話しかけた。
「俺が強くなったのは、あの日の約束だろ?」
「約束・・?」
「ま、まさか、俺との約束を忘れたなんてこと、ないだろうな!?」
「・・・」
黙ってしまった太一に対し、大二郎は突然、目尻を吊り上げてにじり寄った。
「あの日の約束を忘れたっていうのか!?」
「あの日って、僕が大ちゃんの家に泊まった日のことだよね・・?」
「当たり前だろ!」
「あの日のことは覚えてるよ。大ちゃんと・・その・・キスしたことだって覚えてるんだ。
だけど、そのあとになにを約束したか、細かいことまで全部覚えてないんだ。
頭の片隅になにかモジャモジャとしたものはあるんだけど、分からないんだ。ごめんなさい・・」
その言葉に、大二郎は唇を噛み締める。
「太一・・・この大バカヤロウ!」
大二郎のゴイツ指が、太一の柔らかい肩を強く握りつぶした。
額に汗を流し、僅かに震える太一。
そんな太一に、大二郎はひとつ大きな溜息をついた。
「なぁ太一、頭の片隅に記憶があるんだな?」
「えっ・・?」
「ならば、いまここで、思い出せばいいんだ」
「な、なにをするつもり・・?」
大二郎は、太一の正面に立ち、両腕をガシッと鷲づかみにする。
そのまま自分の足裏を、太一の足にかける。
「わわっ!」
まるで柔道の足払いをするように、体重をかけて太一を畳の上にドスンと押し倒した。
大二郎は倒れている太一のお腹の上に、強引にまたがったいたのだ。
次回をお楽しみに(こればっかり)。