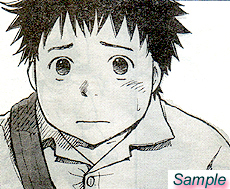 亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
大二郎に押し倒されてしまった太一たが・・?
登場人物
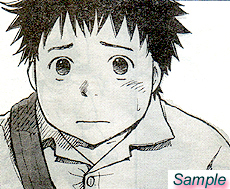 亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
亀山太一。16歳の高校一年生で、デブで運動神経が悪いために、クラスから疎んじられている。
畳の上に仰向けに倒されてしまった太一。
大二郎は、太一のふくよかなお腹の上に、ゆっくりと腰を下ろした。
いわゆる、マウントポジションというヤツだ。
<はぁはぁ>と息を荒げる太一のお腹。
太一の緊張した面持ち。
一方、お腹にまたがった大二郎の顔つきは、柔らかいものだった。
大二郎が話しかける。
「俺は、"あの日の太一のすべて"を覚えている。どういう意味か分かるか?」
大介の発言に対し、太一は言葉を詰まらせる。
無言で首を横にふった。
「そうか・・。高校を卒業するまでは我慢する約束だったけど、
いま、あのときの約束の1つを果たすからな。太一がいけないんだ。お前が約束を忘れたんだから」
大二郎は、そっとYシャツのボタンに手をかける。
真っ白でそうな清潔な太一のYシャツ。
上から1つ、また1つと、ボタンを丁寧にはずしていく。
その様子を、太一はゴクリと生唾を飲んで、ただ見守っていた。
大二郎は大きな指で、太一のYシャツのボタンを器用に外す。
やがて、ボタンはすべて外れ、
太一の体を纏っていた白いYシャツは、彼の体のもとから離れた。
「あっ・・あっ・・」
太一は、恥ずかしさのあまり、肩を震わせて視線を横にずらしていた。
大二郎は上からゆっくりと、薄いランニングシャツ一枚になった太一の体を見つめた。
太一が着ているシャツは、汗で濡れていて、ふくよかな肢体にぴったりと張り付いている。
乳房が大きい。
そのためか、桃色の乳首がシャツから浮き出るように見える。
大二郎は、太一の胸までゆっくりと顔を近づける。
目を閉じて、ただクンクンと鼻をならす。
「懐かしい・・・汗臭さと石鹸が混じったような・・これが太一の匂い・・」
「大ちゃん・・」
太一は大二郎の行動に、顔を真っ赤にさせる。
太一の上半身は日に焼けていないためか、シャツに劣らず色白だった。
お腹も、胸も、二の腕も、どの部分も触りたくなるくらいに柔らかそうで、プニッとしている。
あまりに大二郎が見つめるものだから、太一は思わず手で豊満な胸を隠そうとする。
しかし、大二郎の真剣な眼差しを見ていると、隠す行為すら失礼に感じた。
無意識にモジモジとする太一を見て、大二郎の頬は緩んだ。
「太一、ゆっくりと目を閉じろ」
「目を?」
「閉じるんだ。そして落ち着ついて思い出すんだ。ゆっくりでいい。
ここは俺の部屋だ。お前は小学4年生で、俺の家に泊まりに来た」
「大ちゃんの部屋・・?」
「思い出せ。記憶を辿るんだ。あの日に起こったすべてのことを」
太一は目を瞑って、あの日のことを必死に思い出した。
──あの日・・。
えーと・・たしかお風呂から上がって、大ちゃんとテレビゲームをしていたっけ・・。
そのうち、だんだん眠たくなってきて・・。
僕と大ちゃんは、一緒に布団を2枚敷いた。
僕は大ちゃんのとなり。
一緒に寝ることになったんだ。
電気を消して、真っ暗になる。
僕は目を閉じて眠ろうとした。
・
・
目を閉じると、なんとなく思い出してくる・・。
こんな風に真っ暗だった。
それからウトウトとして・・・。
耳元で大ちゃんが囁いてきたんだ。
(太一、もう寝た?)
(ううん・・まだ・・)
(寝る前に、体の触りっこしようぜ)
(うん・・大ちゃんがしたいなら・・)
僕は、無意識に大ちゃんに呟いていた。
「大ちゃん、あのときと同じことして・・お願い・・」
「あぁ。分かってる」
大二郎はゆっくりと太一の胸に手を伸ばした。
シャツの上から、太一の胸を優しく撫でる。
右手で太一の左の乳房を握り、左手でもう片方の乳房を握った。
大きくて、女の子のような太一のおっぱい。
そのまま大切なものを扱うように、乳房を上下にゆっくりと揉んでいく。
「あっ・・大ちゃん・・そこは・・ううっ」
「太一、気持ちいいか?」
「はぁ・・ああ・・」
大二郎は、円を描くように太一の柔らかい乳房を刺激していく。
ときに優しく、そしてときに上下に突き上げるように。
「これが成長した太一の胸・・」
「ああっ・・大ちゃん・・なんか変な気持ちに・・・」
「ど、どうした?」
「この感じ・・ずっと昔に感じたことが・・。あの日、大ちゃんの部屋で・・ああっ!」
「そうか・・」
「あんっ・・大ちゃん・・!」
突然、太一は喘ぐように叫んだ。
「ああっ、うっ、はんあ・・」
乳房から体全体に伝わる、大二郎の手の暖かさ。
太一は、ただ目をギュッと閉じて、打ち震えるような快感に身を任せていた。
大二郎は柔らかい表情で、両手をゆっくりと太一の背中に回した。
「太一、ちょっとだけな」
「えっ・・」
大二郎は、太一の上半身を思いっきり抱きしめる。
そして、重力にまかせるように、自分の唇を太一の唇に重ねた。
「!!」
その瞬間、まるで電気が走ったかのように、太一の体がビクリッ!ともんどりうった。
(あうっ・・)
(はんむ・・)
大二郎は太一の唇の感触を、舌で確かめるように舐めていった。
太一もそれに呼応するように、口をすぼめてお互いの唇の感触を確かめ合った。
そのうち、大二郎の舌が太一の唇をこじあけて、舌と舌が絡み合う。
(ああっ・・この感覚は・・・。
大ちゃんの心が、僕の体の中に流れ込んでくる・・。
気持ちいいとか、心が休まるとか、そういうのじゃなくて・・。
このままずっと、大ちゃんと一緒にいたい・・。
そっか・・この気持ち・・・大ちゃん・・。
僕はずっと大ちゃんのことが・・そうだったんだ・・)
いつの間か太一の目から、しょっぱい涙が零れ落ちていた。
次回、最終回です。