

性格

シシの設定をみると、「いつもヒヲウとケンカばかりしている力が自慢の機の民」とある。たしかにヒヲウとはケンカばかりしている場面が多い(だいたい「べんべらぼう」の言い合いなのだが・・)。
ヒヲウは常になにかのアイデアを模索したり、信念をもって行動しているタイプなのだが、シシは特に何も考えていないで行動している直情型のタイプである。シシとヒヲウと同い年だが、シシはヒヲウより純粋で子供っぽい。シシはなにか言われると、「どうすんだよ」とか「そんなこと知らねーよ」などとすぐに相手に喰ってかかる。その場しのぎというか、何も考えていないというか、こういうセリフがシシらしいといえばシシらしい。まぁ言ってしまえば、あまり機転が利かなくて鈍くさいタイプの子供だ(まぁそれはそれで俺の好きなところ。信念をもった子供など薄気味悪い←カテジナさんか?)。
ヒヲウとシシのコンビは、見た感じではシシの方が強そうなのだが、シシは舌足らずのために(笑)、自己主張で完全にヒヲウに負けている。そのために、ホムラの主役クラスの中では、埋もれてしまっている感じが強い。主導権は常にヒヲウに握られ、「シシ、来い!」だの「シシ、なにやってんだ!」とヒヲウに振り回されっぱなしである。シシもそのあとに「なんだよ!」とか「おめーがやれ!」と、これまたシシらしいセリフで反撃を試みてはいるが、わがままで自己主張たっぷりな主人公のヒヲウにそんな言葉は全く通じない。特に後半に行けば行くほど、シシは角が取れて、ヒヲウに対して従順になっていっているような気がする。別の意味で考えると、序盤のシシはかなり無鉄砲だったが、終盤にいくと、ひとり立ちして成長したと解釈するべきなのだろうか(わずか8歳にして母親の死という最悪の事態を乗り越えたわけだし・・)。
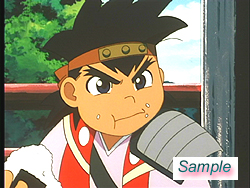 個人的には、シシにはもうちょっと弾けて欲しかった。ガキ大将というほどのインパクトがないし、なんだかんだでけっこうおとなしい性格なのである。思い切って、全員を仕切るくらいの暴れん坊ぶりを発揮してくれたほうが、見ている方としても分かりやすくて感情移入もしやすいと思うのだが・・。まぁそうしてしまうと超わがままで目立ちたがり屋の主人公、ヒヲウとキャラ的にかぶってしまうので仕方なかったのかもしれない。このアニメは、ヒヲウを中心として回っている主人公至上主義アニメなので、ヒヲウ以上に目立つことが許されなかったのだろう。
個人的には、シシにはもうちょっと弾けて欲しかった。ガキ大将というほどのインパクトがないし、なんだかんだでけっこうおとなしい性格なのである。思い切って、全員を仕切るくらいの暴れん坊ぶりを発揮してくれたほうが、見ている方としても分かりやすくて感情移入もしやすいと思うのだが・・。まぁそうしてしまうと超わがままで目立ちたがり屋の主人公、ヒヲウとキャラ的にかぶってしまうので仕方なかったのかもしれない。このアニメは、ヒヲウを中心として回っている主人公至上主義アニメなので、ヒヲウ以上に目立つことが許されなかったのだろう。
力が自慢という点はどうだろうか?実際にヒヲウを肩車したり、持ち上げたりするパワーはあるのだが、それ以上のパワーはない。風陣の大人相手には全く歯が立たず、所詮は子供の中での力持ちという設定。力が自慢ってのがあまり活かされなかったので残念。そもそも暴力を主人公が否定するので、シシの自慢の力を出す場面もなかったように感じる(つくづく、主人公至上主義なアニメだなぁ)。
また、「暴走気味」という設定があるのだが、これはちょっと違うと思う。シシは別に暴走している場面なんてないし、どちらかというと、ヒヲウの方がわがままで暴走している。たぶん、2話〜4話あたりの仇討ちのシーンから「暴走気味」という言葉がでてきているのだと思うのだが、あれは暴走ではなく、シシとしては当然の行動だと思う。仇討ちのシーンに関しては下で詳しく書こうと思う。
雷電

雷電とは、シシが常に肌身離さず(?)持ち歩いていたカラクリ人形の名前である(一体あの服の中のどこに隠し持っているのかは不明。ふんどしの中か?)。ヒヲウに対抗して作ったカラクリ人形で、明らかにヒヲウのカラクリ人形"錦丸"を意識して作ったものだろう。ヒヲウに勝つために改良に改良を重ね、創意工夫をしたシシの快心の作品と思われる。雷電は、形と名前から、関取をイメージしたカラクリと思われ、体型は横に広くシシらしい力強さを全面に打ち出したデザイン。しかし、そのためかヒヲウの錦丸のようにピョンピョン飛び跳ねたり、バック転をするような芸当は得意ではなく、もっぱら腕を伸ばして相手を投げたり、持ち上げたりするのを得意とするようだ。ただ、一部の場面では空中戦を演じたりしていたので、それなりの機動性も持ち合わせているらしい。
シシのカラクリ師としての腕は、見かけによらずなかなか優れていると思われる。おそらく幼い頃から、ライバルのヒヲウの錦丸とカラクリでの勝負をずっとしていたために、自然と腕も上がったのではないだろうか。シシは、壊れた錦丸(ヒヲウのカラクリ人形)を自力で修理していたので(修復したあとに、ヒヲウに「ヘタクソ!」と言われていたが←これもわがまま主人公ならではのセリフだ・・)、ヒヲウのカラクリの構造も理解できる知識はあるようだし、細かい作業はけっこう得意のようだ。そもそも天才と言われるヒヲウのカラクリとほぼ互角に渡り合っているのだから、シシの技術はけっこうなものだと思うのだが、あまり物語中でそのような印象を受けないのが残念だ。
シシが活躍するシーンが少ないのと同様、実際に雷電が活躍するシーンはあまりない。これがまた悲しい。雷電は、最後には新月城のワナを偵察するために、ヒヲウに強引に奪われて串刺しにされてしまい、そこで命尽きてしまった(シシは泣いていたのに・・やっぱり主人公のわがままっぷりには勝てません)。その後、シシは雷電のような人形カラクリを作った形跡がない。
服
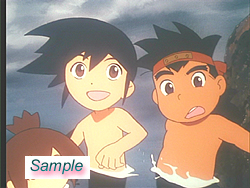
シシの服はカラクリ師を意識してか、ちょっと派手な祭り服を着ている(これが普段着なのかなぁ?ちょっと派手じゃないですか?)。なぜ肩あてがあるのかよくわからんが、頭にバンダナ、そして継ぎはぎをしたズボンである(←これポイント)。たしか、他の服に着替えたときも、シシのズボンはなぜかすべて継ぎはぎがあったと思う。そんなに家が貧乏だったのだろうか? 腰には茶色の巾着のようなものをぶら下げているが、ここに雷電が入っているのかと思ったが、どうも大きさ的には入らないようなので、カラクリの道具が入っているのかもしれない(やっぱり雷電はふんどしの中か?)。
さて、問題のバンダナ。風呂のシーンでも取らなかったバンダナは、母親がシシの誕生日に作ってくれたプレゼントなのだろうか?これってつまり、死んでしまった母親の唯一の形見になるということか? だから風呂でも外さなかったと予想。(しかし、最終話の4年後はバンダナの形が変わっているので、形見じゃないのかな? 頭が大きくなったから自分で調整したとか・・)
ちなみに風呂のシーンでは、フルチンです。しかもデベソなのがわかりました。本当はフルチン画像を載せようと思ったのですが、さすがに自粛・・・(みたい人はDVD買ってくださいってぉぃ)。
ホムラのパイロット

シシはヒヲウとともにホムラのパイロットを務める。第1話でヒヲウと共にホムラを動かそうとしていたシシは、ヒヲウを肩車したときにたまたま落ちてきたホムラのパイロット服に入ってしまい、そのままホムラの足の部分を担当するようになる。しかし、この足の部分、シシは目しか見えない状態で、なんとも損な役回りである。しかもシシはヒヲウを常に肩車した状態でホムラを動かしているので、相当重労働のはずなのだ(力自慢というのはこの意味だったのか?)。肩車ってけっこう疲れるんですよね・・。
ホムラが人間の形に変形したときに、うまく歩いたりしているのは、シシの操作技術によるものなのだが、それがすべてヒヲウが動かしているように見えてしまう。新月藩に入るときの岩場を渡っていたのはすべてシシのお手柄だし、水中での移動しての大活躍はすべてシシがペダルを漕いで移動させていたものによる(しかもヒヲウを肩車して)。はっきりいって、ヒヲウはただ手を横に動かしているだけな気がするんだがな。
しかもホムラがちょっとでも傾いたりすると、ヒヲウに「シシ!ふんばれ!」とか「シシ!なにやってんだ!」とシシが怒られる。つまりどんなにホムラで活躍しても、都合の悪いときはシシのせいになり、おいしいところはすべてヒヲウに持っていかれてしまうというとんでもなく悲しい役割だ。こんなところにも主人公至上主義の片鱗が・・。シシ派としては、見ているとヒヲウのわがままっぷりに腹が立ってくる(たまには上と下を変わって、シシの大変さを思い知れ!)。
仇討ち(最大の見せ場)
シシの最大の見せ場は意外にも物語序盤(第2話〜第4話)である。機の民の村が風陣に襲われ、シシの母親は捕らわれて(殺されて)しまう。ヒヲウやシシたちはホムラで村を脱出するが、シシだけは「かあちゃんを助けに行く」と言う事を聞かない。なぜならシシは一瞬にして帰るべき家も、母という唯一の心の拠り所も失ってしまったからだ。
シシの家庭は母子家庭のようで、父親は他界しているようだ。父親がいつ亡くなったのかはわからないが、もしかしたら父親の死を明確に思い出せるころに亡くなった可能性も高い。父親の死の悲しさを知っているからこそ、母親の死まで直面することは耐えられなかったのかもしれない。
当然、シシの行動は直情型そのものとなり、母親を助けることだけに目が向いてしまう。隣村に来ていた同心たち突破し、仲間のことを考えずに勝手に村に戻ったり、風陣にホムラの場所を教えてしまったり、母親を助けるためなら何でもやる!という周りが見えていない行動をしてしまう。このあたりのシシの心理描写はよく出来ている。シシの気持ちを考えれば、これは自然な行動だと思う。これを「暴走気味」と設定に書かれているのはなんともいただけない。
一方、ヒヲウは、母親はすでに他界しているし、父親のマスラオは行方不明。しかもたくさんの兄弟がいる。機の民の村が全滅してしまったことに怒っているのはヒヲウとてシシと同じなのだが、心の余裕が全然違う。ヒヲウはシシを励まそうと、なにか言葉をかけるのだが、それはシシにとっては余計なお世話、なぐさめにもならない。それどころか、あっけらかんとしたヒヲウに対してシシは怒りをぶつけてしまう。例えばこんなシーンがある。シシが赤ん坊のジョウブの世話を頼まれて、ホムラの中にヒヲウといるとき、シシが母親の死に耐えている場面だ。
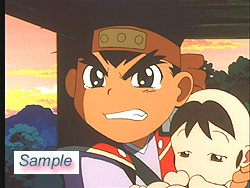 ヒヲウ「おい、見ろよ。ぜんまいがすべて自動的に巻かれている。馬で走っているときに巻き取る仕掛けになっているんだ!」(←空気読め!)
ヒヲウ「おい、見ろよ。ぜんまいがすべて自動的に巻かれている。馬で走っているときに巻き取る仕掛けになっているんだ!」(←空気読め!)
ヒヲウ「こうしておけば、いざってときにまたホムラを暴れさせるぜ!」(←だから空気読め!)
シシ 「うううううう」(←怒り心頭)
ヒヲウ「なぁ!(悪魔の笑顔)」
シシ 「なぁ じゃねぇーんだよ!!」
ヒヲウ「はぁ?」(←空気読め!)
シシ 「なんでお前はそんなに平気なんだ? 俺たちは帰るところねぇんだぞ!」
シシ 「村は滅茶苦茶にされて・・・かあちゃんたちが・・かあちゃんたちが・・・・・こっ・・」
ヒヲウ「殺された?」(←無神経すぎ)
シシ 「うぅ・・・・言うな!!!」
ヒヲウは、まだこのときシシにかけるべき言葉が見つからなかったのだと思う。なぜならヒヲウ自身も自分にできることが何だか分からなかったからだ(それを諭してくれたのは才谷(坂本竜馬)だったわけだが・・)。シシに適当な話題を言って気を紛らわそうとしたのだろうが、これは無神経というか、シシからするとシャレになっていない(これもヒヲウの主人公至上主義だから言える言葉ですね・・)。
しかし、その後、傷心したシシの前に原田左之助(後に新撰組の隊長となる人)が現れる。襲ってくる風陣を刀であっという間に殺した原田に、シシは目を奪われる。そして原田はこう話すのだ。

原田 「仇討ちだ」
シシ 「仇・・うち?」
原田 「そうだ。仇は討たねばならん」
ヒヲウ「勝手に決めないでよ!」
原田 「奴らの非道を認めるのか?何もしないことは奴らを許すことだぞ」
ヒヲウ「そんなこと・・」
原田 「いいか、例え子供でも立ち向かう相手に背を向けてはいかん」
シシ 「そうだよ、仇討ちだよ!かぁちゃんの仇を討つんだ! 俺がやりかたったのはそれなんだよ!」
ただ逃げ回るだけで何もできなかったシシは、原田の「仇討ち」という言葉にあっという間に感化される。なぜなら、シシは一体この先どうしていいのか分からなかったからだ。やっと1つの答えらしきものがシシの中に見つかったのである。シシは原田とともに母の仇討ちに向かうことに決める。
ところが、原田と共に仇討ちに出たシシではあるが、人を殺すなどということとは無縁の生活をしていたため、人間の死体をみただけでも足が震えてしまう(まぁ普通そんなもんですよね・・)。そしてシシが風陣に突っ込もうとしたとき、ヒヲウはなんとかカラクリでシシを止める。しかしお互いに納得できないシシとヒヲウ。

ヒヲウ「べんべらほう!助けてやったんだろ!」
シシ 「うるせー、余計なことしやがって」
ヒヲウ「余計じゃねー。あんなとこ突っ込んで殺されちゃったらどうすんだよ!」
シシ 「関わりねー!そんなこと!!」
ヒヲウ「関わりなくねー!!」
シシ 「関わりねー!」
ヒヲウ「関わりなくねー!!」
シシ 「俺には関わりねーんだ。恨み晴らすためなら死んだっていい!」
ヒヲウ「いいわけないだろーー!!」
シシ 「おまえには分かんねーんだよ!」
ヒヲウ「分かんねーのはお前だ!」
ヒヲウ「俺は嫌なんだよ。誰か死ぬのも、殺すのも!」
ヒヲウ「行くんなら、カラクリで俺に勝ってからいけ!」(←強引な展開だな〜)
ヒヲウの物語を通しての信念がよく出ている場面である。ヒヲウは物語中ずっと戦いを否定する。だから一番の親友であるシシが人を殺すのも、殺されるのもヒヲウにとってはどうしても我慢できないことだった。だが、シシを止める策を思いつかないヒヲウは、シシを強引にカラクリ勝負に持ち込ませる(なんだかよくわからんのですが、本当に強引です)。しかし、怒りに燃えるシシは原田の槍でヒヲウの錦丸を串刺しにしてしまう。

シシ 「そうだよ、遊びだよ。こんなの遊びだ・・」
ヒヲウは何度もシシを止めようとした。カラクリで対決することによって、シシにまたカラクリの楽しさを思い出して欲しかった。それくらいしかヒヲウにはシシを止める方法が思いつかなかったのだ。
だが結局止めることはできない。それはシシが母親を惨殺され、"仇討ち"という、方法としては好ましくはないが正当な理由をもって行動しているのに対し、ヒヲウがシシに言っているのは所詮は綺麗事だからである。しかし、シシは一時的な感情とはいえ、粉々に破壊してしまった錦丸をみて、心情に変化が起こる。立ち去ろうとする原田を待たせて、錦丸を修復するのである。
シシ 「あ、この削り方。これヒヲウの工夫なんだ」
シシの言葉に徐々にカラクリ師としての本能が戻ってくる。この言葉に原田も苦笑いし、シシには仇討ちは無理だと悟るのである。それにしても、シシの唐突な心変わりは演出があまりよろしくない。あれだけ仇討ちに燃えていたシシが、急にヒヲウの気持ちを汲み取って改心してしまう。ちょっとドラマとしては都合が良すぎな感じもするのだ(所詮ドラマなんてこんなもんか?)。
この部分を俺なりに解釈すれば、シシは粉々になった錦丸に、自分の死に行く姿をオーバーラップさせたのだと思いたい。つまり、このまま仇討ちを続ければ、シシの将来は破滅しかないということだ。仇討ちなどといきがってはみたものの、結局自分はカラクリ師だということを思い出した、ということだと思うのだが(どう解釈するかは人それぞれですね・・)
このあと、偶然襲ってきた風陣に対し、なし崩し的にホムラに乗り込み、そのままヒヲウと旅を続ける決心をしたシシ(このへんもけっこう強引です)。もしかすると、シシは他に仇を打つ方法を探そうとしたのかもしれない。また、ヒヲウを信じ、ヒヲウと旅を続けるうちに、なにか目的が見つかるかもしれないと期待したかもしれない(かなり微妙な解釈ですが・・)。

ちなみにずいぶん後の話になるが、ヒヲウの父、マスラオに出会ったシシは、マスラオが風陣に加担していたことを知る。信じていたヒヲウの父親が、自分の母親を殺した風陣に加担していたことに驚くシシ。自分の母親が殺された悲しみをずっと耐えながら、真実を知るためにヒヲウの言葉を信じて旅をしてきた結果がこれである。
シシの怒りはついに爆発する。しかし、ヒヲウはこの場面では「マスラオの知らないところで、機の民の村が襲された。つまり父は無関係」と思っているので、シシの気持ちを察することはできなかった(これまた主人公至上主義だなぁ)。
結局いままでの旅も報われず、母親の仇もとれなかったシシは、ここで行き詰まってしまう。しかし、ずっと旅を続けたきたシシには、もはや仇討ちのことなどどうでもよくなっていたようだ。ある程度心の余裕というか、成長した姿がそこにあったのだ。このあとヒヲウを責め続けるわけでもなく、自分がやらなくてはいけないことをヒヲウとともに歩んでいくことになる。それにしても、いつも主人公の都合で振り回されるシシは、ちょっとかわいそうな少年だったなぁとつくづく思う。
獅子王で妄想

本編中に獅子王という公家が登場する(獅子の面をカブッたコスプレイヤーです←ぉぃ)。公武合体を主張し、尊皇攘夷派である清河たちを手玉にとった精悍な面をした公家である。実はこれをみたときに、「獅子王」ってまさか、シシのお父さんなんじゃないだろうなと思った。だって、獅子王=シシ・オウ=シシのオウという解釈が成り立つし・・(強引ですけど)。そもそも「シシ」っていう名前がちょっと変わっているし、なにかあるのではないかと妄想していたのだが、何も関係なかったのでがっくりだった(まぁ顔がどうみても似つかないから違うかな・・)。でも、もしこの設定が本当だったらシシ派としては相当おもしろかったと思う。
それでちょっと妄想してみる。実はシシは獅子王から生まれた公家の子供で、赤ん坊のときに獅子王から機の民の村に送りこまれた。第1話で登場するシシの母親は獅子王からシシを育てるのを頼まれた仮の親。獅子王はカラクリを戦さに使うためにどうしても機の民の力、ホムラが必要だった。獅子王がシシを機の民の村で育てさせた理由は、戦さになったときにシシにホムラを使わさせるため。そして獅子王の狙い通り、シシはホムラとともに京都の獅子王の元へ。衝撃の真実を知ったシシはさて、どうなるのか?という感じ。妄想が膨らみすぎて、あと原稿用紙で100枚くらい書けそうなのでもうこのへんでやめとこう(もしこのあとの妄想ストーリーが知りたいという人はメールください←誰もいないか)。
ヒヲウ戦記全般について
ヒヲウ戦記は、幕末を舞台とした冒険活劇である。ヒヲウたちカラクリ師と坂本竜馬などの英雄をミックスし、幕末という激動の時代に、西洋の文化に対して、日本の伝統文化であるカラクリが大活躍したというパラレルワールドを作り出している。世界観は悪くないのだが、物語全体をみたときに、一体何が言いたいのかいまいちよくわからない。たぶん子供の成長をテーマにしているのだと思うのだが、それにしてはあまりに舞台が大きすぎる。ヒヲウたちは新月藩のお家騒動に巻き込まれたり、尊王攘夷の動乱に巻き込まれ、右往左往しているようにしかみえない。その中でヒヲウはカラクリを使って戦を懸命に止めようとするが、時代のうねりはその行動さえ最終的には否定しまてしまい、結局戦いはずっと続くということになってしまう。第25話で、ヒヲウたちの機の民としての筋は通したという形では終わっているが、ではそれがなんだったのか?と問われると返答に窮する。また、幕末という時代を選んだのはおもしろいと思うのだが、わずか8歳の少年たちが歴史の重要人物に影響を与え、それによって歴史が動いたという話も、いまひとつ徹底していないというか、中途半端というか・・。幕末の歴史まで取り込んでしまったのはちょっと欲張りすぎだったのではないだろうか。
 たださえ、初期登場人物が多い中(ヒヲウ・シシ・マチ・テツ・サイ・マユ・ジョウブ)、新月藩の雪と華をメイン以上の重要役として登場させ、さらに敵のアラシなどの風陣、幕末の志士も多数登場させているので、主人公たちへのスポットはヒヲウ意外はあまり当たっていない(はっきりいって人多すぎ)。また、主人公至上主義アニメなので、なぜか登場する人物すべてが、わずか8歳のヒヲウにばかり注目するのもいただけない(シシは思いっきり無視されているのがムカツクし、そもそも大の大人が8歳のガキなんて相手にするかね?)。数々の大名や、公家、坂本竜馬までがヒヲウにゾッコンなのもあまりにご都合主義的な感じがする。せっかくヒヲウ・シシ・マチという理想的なトリオを組んでいるのだから、この3人を中心にもっといいドラマができなかったのだろうか?
たださえ、初期登場人物が多い中(ヒヲウ・シシ・マチ・テツ・サイ・マユ・ジョウブ)、新月藩の雪と華をメイン以上の重要役として登場させ、さらに敵のアラシなどの風陣、幕末の志士も多数登場させているので、主人公たちへのスポットはヒヲウ意外はあまり当たっていない(はっきりいって人多すぎ)。また、主人公至上主義アニメなので、なぜか登場する人物すべてが、わずか8歳のヒヲウにばかり注目するのもいただけない(シシは思いっきり無視されているのがムカツクし、そもそも大の大人が8歳のガキなんて相手にするかね?)。数々の大名や、公家、坂本竜馬までがヒヲウにゾッコンなのもあまりにご都合主義的な感じがする。せっかくヒヲウ・シシ・マチという理想的なトリオを組んでいるのだから、この3人を中心にもっといいドラマができなかったのだろうか?
また、タイトルにカラクリとついているのに、ヒヲウたち自身がカラクリをほとんど作っていない。村のご神体であったホムラを使って敵をなぎ倒していくだけで、自分たちでカラクリを作って窮地を脱していくという話でもない。これが気に食わない。せっかくカラクリ師なのだから、自分たちでどんどんカラクリを発明していって、風陣に対抗してほしかった(戦いにすると"戦いはしない"というヒヲウの信念かに外れることになるからダメなのかな?)。または、さまざまな災難を回避していくストーリー(回避アクションもの?)でもよかったように思う(回避アクションものってめちゃくちゃつまらなさそうですが・・・)。
まぁ結局のところ、どうしてこういう意見になってしまうかはっきりいってしまうと、シシがあまりに活躍しないからである(最初から素直に白状すればよいわけですが・・)。大局的にみれば、ヒヲウたちを1グループとして、彼らが明治維新の動乱に一役買ったという空想的な面白みはあるのだが、俺は納得しない。少年アニメは、主人公の少年が自分たちがきちんと個性をもって、苦労して、挫折して、時には発見したりして成長していくという王道的なもの(スポ根に通じるもの)がないと、俺はどうも入り込めないし、感情移入ができない。ヒヲウたちはこの物語を通じて、どこまで成長したのだろうか? ただ日本中を旅をしただけで成長したと実感できるものがあまり見えてこない。物語の最初から最後までヒヲウのわがまま、"からくりは戦いには使わない"という"べんべらぼう"な信念につき合わさせていただけという感じだ。シシも序盤の仇討ちのエピソードが終わった後は、ただヒヲウにくっついていただけで、別にシシである必要がなかったと思う。つまり、ヒヲウ以外の登場人物は、別に誰でもよいのではないかと思えてしまうのだ。
シシ中心に見ていた俺にとっては、このアニメの出来は残念でならない。別に萌えアニメにしろという意味ではなく(いや、萌えもいいんですけど)、史実に沿った幕末の動乱なんてそれほどアニメに関わらせる必要もないと思う。もっとシシたち個人の成長を大切にしたアニメにした方がおもしろくなったのではないかと思うのだが(え?成長しているって? では俺の理解力が足りないってことで←ぉぃ)。
(主人公クラスは、ヒヲウ・シシ・マチだけでよいですね。この3人に風陣と、ヒヲウ+才谷、シシ+原田、マチ+誰かという組み合わせで物語を作っていって欲しいかったな・・・。ホムラもいらない。これでリメイクを希望)
(それと全52話だったという話があるが、これも×。26話も使ってこの話だったら52話使ってもおもしろくなるわけがない)
萌えどころ
シシは萌えどころは元気で健康的なところ。小麦色の肌がいい。しかし、あの肌の色、村のほかの人たちと明らかに色が違う(人種違い?)。裸のシーンでは全身小麦色だし、祭りの服を着ているので綺麗に日に焼けた体の色とは思えない。まさか突然変異で生まれた子供なんだろうか(←ぉぃ)。
また、めざとく装飾した、バンダナや肩あてやら小物もバッチリ。愛河さんの声も合っていると思う。裸のシーンまでサービスしてくれる気前のよさは褒めたいが、シシがあまり活躍しないのだけはいただけないところか・・。
使用している画像、台詞等は「機巧奇傳ヒヲウ戦記 DVD Vol.1,2,3,6,13」より引用させていただきました。著作権はBONES・會川昇、ヒヲウ製作委員会に帰属します。