 亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。
亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。
大塚の機嫌を損ねてしまった太一は・・?
登場人物
 亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。
亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。
 大塚。同年のプロボクサー。気性が荒く、人付き合いが下手。太一ともうまくいっていない。
大塚。同年のプロボクサー。気性が荒く、人付き合いが下手。太一ともうまくいっていない。
次の日。
──巌根(いわね)ボクシングジム。
太一が通っている、ボクシングジムの名前だ。
線路沿いにある2階建てのアパート風の建物で、
1階にはリングがあり、それを囲むようにサンドバッグやロッカーなどが、所狭しと並べられている。
ボクシングジムといっても、看板がなければ外からは全然分からなくて、普通の事務所に見える。
しかし狭いドアを開ければ、ボクシングに人生をかける若者が、汗を流す世界が広がっているのだ。
ここから将来、世界チャンピオンが生まれるかもしれない。
(よ〜し、今日も練習、がんばるぞ!)
太一はここ2ヶ月、学校が終わると一目散にジムに走っていた。
学校の終業のチャイムが鳴ると、みんなに気づかれないようにスッと教室を抜け出す。
不良どもに気づかれると厄介だから。
もっとも、太一のことを気にしているクラスメートなど、いないのだが。
学校からジムまで、およそ2kmの距離があり、走ればちょうどよいウォーミングアップになる。
(今日は蔵田さんは遅いのかな。大塚くんよりも早く着いて練習しようっと!)
ジムでトレーニングできる時間は、学校が終わってから18時くらいまでに限られる。
もちろん、夜遅くまで練習することは可能であったが、
ボクシングジムの費用を親に出してもらうにあたり、太一は夜は勉強をするという約束をしていた。
だから、貴重な時間を無駄にはできなかった。
『人より目立たなくていい』
『つまらない人間だって言われてもかまわない』
『ボクはただ穏やかに生きていたいだけなんだ』
ボクシングに入門する前の、太一の考え方だった。
親からもクラスメートからも「お前が頑張る必要はない」と言われ続けた。
──誰にも期待されない。
人間にとって、これほど悲しい現実があるだろうか?
そして、期待されないことで、その人間はさらにダメになってしまう。
その典型が、2ヶ月前の亀山太一だった。
太っているだけで妹から邪魔者扱いされ、メタボなだけでクラスではバカにされ続けた。
太一は成績が優秀なわけではないし、運動が得意なわけでもない。
その証拠に、体育の授業では太一が入ったチームが負けてしまう。
もし、太一に1つでも取り柄があればクラスに馴染んで、友達も出来ただろう。
だが、一度「アイツは何の取り柄もないダメ人間」と烙印を押されれば、
クラスのみんなから邪魔者扱いされ、その印象をくつがえすことはむずかしい。
所詮、学校というのは閉鎖された空間で、クラスには嫌われる人間が必ず1人はいるものなのだ。
そしていまのクラスでは、たまたまその対象が太一だったいうだけだ。
しかし、太一は2ヶ月前とは別人になっていた。
もちろん外見は相変わらずメタボでデブで、息をハァハァと切らせる運動オンチな高校生である。
だから、クラスメートには相変わらず無視されて、友達もいなかった。
昼ごはんを食べるときも、一人ぼっちだ。
──変わったものとは。
"内面"、つまり"気持ち"だ。
『人より目立たなくていい』
『だけど、つまらない人間には"なりたくない"』
『穏やな人生ではなく、激しくボクシングに打ち込みたい』
これがいまの太一の考え方だった。
ボクシングで頑張れたことが、自信につながった。
何より、大塚とのスパーリングで見せた気迫が、ジムのみんなに伝わった。
だから太一は、ジムで仲間として認められ、生まれて初めて同じ目標を持った友達を得た。
蔵田さん、先輩たち・・。
みんな厳しいことは言うけど、どこか優しかった。
──自分には仲間がいる。
そう考えただけで、太一はいままでとは違う充実さを感じていた。
頑張ることで、共に笑ったり、苦しんだり、そういう違う生き方を出来ることを知ったのだ。
だから、学校でひとりぼっちでも、体育の授業でバカにされても、もう気にならなかった。
しかし、太一にはたったひとつだけ、気になることがあった。
それはジムにいる大塚。
自分と同じ、高校2年生だ。
中学からボクシングを初めて、つい先日はプロテストに合格。
太一もプロテストの合格を目標にしているだけに、大塚の存在は大きかった。
もしかして、大塚と同じ練習をこなせれば、自分もプロテストに合格できるのでは・・?
3Rのスパーリングで対戦した因縁からか、
太一は大塚を良きライバルとして(といっても大塚は太一をライバルとは認めないだろうが)、
そしてボクシングの夢を話せる友達になりたかったのだ。
しかし、肝心の大塚は無口で、なかなか話すきっかけがつかめない。
『大塚が笑っているところなんか、みたことねぇよ』
これが大塚に対するジムの先輩たちの話。
大塚は見た目にたがわず、気難しい性格らしく、太一には心を開いてくれなかった。
(大塚くんと一緒にボクシングの話ができたら、もっと楽しそうなのに・・)
太一はいつもそう思っていた。
昨日は帰り道で大塚と一緒になったが、なぜか彼を怒らせてしまった。
(どういう話をしたら、大塚くんは笑ってくれるんだろう?
大塚くんって、学校の友達とは何を話しているのかなぁ・・)
太一はジムに走りながら、大塚のことを考えて走っていた。
・・・・。
ジムに着くと、太一はドアをあけて似合わない大声を出した。
「今日もよろしくおねがいしま〜す!」
「お、メタボ少年、今日も早いな」
ジムの会長である巌根(いわね)さんが、ミットの相手をしながら振り向いて返事をしてくれた。
さらに、先輩の市村がやってきて、太一のお腹の肉をぎゅうぎゅうと摘む。
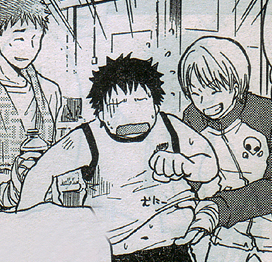
「なんだよ亀山、今日もこりずに来やがったな」
「肉をつままないでくださいっ」
半分からかっているのだろうか、会長さんたちはいつも太一を見てニッコリとしている。
「そのメタボっていうのも、やめてください」
「ハハハッ、そのでっぷりと太ったお腹を見ていると、つい言いたくなってな。
一番奥で縄跳びをやってな。そのうち蔵田も来るだろう」
太一はキョロキョロとジムの中を見渡して、尋ねた。
「あのー、大塚くんは来てないんですか?」
「そういえば、大塚はまだ来ていないな」
「そうですか・・」
太一は残念そうに視線を落とし、そのまま縄跳びを始めた。
結局その日、大塚はジムに現れなかった。
(大塚くん、どうしたんだろう? 無断で休むことなんてないのに・・)
蔵田に大塚のことを尋ねたみたが、何も知らないとのことだった。
(まさか、昨日の帰りにボクが変なこと言ったから休んだのかなぁ・・いや、大塚くんに限ってそれはないか・・)
きっと風邪かなにかで休んだのだろうと、太一は気持ちを切り替えることにした。
しかし、昨日のことを謝りたいと思っていた太一は、なにか釈然としないもの抱えていた。
第3話に続きます。次の話を読む